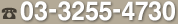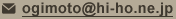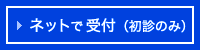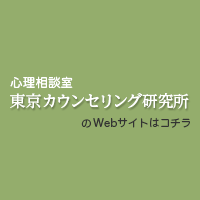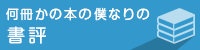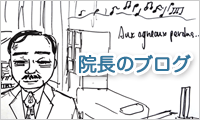|
ジャック・ラカン
 |
 5. ラカンとアリストテレス[1]
ラカンが「存在のみせかけ」として示した対象aは、アリストテレスによって示される存在者の存在を保証する究極の存在であるところの目的因としての神といった概念に結びついているのは明らかである。霊魂 âme
(この場合、霊魂の最高位に位置する理性 1) 道具や装置の取っ手となる部分、たとえば熊手やつるはしの柄、ヴァイオリンの桿など、 あるいは飛行機の操縦桿(manche è balai)、成句としてse mettre du coté du manche「強い側、有利な側につく」。またラテン語の形容詞mancus「不器用な」から派生し、上記の2),3)と重なり合うことで「不器用」、転じて「ばか」、「間抜け」を意味する男性名詞およびその形容詞も存在する。 ラカンがle mancheという語を用いるとき、この語の多義性を利用しているものと思われる。 penséeはle mancheの側に、penséはもう一方の側に属しています。このことはle manche が言葉 paroleであるということから読み取れます。※このようにラカンが言うとき、le mancheは、アリストテレス以来の目的論的世界観を支え、人間の主体を 知へと指南する手段としての言葉である一方、それはファリックな機能のみかけ上の普遍性、必然性とその限界を示すものでもある。つまりこの語により、ファルスの享楽は自慰にすぎず、それは白痴の享楽※※ であることからも、le mancheがもたらす知は、象徴界という閉域に限界づけられた、現実界を無視した独善的な知であることが示される。 ※ S20.p.96. ※※ ibid.p.75. ラカンは、アリストテレスの霊魂論から行動主義理論に至るまでをひとつの系譜のなかでとらえる。 かれはそれをclassicismeと呼ぶ。※ classicismeとはもちろん古典主義のことであるが、 ラカンがこの語で表現しようとすることはその語幹classの意味するところにある。 アリストテレスにおいては種、属はつねに同一性の原理にもとづいてとらえられる。 ある種に属すもの、ある属に属すものはつねに同じ種、属を生む。こうした同一性の原理はアリストテレスにおいて特徴的な目的論にもとづいている。 たとえば『自然学』第2巻7章においては、四つの原因のうち目的論の優位が説かれている。 |