ラカンと三値論理
はじめに
本稿は、拙稿『Sexuationの式-Le savoir du psychanalysteの1971年6月1日のアントゥルティアンを中心に』(I.R.S, no. 9/10, pp. 298-331)の続編にあたる。
ラカンが本格的にボロメオの輪に取りくむのはセミネール21巻Les non-dupes errent(1973-74)からである。論理から結び目理論へ、あるいはsexuationの式のボロメオの輪による定式化、こうした目論見をこのセミネールに窺うことができる。ボロメオの輪について、あるいは結び目のトポロジー一般についてはこの年以後も連綿と論じられ、展開されてゆくのであるが、「ラカン論理」のボロメオの輪の原型(3つの輪によるボロメオの輪)における定式化は当セミネールにて一定の成果を結んだとみてよい。ラカンは爾後のセミネールにおいては「論理」を集中的に論ずることはしていないし、そのようなマニフェストを強く感じさせるものはないのである。「性的無関係」のテーゼが覆されることはないし、このテーゼに関する量子式を散見することはでき、この問題のディテールにおける記述やボロメオの輪の構造において進化はみとめられるものの、骨格に当たる部分に大きな修正が加えられることはない。
0-1は1971-2年のセミネール、アントゥルティアンの中心課題であったが、ではS1-S2はどうか(S1-S2を0-1とパラレルに捉えることはできないが、原抑圧との関係でいえばS1は0と深くかかわり合っている)。「知」というものをどのレヴェルで捉えるかにかかってくるが「無知」という到達不可能なものへの方向性が→2として示されるとしても、0の後継数は1だが、1の後継数は存在せず、2はラカンにとっていわば鬼門となる数字となる。ふたつの輪あるいはふたつのトーラスを結び目性nodalite(ボロメオの輪はいわゆる結び目のトポロジーにおける「結び目」ではない。しかし三つの輪がバラバラにならないようにまとまりconsistanceを保つことが可能なのはのはこの結び目性によるものであり、中心に位置する「締め付け」coincementは三つ葉の結び目n?ud de trefleと同様の構造を持っている。それゆえボロメオの輪の構造を「三つの輪とひとつの結び目をもつ」ものと規定することにする。本稿において以後、結び目n?udと結び目性nodaliteを区別なく使用することとする)で繋ぎ止めることはできない。
ふたつのトーラスの絡み目deux tores enlacesは既に30/05/1962で登場する。神経症者においては、目差される対象が?他者?の要求であり、神経症者は捕えることのできない対象aを捕えることを要求し、この対象は?他者?の対象でもあるのだ。1976-7年の“L’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourre”ではこの構造の切断、平面化、裏返しといった操作が示される(demontrerではなくmontrer)。ヴァプローは、ラカンがL’Etourditで言及している切断の操作によってこのことは既に示されているとして、自らさらに仔細に検討している(Jean-Michel Mappereau, Etoffe-Les surfaces topologiques intrinseques, p.200~)。トーラスの表面に穴をあけ、トーラスの壁を二層に分離し、内層のトーラスが外層のトーラスの帯(穴をあけたことにより単なる帯になる)で覆われるかたちとなる。ついでこの帯を裏返しにし、以上のプロセスとは逆のプロセスを施すと元の構造と全く同じ構造が出来上がる。この特性を利用してトーラスの中空の部分を囲む壁を2回転させるかたちでトーラスの環を一周するような線と環構造に沿った円形の線を繋げる。これがラカンがL’Etourdit述べている操作(Autres Ecrits, p.470)であることが説明される。この場合、帯はメビウスの帯となる。ラカン自身が「関係の不-意味/方向ab-sens」(ibid., p.468)注1)という新造語にこめた両義性、メビウスの帯の方向性の欠如、女性における性のpas-touteへの到達不可能性は、この操作により明らかにされる。トーラスの中空のガス抜きevidementによる平面化mise a plat, 再膨張あるいは裏返しといった操作の連続にもかかわらず、トーラスの構造は不変なままである。二足性bi-pode(ibid.)では裏表にするにしても、元の木阿弥なのである。2という数字は自己言及的にしか2といえない欠陥を持った数字である(12/03/1974)所以である。性についても無意識についても、「それはふたたびもとの場所に戻ってくる」とされるラカンの現実界の定義からすると、2は性的無関係により不可避的に間隙failleを生じさせるもので、そこへの到達もそこからの展開も叶わない数ということになる。1977-8年のセミネールのタイトルL’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourreの頭の部分は不成功insuccesという語を読み取ることができる。そのタイトルと同様、ここでのラカンは押し並べて悲観的であるが、われわれはまだその4年前の時点にいる。
ボロメオの輪は最低限三つの輪を必要とする。1→2という道は断たれたが、3からはその後継数4、その後継数???と無限大にまで環を増やしてゆくことができる。ミレール版Encore, p.113におけるいわゆるn?ud borromeen generaliseによって示されるものである。
ディ(-)マンシィオン
ボロメオの輪の特性を明らかにしよう。ラカンはボロメオの輪における三つの環をそれぞれ、1953年以来の三つの領域である象徴界、想像界、現実界に割り振る。しかしながら特定の輪を、これは象徴界、こちらは想像界、残ったこれが現実界とすることはできないとしている(08/01/1974)。輪はそれ自体として弁別的特徴はない。ひとつの輪についてラカンは質quqlite注2)と呼ぶ。ボロメオの輪のdit-mansion注3)を構成するのは象徴界、想像界、現実界なのであるのだが、このdit-mansionはデカルト的空間としての3次元dimensionではない。
側にも見ることも、感じることも、示すこともできない。対象のnon spheriqueな事実を示すものである。いっぽう水平線である象徴的なものにかかわる線については<他者>が関与してくる。赤ん坊は、鏡像(鏡が平面であることからこの像は虚像である)を見た後に、必ずといってよいほど、かれ(かの女)を抱いている大人(母親)の方に振り返る。その都度、<他者>の承認を求めるのである。理想自我は鏡像、イマーゴであるが、自我理想は<他者>の欲望が関与して来るもので、ちょうど前者は垂直線、後者は水平線と関係している。ラカンは光学シェーマを用いて、究極的には人間の超越論的感性の限界を示し、この限界を超えるためにはどうしてもトポロジーに頼らなくてはならなくなり、まず曲面(鏡は、平面鏡であろうと凹面鏡であろうと曲面上で映し出す効果をもっている)のトポロジーを導入したわけである。
人間が観ているフェノメナールな世界とは ラカンの言うdebilite mentale, vice de structureの効果なのである。遠近法も自明のこととされているが、なにも遠近を遠くのものは小さく見える、近くにあるものは大きく見えるといった図式で捉えなくても目測可能なはずである。例えば遠くのものはぼやけて見えるあるいは暗く見える、近くにあるものははっきり見えるあるいは明るく見えるでも遠近感は生まれる。人間の遠近法では消失点point de fuiteが必然的に存在してくるが、人間の視野がもし360度近くあり、網膜も凹面ではなく凸面だとしたら、消失点もなくなるし、自分を映し出すため、鏡は平面鏡では役に立たず、視覚器官がやはり球形であるとすればその中心点から等距離にある球面の内部(つまり凹面鏡となる)にすっぽり入り込む必要がある(もしそうなれば、平面鏡の場合とは異なり、背中が映らないなどということはなく、全身が映し出される)。完全に360度の視野というものを想定すれば、そこには左右という方向性orientationは意味のないものになる。いずれにせよ人間は平面というものにこだわる。鏡以外にも、文字が書かれている書物、タブロー、写真、映画のスクリーン、地図(実際、地図を作成するためには多様体理論を援用しなければならない)そしてユークリッド幾何学 … 平行線の定理をめぐって非ユークリッド幾何学は生まれた。
人間の思考にとって「見る」という営為がどれだけ重要視されてきたかは、例えば理論(「理論理性」の理論からしてそうある)、theorieの語源を調べると理解できるだろう。ラテン語のtheoriaはさらに古代ギリシャ語のtheoriaから派生してきており、これはI.見る,観察する、調べるという行為、II.観劇(Le RobertのDictionnaire historique de la langue francaiseによると宗教劇に遣わされた役者グループで、この劇で神託が告げられた、とある。観想〔プラトン以降〕という語義があり、同辞書ではtheoriaもtheoros観客から派生した語であるとしている。また思弁的speculatifという語も俗ラテン語のspeculativusから借りてきた語で実践的に対する反省的、理論的を意味する。動詞speculerはラテン語speculariからの借用で、これは、「観察する」、「ねらう」、「スパイ的監視をする」という語義があり、specula(「観察を行なう場所」、「高所」の語義があある)から派生したもので、さらにこの語もspecere(「注視する」という語義がある)から派生したものである。speculerにはspecutacle, speculaireといった関連語があり、speculaireはラテン語specularis(「鏡の」という形容詞)からの借用で、それはspeculum(「鏡」、転じて比喩的に「忠実な再現」、「像」という語義となる)がもととなっているが、現代フランス語では、speculum anal肛門鏡, speculum nasal鼻鏡のように、医療機器の名称として用いられている。人間は3次元空間に埋まっているplongeとよく言われる。
だがラカンがいうvice de structureにおいては、往々にして次元をひとつ下げて見ないとものごとが理解できない。MRIなどにおいては、MR信号を周波数変換してからディジタル変換して得られた実数部と虚数部からなる、つまり複素数からなるraw dataの集合 - これをk-spaceと呼ぶ - を二次元フーリエ変換してはじめてMR画像になるのである。もし人間にこのような欠陥がなければ、raw dataの時点で、あるいはせめてもk-spaceの時点でことを把握できるのではないであろうか。
カントの『純粋理性批判』の本文は超越論的原理論 Der tranzendentalen Elementarlehre、第一部、超越論的感性論 Die transzendentale Asthetikというタイトルから始まる。Asthetikという用語はBaumgartenが1750年の自著の第一巻をAstheticaと命名したことにより普及する。古代ギリシャ語のaisthetikos、つまり感覚aisthesisによる知覚あるいは理解の能力を有するものといった意味をもつ語からこのドイツ語が生まれた。現実の対象すなわち物自体Ding an sichが心意識Gemutを触発affizierenすることにより感覚Emphindungが生まれる。感覚Enpfindungを介して現実の対象に関係するような直観を、経験的empirischと呼ばれる直観Anschauungとカントは書いている。この経験的直観による無規定な対象を現象Erscheinungと呼ぶ。ところで現象において感覚と対応するところのものをカントは現象の質量Materieと呼んでおり、一方で現象の多様な内容をある関係において整理するところのものは、現象の形式Formと名づけ、前者はa posterioriに与えられ、後者はa prioriに与えられているものだとする。つまりこの形式は、一切の感覚から分離して考察されるべきものとされる。「 … わたしがある物体の表象Vorstellungから、悟性Verstandの思惟するもの、例えば実体Substanz、力、可分性のようなものを分離し、また同様にして感性に属するもの、例えば不可入性Undurchdringlichkeit注4」、硬さ、色等を分離しても、かかる経験的直観のなかでまだわれわれに残されているものがある、それは延長Ansdehnungおよび形態Gestaltである、そうしてかかる空間的なものが純粋直観に属するのである。空間という純粋直観は、感官や感覚などの対象が実際に存在していなくても、われわれの心意識における単なる感性的形式として、ア・プリオリに成立するのである」(カント『純粋理性批判』、上、篠田訳、岩波文庫、87頁。そしてこのア・プリオリな感性の諸原理に関する学をカントは超越論的感性論transzendentale Astetikと呼んでいるのである。
ところで、続く第一節 空間について §3空間の先験的解明においてカントは、「空間は三次元をもつ」という命題は経験的な判断あるいは経験判断Erfahrungsverteilではあり得ない、ましてこの種の判断から推論せられ得るものではないとしている。ランベルトとの交流もあったカントは,非ユークリッド幾何学を無視していたわけではない。しかしながら純粋直観としての空間は三次元空間に限定している向きがあり、非ユークリッド幾何学を悟性による思弁的空間、もしくは経験的すなわち物理的空間とみなしていたと思われる、と高峯一愚は『純粋理性批判入門』(論創社)、116頁で述べている。後に論理実証主義は、ア・プリオリなものはカントのいうように総合判断を生み出すことはあり得ないという批判を展開するし、一方、一時期のフッサールはカントに好意的ながらも、幾何学を空間直観から完全に解放し、算術と同じ純粋な論理的学問にすることを望んで公理主義者ヒルベルトに極めて近い立場に向かったことからすれば、空間については、直観に基づけば錯誤に陥るということを言っているに等しいわけで、これでは逆にカント批判になってしまうことにかれは気づいていたのかどうか疑問となる(http://www.hss.shizuoka.ac.jp/shakai/ningen/hamauzu/kukanron10.htm参照)。
ラカンが強調しているのは、分析的経験というものから出発すれば、カントのいう曖昧な「経験」を再検討しなくてはならなくなり、分析的空間には、3次元空間では解決できない問題がもちあがり、つまりこの問題は専ら平面に立脚するユークリッド空間には還元できず、まずは曲面のトポロジーに依拠することになったわけである。schema optiqueを光学シェーマと訳してきたが、視覚シェーマと訳し直してもよいかもしれない。鏡つまり平面鏡は、平面という面が曲面のなかでは特殊例であることから規定される。他の曲面のうちには球面をふくめて閉じた面が存在するが、平面は断裁しないかぎり無限大、あるいは際限のない曲面ということになってしまう。人体側の視覚器官、つまり眼球には、水晶体という凸レンズがあり、網膜は凹面になっている。視神経から外側膝状体、視放線、主に後頭葉に局在する視覚各領野、視覚野からなる視覚に関する神経系統は他のある種の動物と較べても、現実le reelをかなり歪めて現象(カント的な意味の現象)を、ア・プリオリにであれア・ポステリオリにであれ、規定していることは事実である。もちろん人間には純粋に視覚に直接寄与するシステム以外のシステムも存在する。例えば前頭葉の右側にある46野は視覚をなんらかの精神活動に結びつけるための重要な領野なのであろうが、これとてあくまでvice de structureである人間的精神活動に叶っているものなのである。
論理実証主義の学徒とは異なり、ラカンがカントを批判しているのは、かれの超越論的(先験的)感性論にあり、超越論的論理Die transzendentale Logikの批判であり悟性Verstandの批判ではないということである。因に、高峯一愚氏が言っているように、カントの理性には、純粋理性、実践理性と別々の理性があるとするのは間違いであり、少なくと三部作のうち最初のものは純粋理論理性についての批判であり、「批判」の対象とされなければならなかったのが受容性を含む「感性」と自発性を主としてその本質とする「悟性」とに分けられねばならなかったのだが、(純粋)実践理性批判」については、それは専ら唯一の自発的能動的機能でなければならないから「批判」の対象とすることはできず、「批判」されなければならないのは、むしろ受容性を含む感性の影響下におかれている「実践理性一般」でなければならないことにある時点でカントは気づいたとのことである (『カント実践理性批判解説』、高峯一愚、論創社)。
ラカンは「不安」のセミネールにおいて、人間の視覚器官である眼の欠陥性について分析しているが、それをここで引用しておこう。
眼の次元に戻りましょう。つまり、空間の次元にです。空間といっても、あるカテゴリー、超越論的感性という硬直した形式のもとに提示される空間ではありません。たしかに、カントへの準拠は、われわれにとっても、極めて有益とはいえないものの、少なくとも極めて都合よくことが運ぶようにできていますが。そうではなく、それとは別の、空間が、われわれに、欲望との関係において特徴的なかたちで示される場合です。? 欲望そのものの機能の起源、基、構造は、あるスタイル、ある型においてその都度説明されるべきです。中心に据えられている件の対象、小文字のaは、単に分離されたものとしてではなく、省略され、欲望がこれを支えるその場所とはつねに離れた場所にあるものですが、それでも欲望はこの対象と深い関係にあります。この省略といった特徴は、眼の機能の次元においてほど截然と現れてくることはありません。それゆえ、欲望の機能を全面的に支える幻想は、常に、視覚的モデルとの近縁性で示されるのです。?空間においては、それでもーそしてこのそれでもという言葉で、言うべきことは余すことなく言うことを含ませてーみかけ上は、なにも分離されないのです。空間は同質なものです。われわれが空間という語で身体、われわれの身体を構成し、そこから空間の関数が現れますが ・・・ (sic) 観念論ではありません。否です。なぜならば、空間は精神の一関数une fonctionなのであり、つまり空間がバークリー主義をも正当化してしまうようにです。空間は断じて観念ではありません。空間は、なんらかの関係性をもっていますが、精神と関係しているのではなく、眼とです・・・ (sic) この眼球にも役割fonctionがあります。なんのかですか言うと、それはぶら下がっているのです。この眼球、われわれが空間を構成するや否や、われわれは、いわば、この眼球を圧縮して無に帰してしまわなくてはなりません。物理学者がするように考えてみてください。物理学者が、黒板に、ある物体の関数を、この黒板の広がりのなかです、示すようにです。ある物体、物体ならなんでもよいのですが、それはなんでもないものですCa n'est rien。それは点です。それは、それでも、異質ななんらかのものによって、空間の諸次元のなかに閉じ込められているはずなのです。そうでなければ、個物化/非可分化individuationの解決不可能な問題を生んでしまうのです。わたしがこのアンティノミーを問題外として無視の態度を取ってきたのをご存知でしょう。空間のなかの物体、それは、少なくとも、不可入性impenetrable(undurchdringlich : Kant)という性質で示されるものです。そこにはある種の実在論が見受けられますが、これはまったく手に負えません。ご覧のとおり当然の成り行きなのです。だからわたしはカントのアンティノミーを繰り返すようなことはしないのです。空間を関数化することは、この分割不能な単一性を、点として捉えるとしても、やむないことですが、これをアトムと呼ぶことになります。もちろん、この名称を、物理学で用いている同一の用語と一緒にはできません。ご存知のように、アトムはけっしてアトミック、つまり分割不能ではないのですから。? 空間という概念は、究極の分割には抵抗を示すといった措定以外に存在理由はありません。当たり前のことですが、空間は、不連続性を仮定するとき、つまり単一性が一度にふたつの地点を占めるということがないとする場合のみ有効な概念として働くのですから。
以上のことから、われわれにとって、なにが言えるのでしょう。こうです、この空間的単一性を認めるわけにはいかないということです。しかる場所に位置し、他のところには移らない点として示される空間的単一性は、小文字aとはどうあっても相容れないものです。
いまわたしはなにについてあなた達に話しているのでしょうか。わたしは、今からでも、耳では聞き知っている捕獲網のなかにあなた達を突き落とそうと思っているのですよ。つまり、i(a)の形で表されるわたしの像mon imageがあり、 <他者>の前にわたしが居て、そこには余りresteはないということです。わたしには、そこで、わたしが失ったものを見出すことができないのです。これが鏡像段階の意味するものです。この図式の意味は、あなた達のために捏造するためでして、この図のどこの場所であるか、もうすっかりお分かりでしょう。ことわるまでもなく、図は、理想自我と自我理想の機能の根拠を示すためのものなのですから。これらの機能はどのように働くのかと言いますと、主体と<他者>との関係において働いており、鏡の関係、この鏡を<他者>の鏡と呼ぶことにしますが、この関係が支配しているときに働くのです。
この像aは、そのかたちからi(a)、つまり鏡像でして、鏡像段階において特徴的な対象であり、誘惑以上のものを持っており、各主体の構造にだけでなく、認識の機能にも結びついているのです。つまり、この像は、閉じたものであり、いうならば、囲まれたものなのです。また、ゲシュタルト的、つまりよいかたちに描かれているのですが、よいかたちの経験、この領域に特徴的な経験ですが、この経験によって築かれたゲシュタルトの機能は、罠が仕掛けられているということを警告もしているのです(???) (22/05/1963)。
結び目についての次元を考えてみよう。結び目を紙上に描く場合、あるいはディスプレイ上での図でもそうだが、mise a platという次元をひとつ下げる操作が加わる。人間の視覚には厚みvolumeを捉える機能がおそろしく不足している。そのため結び目において線が交差するところでは一方の線を切断し、切れ目がある線の方がわれわれがそれを見ている側からは遠くにあるという約束ごとができている。繰り返し言うが、人間が三次元の空間に浸かっているplongeと思い込んでいるひとは多いだろうが、この臆見をかりに正しいものだとしても、人間はこの三次元を、ひとつ次元を下げ二次元的に捉えよとする傾向がある。ロボット工学で2,5次元という言い方が定着している所以である。
Les non-dupes errentにおいてラカンは想像界に数字2を割り振る(14/5/1974)が、想像界にどっぷり浸かるとさらにこれは2→1となる図式へ向かうおそれがある。自己愛は2者において1者が成り立つとする迷妄に基づく。
ここでは、ヴァプローがポアンカレに倣ってトポロジーにおける次元を定義しているので、これを引用しておこう(Jean-Michel Vappereau, ibid. p.13-15)
トポロジーの対象の次元は切断によりその対象が(いくつかの部片に)切り離される際の切断の次元によって定義される(???)
一次元は点であり、ユークリッド幾何学においては次元をもたないものである。いくつかの点は線を成し、これが一次元、線の組合せは面を成し、これが二次元、曲面を寄せ集めると立体を成し、これが三次元となる。以上のような説明は直観的な点が残る(???)正確に定義するにはこれと逆の方法を採るべきである。つまり対象がn次元であるというのは、n-1次元の切断により分断されふたつに分けられるということである。
ボロエオの輪、現実の科学/知、論理
デカルト的空間の座標軸において中心に添えられるのはx,y,zの三つの軸が交差する点である。線を実在するものと仮定するならばこの点も実在する点である。ボロメオの輪の中心にあり、三つの輪をそれぞれ3方向にひっぱると中心の穴は点に近づく。しかしいくら引っ張ったからといって、つまりラカンの表現に従えば、言語を総動員してこの穴を塞ごうとしても穴は現実界に属するもので、これを塞ぐことは不可能である。そして三つを纏めて捉えることで、これが前述した質であり、質は「いち」でしかない。この「いち」が現実界に属す。
真理は、事実、今のところ論理にありますが、矛盾無しという訳には行きません。論理は真と偽という二元論に拠っています。真は知の想定に過ぎないのですが、それはイメージで示される知で、 - 知の意味sensはそこで示されるのです - (真、偽といった)二つの要素の結合にあたります。
それゆえ、もし1が、三分の1 がそこに加わって結合することがなければ、この知は想像的なものなのです。さきほど申しましたように、加わる輪は同じタイプの輪ではなく、結び目をもたらす輪です(8/01/1974)。
more geomitricoが支配した時代はあまりにphenomenalな面を重視していた。mesureとは尺度だが、ユークリッド空間では距離として示される。ラカンによればそこでのsuppositionという語、さらにsubstanceとかsujetとかラテン語の接頭辞subがつく語はl’Imaginaireの下に置かれていたといえる。
トポロジーにおいては距離とかこの距離を計測することを断念する。トポロジーにおけるsuppositionはconsistanceであり、近傍の定義から展開される空間概念である。空間が柔らかいという特性malleabiliteや連続的変形deformation continueもこの近傍から導き出される。
「知を想定された主体」sujet suppose savoirという表現も以上の補足的説明ではっきりしてくる。古代ギリシャ語hypokeimenonをsuppositionと仏訳することが可能だと。主体は想定されるだけのものとなり、それが存在するexisterはするとしても、語る存在etre parlantでであろうが、これもラカンにとっては冗語であって、動詞のetreはparlerがあってはじめてetreなのであり、etreという動詞がなければ存在と言おうとそうでないだろうとetreはないものとなる。
存在l’Etreが想像的なものとして - それを「いち」とするならば、これはプロティノス的一者となる - これを退けるとしてexistenceはex-sisterすると表記することにより、量子記号(∃) - ラカンはqunatificateurとは言わずquanteurと言う - はオリジナリティーを持つようになる。ex-sisterはつねに場所を移動するという意味合いからこれが順序を換えることが可能なこととなり、つまり彷徨える者つまりnon-dupes errentであるものをまとまりconsistanceのあるものとしてdupeとなって捉えることがこの年のセミネールの課題なのだとされる。象徴界,想像会、現実界の三つ巴から質問を出すが、答えからこの質問は発せられるのであり、それは現実界なのである。無意識についての知とは現実界を捉えようとすることとされる(15/01/1974)。
ラカンにとっての論理学とは「現実の科学」la science du reelと規定される。「真」、「偽」にかかわる命題論理の嚆矢はアリストテレスであり、いわゆる『オルガノン』(この名称は3世紀ディオゲネス・ラエルティオスによるものが初出とされるが、時代によってその構成は異なり、あるときは、『弁論術』, 『詩学』も含まれていたが、通常は、『カテゴリー論』、『命題論』、『分析論前書』、『分析論後書』、『トピカ』、『期弁論駁論』から成るとされる)においては「真」toalethesという語は多くのページにおいて散見される。伝統的論理学はアレクサンダー大王、教皇シンプリキウス、ルリウス・パキウス・デ・ベリーガ、ピエール・デスパーニュ、トマス・アクイナスと受け継がれていったが、ラカン曰く、アリストテレスの後に続く論理学書はそのページの半分は『オルガノン』の注釈という体裁をとったものであれ、これは本当の注釈ではなく噛み砕いて平易に読解できるものにしたにすぎないばかりか注釈あるいは注釈の注釈というものを通じて解釈のずれは深まる一方となったと。
三段論法(古典ギリシャ語syllogismosは「計算」「推論」「演繹の結果」の意)は一見ボロメオの輪を予感させるもののように見えるが、ラカンからすれば、アリストテレスは現実界を曲解して三つは二組ずつでそれぞれセットで揃っているもので、三つは同一中心をもったconcentriqueものと看做せると(1974/2/12)。
精神分析的言説と論理学は「言われたこと」ditsに立脚するものであるが、この「言われたこと」からその意味を抜き取るということで特徴づけられてきた。現実界について知るにはこの方法しかないとラカンは言い、しかも論理の道筋をたどるには書字l’ecritに頼るしかないとする。
現実界において本当のことを言うle dire vrai(無論vraiとは命題論理における「真」であることを踏まえておかねばならない)とは溝を穿つ言い方で言うことであり、性的関係を書くことは不可能である、性的関係が存在しないことを補う言い方である。性的関係を書くのが不可能なことが永遠に穴を形成しこれからも形成することとなるのある。
分析的言説においては、というよりは端的に言って、分析主体が語ることばにおいて本当のこと/真を言うとは、様相としては偶然のできごとである。しばしば分析主体は失言をするが、これは恋文と関係している、つまり転移が働いているからであり機知mot d’espritとはそういうものだ。
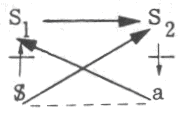
主人の言説においてS1(アリストテレスに即して言えば、これは前提命題protasisに相当する、少なくとも主人にとってはそう看做されるものといえる)から矢印はS2に向かう。しかしながら、精神分析的言説の教えるところによれば、S2は無意識的知であり、これは主体にとって無知の知である。ただ残り滓としてのa、plus-de-jouirとしてのaからS1(aの効果からラカンはrainureという語を選んでいる。“L’identification”のせミネールにおける古代人における刻みを入れた骨についての件を思い起こそう。切り込みとはtrait unaireに他ならない)に向かって、一方でS barreからもS2へと矢印が引かれ、これ以外には矢印は存在せず、S1とS barre、S2とaとのあいだは遮断されている。知は精神分析においては無意識(の主体、つまりS barreについて)の知なのだが、これはシニフィアンについての知となる。 アリストテレスにおいては推論syllogismosはすべて論証apodeixisであるとはかぎらない。通念endoxaから出発するものは弁証である(『前書』は論証と弁証双方に共通する推論を扱うが、『後書』は論証そのものについての議論だとされている)。論証とは必然なる原理から出発する推論なのだが、ラカンにとって必然はne cesse pas de s’ecrireで、いわば淀みのない流れでフロイトの『科学的心理学草稿』においては慣性法則が当てはまるoニューロンでの流れである。分析主体の語る言葉もたいていはこの流れに乗っているのだが、ときとして出来ごと evenementが起き、signifianceではなくsensがもたらされる。それは対象aとの出会いであるが、繰り返し言うが、この出会いは出会いそこないの出会いである(S barreからaへの矢印は遮られている)。無意識の知は性的関係がないことを補うため、ひとは分析的言説において正しく言うのだが、この正しく、あるいは真である言説による推論が現実界の知へ向かうとすれば、これは論理的構造を持っているわけであるし、それは書かれたものl’ecritによってなされるのだが、これは挫折を余儀なくされる論理である。しかしフロイトは『科学的心理学草稿』においてシェーマによってヒステリーの知を理解しようとしたが、ラカン曰く、レミニッセンスということばで説明したつもりになっている。
現実界に書かれている論理は、性的関係へと通じる道を遮る方向にことさら向かう。ことさらこういうこととなるのは、身体に寄生しているファロスによって分析的言説が規定されているからだとラカンは言う(La Troisieme, 31.10.1974 / 3.11.74)。ファロスの法は所詮シニフィアンの法に、象徴的去勢の法に限定されているわけで、「書かれないことを止める」という偶然の様相を経験する。
オルガノンとは道具のことである。精神分析も道具が必要でありこれもオルガノンである。ラカンならずともこれが性器organe sexuelであるとの連想が働くし、それは男性性器に違いない。この道具で探りを入れる訳であるが、殆どうまく行かないのである(12/02/1974)。
セミネール『アンコール』において、ラカンはアリストテレスの思想をmanche(男性形)の思想だとしている(seminaire XX“Encore, ed. seuil, p.99)注5)。le mancheは取手、飛行機の操縦桿など人間が操作できるものでその操作に際して手で掴む部分のことを表すが隠語として男性性器の語義がある。まさしくファロスの言説、論理である。ラカンによれば、『霊魂論』において書かれていることは端的に言って「ひとはその霊魂で考える」である。霊魂とは神のものであり、あるいはアリストテレスの思想とも取れる。かたちは変え、ライプニッツのモナドロジーもこのパラダイムから逃れることはできなかったといえる。無意識は「存在が考えるということではなく???存在が語ることにより、享楽に到っているが、さらに付け加えれば、この無意識自体、そのことを全く解っていない」(ibid. p.95)となる。「不動の動者」として神は動因であるのであるが、『形而上学』ではこの動因についてのとんでもないトリックが明らかにされる。神は実は動因などではなく、その他の存在、それ以下の存在が神を憧れて勝手に動いているのだと。『二コマコス倫理学』においてラカン的にいえば最高の享楽は神において現実のものとなっているのだが、人間がそれを求めようとすると中庸という概念によって示される。快楽が享楽と同じということになるが、これは逆説的ではあるがファロスの享楽のことである。それは享楽もどきであり、その実、結果的に緊張の緩和のことなのであるから。
もちろんラカンにとって「不動の動者」など存在しない。真理は発見できるものではない。アリストテレスは実はファロスの享楽を信じ、「他者」をこれによって享楽へと導くことができる/「他者」とともに享楽へ向かうとができるとするファロス中心的幻想をもっていたとして、かれはそれに気づいていなかった思想家だった注4)として、「 ??? 本当のものは全体に還元されない。級数は収束はするが」??? le serieux ne serre pas tout. Il serre de pres la serie(19/2/1974)。「魂」ではなく「脚でもって考える」(La Troisieme)とアリストテレスに厭味を言う(ペリパトス派とは名ばかりだと言いたいのだろう)ラカンは主体的に動くことによって「求める」。ボロメオの輪は緩い構造structure a la noixをもっているが、どうあっても中心部分の締め付けcoincementは実体のある点とはならない。引っ張ったり緩めたりできるボロメオの輪であるが、これはどう定義すればよいのかが問題なのでなく、「つくることができればよいのだ」 (ibid.)。それは発見すべきものでなく、発明するものである。
ブール
ジョージ・ブールは、たしかに論理学が現実界の科学/知であるべきとするラカンにとって、記号と数字だけで(つまりsensをそぎ落とした)式を表したことで評価されるべき点がある。しかし、かれは世界を数字の1で表し、この1と変数xで世界内のものを表記しようとした。ブールは世界を批判のないまま定立させてしまった。この年のセミネールでラカン自身がボロメオの環で証明できたと思っていることは、形而上学との対峙である。ラカンにとって形而上学とは、世界というものにおける主体を定義し、その上で主体の知connaissanceによって特徴づけられるものとされる。精神分析の実践から得られた諸要素 - 四つの言説で用いられる_S barre, S1, S2, a - を組み合わせてできたものは純粋の場所、純粋のトポロジーに属するものとは区別されるものであるとラカンは断っているが、分析家の言説にはエク-シスタンスの場所を与えようとしている。
ブールの式を検証する際に、ラカンは、象徴界における1(Un)が世界l’universにおける個別化されたものすべてに支えられているのかと自問する(14/5/1974)。ブールは自らの式において、1が真理を分有するものをカヴァーすると主張できるなどと思っているのであろうか。1 - xが真である言表からxを引かれたものだとして、xは変数だとしても、これはいわゆるダミー変数であり、xが1か0であるゆえ、つまり真か偽かのどちらかになり、1 - xも1か0であることになり、結果として両者には違いがないことになってしまう。ブールの式をあくまで数学的に扱うと、x(1 - x)= 0さらにx - x2 = 0でx = x2が得られる。
でラカンの式となる。
x (1 - x) (1 + x) = 0
x - x3 = 0
x = x3
世界にxを足すという解釈をするならば、このxはエク-シストすることになりはしないか、とラカンは自問する。精神分析の経験からすれば、対象aによってひとつ余分un plusがつねに生ずることになる。となれば、?1?, le Unは世界だとして、集合だと看做せるかどうか疑問である。
ラカンはブールも(1+x)ないし(-1-x)あるいは-(1+x)を第三項として付け加えることに想到することができたのだが、後でこれを抹消したと言う注5)。二値論理が前提とするのは、意識の相関者としての世界の定立であり、これはファロスの享楽が1を真=真理として現出できるとする矜持だとラカンは言いたいのであろう。ラカン自身の式における真理値、1,0とは別の値-1はex-sisteするものであり、これはファロスの享楽の効果としてのa、剰余-享楽である。それはブールの思考からすり抜けた(-)、否である。それは「半ば-言う」において言われなかったものである。sexuationの式に立ち戻り、ラカンはこのnonをファロスの機能に対するnonと発する言、すなわち去勢のnonに関連づける。循環構造が出来上がっているが、これは悪循環と言ってよいであろう。
ラカンと三値論理
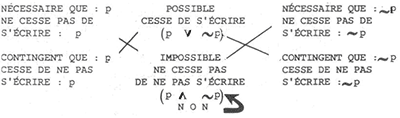
「不可能」とは矛盾率¬(p∧¬p)が成り立たない現実界の知/科学scienceについての様相である。三値論理においては(p∧~p)が示される。ラカンにとって不可能とは「性的関係」が不可能ということ、無意識の知が不可能ということである。因に直観主義論理においては、否定除去型の背理法「¬Aを仮定して矛盾が出る、それゆえA」は認められないが、否定導入型の背理法「Aを仮定して矛盾が出る、それゆえ¬A」は認められる。Brouwer(以下、いわゆる直観主義論理については『ダメットにたどりつくまで』, 金子洋之著, 勁草書房に負うところが大である)は、排中率は妥当でない(排中率の二重否定¬¬(A∨¬A)が成立する)が矛盾率は妥当だとする(金子によれば、直観主義論理は真の意味での三値論理ではないとされる)。A(が存在すること)が証明も反証もされていなければその存在についての排中率は妥当しないとする。Brouwerの提出した例は問い「xのy乗が有理数となるような無理数x、yは存在するか」である。x=y=ルート2とするとxのy乗=ルート2のルート2乗となるが、これは有理数か無理数か証明できない。もしこれが無理数だとすると、y=ルート2のルート2乗とすれば、xのy乗=(ルート2のルート2乗)のルート2乗となり、つまり2となり、これは有理数である。ヒルベルト的無矛盾に従えば、排中率を用いて、この問いの答えはyesと証明できるが、これは「存在=無矛盾」の立場であり、Brouwerの立場「存在=構成」に従えば、存在すると主張されるものを構成するか、もしくは構成するための実行可能な方法が与えられなくてはならないこととなり、ルート2のルート2乗が有理数か無理数か証明ができないのだから答えはyesでもnoでもないことになり、ヒルベルト的立場は退けられる(同掲書pp.51-53)。
ラカンは19/02/1974のせミネールにおいて、「発明する」と言う物言いが直観主義の「構成する」construireの影響を窺うことができると思われるのではと断りを入れている。仮に無意識の知がまだ確立されていないものとする(将来この知が確立される可能性があるとする)ならば、これは「認識史」の問題であり、「知的状態」としては証明がなされていないということになる(野矢茂樹『論理学』169頁, 東京大学出版会)が、金子はこのような「認識」、「知」(フランス語ではconnaissanceとなろう)が問題となるのは「存在の論理」に対峙させるかたちで示される「認識の論理」を標榜するHeytingの方であり、Brouwerであれば「心的構成活動として体験される」という言葉に置き代わるだろうと言っている(ibid. p.59)。いずれにせよ、無意識が問題にされるのは「存在」のレヴェルではなく(Cathelineauによれば注7)、「発見」decouverteは「存在」が前提となるとしている)「無」のレヴェルでであり、そこに知があるとしても、それは無意識の形成物にすぎず、無意識そのものはex-sisteするものとして示される。
翻ってラカンは、同日のセミネールにおいて、Hintikkaがやってはいけないことをやってしまっているが、そのやってはいけないことをラカンもやっていると述べる。
ヒンティッカの Time and Necessityが上梓されたのは1973年であり、まさにこのセミネールLes non-dupes errentと同時期のものであるが、ラカンは、かれがアリストテレスの命題論理には既に様相論理が入り込んでいると見抜いていたことについて、自分より先んじていたと評価する。
アリストテレスの『命題論』の「明日海戦が云々」といった命題をめぐって、これは論理学者に未来偶然といった問題を提起する命題であり、Hintikkaの論理展開の出発点である。ヒンティッカはアリストテレスには2種類の「可能性」があり、そのうちのひとつがヒンティッカの言う狭義の可能性possibility properであり、様相論理において検討すべき課題となるとしている。(Hintikka Jaakko, Time and necessity : studies in Aristotle’s thory of modality, Clarendon Press
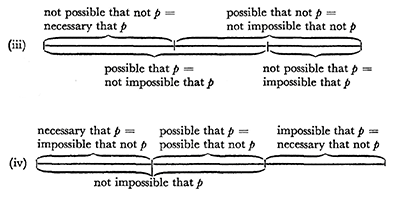
ヒンティッカのダイアグラム (ibid. p.28) によれば、命題pが可能ということは、ダイアグラム(iii)では、線の上部の左側、①not possible that p = necessary that pおよび同右側、②possible that not p = not possible that not p、線の下部の左側、③possible that p = not impossible that p, 同右側、④not possible that p = impossible that pがあり、ここでは「可能」は③つまりnot impossibleであり、①全体と②の一部を包含している。一方ダイアグラム(iv)においては、同様に線の上部の左側、⑤not possible that not p = necessary that p、同中間、⑥possible that p = possible that not p、同左側、⑦impossible that p = necessary that not p、線の下部⑧not impossible that pであり、⑧が⑤、⑥の全体を包含していて、⑦とは
反対対当となっている。ヒンティッカがpossible properと呼ぶものは⑥にあたり、かれはこれをアリストテレスの「偶然」と同義、あるいは深い繋がりがあり検討に値するものとしている。
ラカンはアリストテレスがときに「可能」と「偶然」を混同しているとしているが、少なくともPr.I.13.32a21-29でふたつの可能性をdynaton, endecomenonといった呼称を割り振っている。後者の語義は「貯蔵所」、「受け入れる場所」等であり、A. Beckerはこれを「偶然」と訳し、Ross, Lukasiewiczもこれを支持している。Soulez(Antonia Soulez, Science du sujet science du reel, Littoral, no. 30, pp. 117-136)および
Cathelineau(Pierre-Christophe Cathelineau, Lacan lecteur d’Aristote, Edition de l’Association Freudienne Internationale, p. 301)
が例証としているのは『命題論』第13章で述べられている、フランス語でいう2種の“peut”についてである。≪le feu peut chauffer≫「火はものを暖めることができる」と≪c’est la meme chose de dire qu’une chose peut etre coupee ou peut ne pas etre coupee≫「あるものが切られることも切られないことも同様に可能である」の違いである。前者が「必然」に属す「可能」であり、後者が偶然を示す「可能」であるとしている。Soulezの結論は、pV¬pで表される命題は真であると検証することができない事態を表すもので、一方これはラカンが「troisは“et ??? et”の側にある」とする定式に叶ったものといえる。
ところで、ラカンが「やってはいけないこと」といっているのは具体的になになのか。ヒンティッカにおいてとラカン自身においてと同じものなのか。
ラカンが常に注意を喚起するのは、想像的な奸計に騙し踊らせられることであるが、このことは、この年のセミネールのタイトルLes non-dupes errentとも関係している。Dupeとは想像的な審級に籠絡され、一義的意sensの解釈に捕われた分析家とも読める。ラカニアンたちはbonne dupe, mauvaise dupeと秤にかけるような物言いをする。しかし筆者が思うに、分析家という者は、否応無しに、まさにフランス語でbon gre mal gre etre dupeである瞬間を経験するはずである。先取りすることとなるが、この瞬間が「偶然」なのである。そうではない時間においてはetre non dupes errantなのであり、必然的エクリチュールに流れを任せているのである。errerとは「(船などが)推進力の力を借りないで惰性で航行する」といった語義の動詞である。
これ以上にしてはならないことは、解釈にあたって、ある意味を見いだすことに成功したと思い込み、自ら知を担った主体だとする矜持である。現実界たる無意識は純然たる穴であるのだから、そこに知があるとしても、それは穴の縁取りを飾る知であり、現実界そのものについての無知を粉飾する、いわば無知の知にすぎないのである。このことは後述することとなる。
ところでヒンティッカにおけるduperieとはどのようなものか。
Souez(ibid.)によると、ラカンの知(科学)が論理にあるとして、それはシニフィアンの論理である。ヒンティッカもフレーゲ、ラッセルのような、現実に対する言語の直接的指示referentといった考え方、つまりシーニュの論理とは袂を分かつ。論理の外延主義の図式、名称-関係といったシェーマに従う、単純な指示の透明性の神話ともいうべきものに基づいた論理、「一義的に示す」ことEindeutigkeitを退けた点でもヒンティッカはラカンに先んじていた。
Soulezに倣って続けると、ラカンがアリストテレスについて指摘している「存在の細分化」concassage le l’Etreはヒンティッカにも当てはまる。かれの様相的意味論とは多重指示の論理を可能性の様相といった形で示すものであり、アリストテレスの「存在」についての多様ながら曖昧な用法を利用している。
アリストテレスの「狭義の可能」ないし「未来偶然」は特に様相論理において課題となるとヒンティッカは言っている。一方で、アリストテレスの可能性の様相に倫理学がはっきりと読み取れるとしているはウカシェヴィッチであり、ヒンティッカに影響を与えた。そのウカシェヴィッチが三値論理を発明し、そのなかで偶然性の命題を扱っている。ラカンが無意識は発見されるものではなく発明されるものとしているのも、発明とはエクリチュールによってなされるものとするCathelineauの解釈に然うものである注7)が、特にエクリチュールの途上にある偶然が発明の瞬間と言えよう。
ヒンティッカがフッサール的志向性を準拠して可能世界論を論じる段になると、ラカンとの逕庭は決定的なものとなる。ラカンにおいてはetreの構造的欠如として示されものがここでは論理的行為として対象一般objectiviteへの関わりが概念的に捉えられ、これが多重世界へと構築され、これは結局、主体の表象化となってしまう。
11/06/1974のセミネールにおいてラカンはこう述べている。
??? 意味素、難しいものではありません。ララングにおいて意味sensを生み出すものはすべて、この言語langueのエク-シスタンスに結びついていることが明らかにされます。つまりそれは身体の生la vie du corpsに関わることの外で起こるのです???それはファロスの享楽、意味論的享楽jouissance semiotiqueが身体に別物として付け加わっていることから問題が起こります。
このパラグラフの後で、この問題について、それは「性的関係が書かれることがない」というテーゼであり、ファロスは意味論、可能世界といったもののオルガノンではないということが繰り返し述べられる。「性的享楽=ファロスの享楽は性的関係における行き止まりimpasseが明記されるものとしての特権性をもつものなの」(Encore, p.14)である。
Soulezとは異なりCathelineauは、アリストテレスの狭義の可能=偶然とは別にhasardについて言及している(ibid. p.313)。hasardはセミネールXI巻でラカンが問題としている、アリストテレスの『自然学』におけるtykeである。こう考えてよいであろう。アリストテレスにとってtykeは随伴的(付帯的)に生起したものであれ、意図されているものdianoiaつまり志向的intentionnelでなければならない。Cathelineauが指摘するように、この意図を川上、生起する事象を川下にみたてる(ibid.)と、『心理学草稿』では前者はabニューロン、後者はbcニューロンということになる。両ニューロン間での疎通をentelecheiaと読むかどうかなのであろう。いずれにせよ、ラカンにとっては、tukeも出会い損ないの出会いであり、少なくともラカンは、やってはいけないことを判っていてやっているのである。
意味le sensについては1974?75年のセミネールにおいて重要な主題として取りあげられることとなる注8)。la Troisemeで示されるボロメオの輪の平面化においては、意味とファロスの享楽は別々に図示されている。
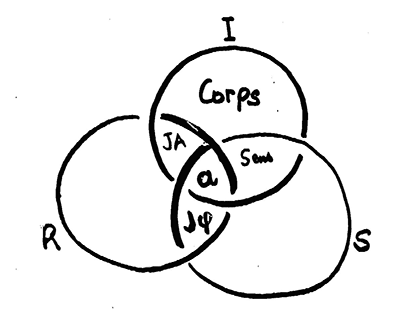
Les non-dupes errentにおいては、まだ意味とファロスの享楽との違いが判然としないのであるが、ここでのボロメオの輪においては、意味とファロスの享楽は相関関係にあり、ファロスの享楽は身体-外hors corpsに位置づけられ、性的関係を成り立たせるものなどではなく、その障害となるものであることがはっきりと示されている。
フロイトの『夢解釈の補遺』の第一部は「解釈の限界」Die Grenzen der Deutbarkeitと題されているが、遡って20/11/1973のセミネールにおいて、ラカンは、夢解釈の限界が示される瞬間は意味が到来する瞬間であるとする。そしてこの意味とは性的な意味である。しかし性的関係は存在しないことから関係が書かれないことになる。それは夢が途切れるときでもある。
??? 性的関係が書かれることがないという 定義を与えられるとするならば、暗号化chiffrageにおいて-暗号解読dechiffrageにおいてではなく-限界が必然的に設定されている-このフロイトの著作において使用されている限界Grenzenと同一の語が数学においても極限という意味で使用されています(20/11/1973)。
chiffrerとは暗号化することであるが、文字通りには数字を振ることであり、これはエクリチュールである。「精神分析が無意識の発見ではなく発明である」とするラカンの主張をもとにこの時代(1973-74年)ににおけるラカンの精神分析の定義が可能である。つまり、精神分析とは、性的関係の追求 ? これは根源的に無意識的なものであり、これをかりにjouissanceであると既定する ? に関する学である。エクリチュールを総動員させると結び目を生じさせる、結び目を取り巻く構造はそれゆえjouissanceの諸局面であり、意味sensは性的関係についての意味なのだが、例えばそれについての言direは行為であり、当然しくじり行為acte manqueとなる。ラカンはこのようなdireをacte manqueとしての成功したdiscoursと呼ぶ。ファロスの享楽は身体外hors corps、つまり戦力外を言い渡されたものとして、性的関係のゲームには参加できないものである。ゲームは負けるのであるが、その敗因がこの戦力外の事実に基づくものとされる。〈他者〉の享楽(この「の」deは目的的属格である)は不可能なものであり、それゆえこの穴は真の穴(この解釈についてはSinthomeまで待たなくてはならない)である。aは剰余享楽plus-de-jouir注9)と解される。あらゆるjouissanceの結果をもってしても、現実le reelはそこからex-sisteしてしまう。しばしば誤解の対象となる語がある。「失われた対象」 である。失われたからには再度見いだすことが可能なのではないかと。そうではない。そもそもそんな対象など存在しなかったのである。対象aは、これもエクリチュールによって、ラカンによって発明されたものである。
おわりに
最後に、エクリチュールをめぐる諸様相について纏めてみよう。性的関係を実現させようとエクリチュール、これが「必然」である。 既述したように、これは『心理学草稿』におけるoニューロンの疎通に相当する。反射弓のように短絡的に成り立つ現実との遭遇に対する延長、デリダに従えばdifferanceがこのエクリチュールに相当する。それは慣性法則に従うerreであり、ne cesse pas de s’ecrireである。「必然」は行為においてもその目論みが果たせることを期待して執拗にavec insistance神経連合のネットワークを拡げてゆく。可能とは対象との出会いが予告されたときであり、エクリチュールは成功したものと看做され(例えばラヴ・レターが功を奏してか、意中の人とのランデヴーが予告される)、成功したエクリチュールから行為へとの移行となる。つまりcesse de s’ecrireである。もし行為が成功したならば、これはveritable acteであり、これは幻想の終わり、defenestration、つまり自殺である。defenestrationとはfenetreという現実原則を突き破り、その結果、poinconは∧と∨へと割れ、この両者もろとも、つまり不可能ne cesse pas de ne pas s’ecrireという領域に主体は突入する。このとき落ちる主体は既に落ちる対象aとなっているのだ。これが唯一成功した行為であり、再度ne cesse pas de s’ecrireを賽の河原のごときに反復する必要はない。ほとんどの行為、機智とされる言direも現実には出会い損ないの出会いであり、失策である。そして多くの場合、等の本人はこのことに気づいていないのである。これを偶然と呼ぶ。再度必然に戻るわけであるからcesse de ne pas s’ecrireなのである。以上のことは精神分析のセアンスにおいても繰り返されているのである。この悪循環は性的関係がないことから起きてくるのであるが、その原因は女性の側のpas touteにある。であるからune a uneと何度でも繰り返すのである。モーツァルト/ダ・ポンテの『ドン・ジョヴァンニ』においてレポレロによって歌われるアリア『カタログの歌』(カタログとはまさにエクリチュールである)のなかの歌詞(???ma in Ispagna son gia) mille e tre 「(でもスペインでは既に)1003人も」(v. Lacan, seminaire “Encore”, Seuil, p.15)は性的無関係に終わる女性との情事の限りない繰り返しについての狂言回しの恨み言である。ドン・ジョヴァンニは新たな女性が現れるその都度、自らのファロスの享楽の可能性を諦めないのであり、それはかれの地獄落ちまで続くのである。以上のことは精神分析のセアンスにおいても繰り返されているのである。時としてアナリザンは出来事evenementに遭遇し、うまくこれを言うbien dire。しかしこれこそがフラプシュス、言い違い、機智、等々であり、失策行為なのである。アナリストはそこに解釈を介入させる。うまく解釈をしたならば、そこに意味が生ずる。そこにconsistanceをみることができたのでアナリスト殿はご満悦である。しかし解釈に込めた意味は性的関係が成り立たないことを意味する意味である。現実/無意識はそのときex-sisteしてしまう。
注1) ab-sensという新造語はab-sexeと対のものとしてL’Etourditで示される。「フロイトはl’ab-sensが性を示すことでわれわれを導いた。このab-sensの方向へと膨張させることでひとつのトポロジーが見せ場をつくるわけだが、語がそれに切れ目をいれるのである」(p.452), 「bipodeによる径庭による関係のl’ab-sens」(p.468)とある。
注2) 例えば「季節」、「方位」、「エーモンの息子」は三つの集合であるが、これらの集合の要素は基数4である。これらの要素同士1対1の対応が可能である。このときこの基数の質は4であるとされる。v.Patrick Dehornoy, Logique et theorie des ensembles, Notes de cours, FIMFA ENS, 2006-2007, chapitre 5 : Les cardinaux, in wikipedia
注3)dit-mansionは「言われたこと」ditの「住まい」mansionであるのだから、ハイデッガーのエコーを感じ取れる。象徴界とは必然的、ne cesse pas de s’ecrireであり、円環の絶えることのない運動であろう。言direによって意味sensが現出し、これは想像的なものである。ところが現実的なものにより結び目が形成され、意味は性的関係についての知に関して核心を突くこと能わず辺縁に押しやられる。中心には剰余ー享楽が残され、結局、言は失敗する。dit-mansionは言の効果であり、これがボロメオの輪であり、本稿そのものの縮約であるとも言える。
注4)カントによれば、この不可入性は感覚に属する、すなわち経験的直観に基づくとされている。ラカンがcross-capで示している相互貫通線ligne d'interpenetrationはこのような古典的物質観では捉えることができないものだが、トポロジーでははめ込みimmersionとして示され、いわゆるトンネル効果、リーク電流といった現象は、このようなトポロジー的発想により説明しうるものであろう。
注5)ラカンは自分をバロック的だと言っている。バロックはいち美術様式であり、美術史とはla mancheの歴史だと言っている。 la mancheとは袖のことであり、日本語でも「袖の下」といった表現にもあるように、なにかを隠す、あるいはくすねる、ごまかすためにも用いられる。la mancheはtour de passe-passe「手品」と関係し、ラカンは自己諧謔的に香具師だと言っているようなものだ。ただしla mancheはle mancheとは語源が異なるものの同音であり、女性性器を意味する語義はないが、ラカンにとっては自己諧謔的にconと同義なのであろう。因にバロック的とはケプラーによる惑星の楕円軌道(バロック様式の建築の平間も同様楕円形である)に見られる中心の欠如、ふたつの焦点の離心性であり、エピステモロジー上はコペルニクス以上のパラダイム変化だとされている。
注4)例えば三段論法(古典ギリシャ語syllogismosは「計算」「推論」「演繹の結果」の意)は一見ボロメオの輪を予感させるもののように見えるが、既に述べたように、ラカンからすれば、アリストテレスは現実界を曲解して三つは二組ずつそれぞれセットで揃っているもので、三つは同一中心をもったconcentriqueものと看做せるとしている(1974/2/12)。
注5)しかしながら、The laws of thoughtにこのような痕跡は窺えない。
注6) Pierre-Christophe Cathelineau http://www.freud-lacan.com/Champs_specialises/Theorie_psychanalytique/Logique_modale)
注7)Pierre-Christophe Cathelineau, http://www.freud-lacan.com/Champs_specialises/Theorie_psychanalytique/Logique_modale)
注8)ラカンにおいて、象徴的なものが優位な時代においては「意味」の創出は、たとえそれが想像的な籠絡が関与しているとしても、メタフォリックな、つまり言語的、象徴的機能にもとづくものとされていた。RSIでは、現実的なものとこかかわりで(もちろん「現実的なものは意味から追い出され???それは意味のヴァージョンなのだが、意味の嫌悪、反-意味、前-意味、というヴァージョンでであり、御ことばの頑な拒絶である???」〔11/03/1975〕といったかかわりであるが)捉えられ、さらに指名nominationとのかかわりで論じられることとなるが、これについては別稿を要することとなろう。
注9)plus-de-jouirという語をフロイトの表現に求めるならば、Lustgewinnという語がこれに相当するとラカンは言っている(20/11/1973)。同日のセミネールでラカンが言及しているTraumdeutungへの補遺の第一部“Die Grenzen der Dartbarkeit”に次のような記述がみられる。
Die Frage, ob man von jedem Produkt des Traumlebens eine vollstandige und gesicherte Ubersetzung in die Ausdrucksweise des Wachlebens (Deutung) geben kann, soll nichit abstrakt dehandelt werden, sondern unter Beziehung auf Verhaltnisse, unter denen man an der Traumdeutung arbeitet.
Unsere geistigen Tatigkeiten streben entweder ein nutzliches Ziel an oder unmittlbaren Lustgewinn ??? (Gesammelte Werke 1, pp.559- )
夢の体験から得られたものすべてを覚醒時のことばに置き換えて完全無欠の翻訳を得ることができるかどうかといった疑問に対して抽象的な問答で済ますのはもっての他です。(審級間での)力関係のなかで、ひとは夢の意味Traumdeutung(前述したように、ラカンは、Deutungとはsensのことだと言っている)に携わる。
われわれの精神の営為は営利的目的に向かうか直接的なLustの獲得(これをラカンはplus-de-jouirと訳す)に向かうかどっちかである。



