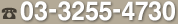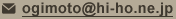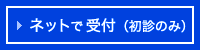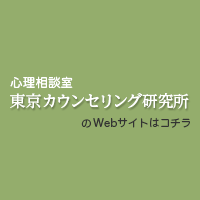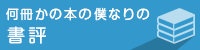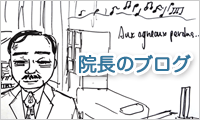|
ジャック・ラカン
 |
イリーナ・アモセノク(注1)との対談
Ирина Амосeнок (イリーナ・アモセノク): I) Y) こんにちはイリーナ Y) あなたは荻本医院で、カウンセリングだけでなく本格的な精神分析も実施していますが、前回の荻本医院の勉強会で発表していただいたケース報告(この報告全体は、あなたもそう理ってのことですが、守秘義務があるのでクローズドでの発表にとどめてHPには公開できないと)で、このケースだけでなく、アンドレ・グリーンの「死んだ母親」la mere morteが深く関わっているアナリザン(ト)なりクライアントは何人かいることを知り、僕の方でも付け焼き刃的にAndre Green, ≪Narcissisme de vie, narcissisme de mort(生のナルシシズム、死のナルシシズム)≫の“La mere morte”を読みました。びっくりしたのは、アンドレ・グリーンがニコラ・アブラアムとマリア・トロックも援用していて、crypte注2)について述べているし… I) ニコラ・アブラアム、マリア・トロックについてはロシアではまだ紹介もされていませんので、よく判りませんが、フェレンツィは少し、そしてロシアでは母子関係についての精神分析が幅を利かせていますので、当然ながら、メラニー・クライン、ウィニコットはそこそこ読んでいます。各都市によって事情は異なりますが、わたしが学んできたサンクト・ペテルブルグでは、フロイトは古典的理論として、しかし臨床面ではクライン派、ウィニコット派そしてラカン派といった学派があるといっていいでしょうが、フランスのように徒党を組んで、という感じではなく、それぞれのшкола間での論争が激しいわけではなく、集団でというより、個人と個人との関係が重きをなしていて、わたしもペテルブルグでは5年間は週二回いわゆる教育分析をある先生のもとで受けてきましたし、その後も週一回のセッションが続いていました。なぜ教育分析を受けてきたかというと、自己分析などわたしには不可能に映っていましたから。その先生との信頼関係がまずあり、助けてもらう、という意識が強かったのです。権威主義的パーソナリティという言葉がありますが、ロシアではある人に対して権威を、ちょうど父権みたいなレッテルを貼り付け、それに服従する、という図式はあまりありません。ですから現代ロシアの有名な精神分析家は誰かなどと訊かれても、wikipediaで出てくる分析家がロシア国内でそれほど名を馳せているわけではないですし、そもそもロシア国外のwikipediaに書かれている精神分析家がロシアではどうかというと、ロシア語のвикипедиаに出てくる名前とかなり違うでしょう。わたしがアンドレ・グリーンを読み始めたのは、かれの臨床家としての力量を認めてですし、特に最近は、これは米国でもボーダーラインが問題となり始めた頃からそうなんでしょうが、アナリザン(ト)が寝椅子で分析家は枕元、というフロイト、そしてラカン派もそうなんでしょうが、このやり方はアナリザン(ト)に強い不安を与え、これが極まるとパニック・アッタックを起こす人も多いわけで、だからわたしは常に対面でアナリザン(ト)と話し合うというスタイルしかとりません。アンドレ・グリーンも同じようにしていました。 Y) 僕はラカンをずっと勉強してきましたし、フロイトを読むに際しても、ラカンを通じてフロイトを読む癖がついてしまいました。ラカンについてはロシアではどのような状況なのでしょうか。また過去の人なんでしょうが、例えばザビーナ・シュピールラインについてはどうなんでしょう。 
I) ラカンのセミネールの翻訳はだいたい日本と同じぐらいの進捗状況でしょう。ただ繰り返しになりますが、ロシアでは母子関係が強力すぎて父親というと影が薄い存在である家庭が多く、臨床面ではクラインやウィニコットの方に軍配が上がるといっていいでしょう。フロイトは古典、そしてラカンは現代を代表する精神分析の理論家という捉え方をわたしはしています。ザビーナ・シュピールラインは、やはり映画注3)の影響でしょうか、一般的にはスキャンダラスなとり上げ方をされることが多いです。やはりルー・アンドレアス・ザロメ(ロシア語ではサロメと発音します)の方が影響力としては格段に上でしょうが、それも臨床家としてというよりその当時の知識人という意味ででしょうかね。精神分析関連の著作というと、≪Эротика≫,≪Анальное и сексуальоз≫,≪Вклады в психоанализ≫,≪Нарциссизм как двойное направление≫それぞれ日本語にすると最初のは『エロティカ』でいいかな、二番目のはイマーゴ誌に投稿された論文でオリジナル・タイトルは≪“anal” und “sexial”≫でどのように訳せばいいのでしょう、形容詞→実詞は言語によって違いますから…『精神分析への貢献』、『ふたつの方向性をもつものとしてのナルシシスム』と四つのタイトルのすべて、ドイツ語からの露訳で、絶版になることもないのですから、かなりの読者層に支持されているのではないでしょうか。 Y) ここにお持ちしたのは、ネット上に公開された、早稲田大学の貝澤 哉さんという方が書いた論文(精神分析によるロシア文化の新たな読解 -I・スミルノフ、A・エトキントを中心に - 〔http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/kaizawa.html〕)のコピーです。ロシアの主に文学批評と関連のある文献についての紹介なのですが、もちろんマルクス主義のバックボーンがあっての伝統も相俟ってなんでしょうが、他国では例をみない独特な研究があるんですね。こちらは『これは、やはりネット上に公開されているABC religion and ethicsというサイトにRichard Kearneyという人が投稿した記事(Working Through Trauma: Narrative Catharsis in Joyce, Homer and Shakespeare〔https://www.abc.net.au/religion/working-through-trauma-narrative-catharsis-in-joyce-homer-and-sh/10094622〕)のコピーです。英語ですがスラスラ読めます。解釈学の系譜に連なる人なんでしょうが、リクールなんかよりもずっと平易な文章です。精神分析にもかなりコミットしています。幸か不幸かロシアにはamazonが進出していませんよね。星の数は信用なりません。いわゆる「さくら」、英語だとpufferによる高得点がありますから。amazon co uk.でRichard Kearneyを検索すると、かなりのタイトルが出てきます。Strangers, Gods and Monsters : Interpreting Othernessというのをオーダーしました。Anatheism(ana-という接頭辞はいくつかの意味を伴うものですが、この場合、returning and after≪the death of≫ Godの語義となります。returningといっても解釈学的な意味であって、信仰の実践ではない)という立場を取っているようですが、そのまま≪Anatheism≫というタイトルの本の星の数は4つですが、多くの5つのなかに一人だけ2つをつけて長々と書評注4)を買いている人(この人自身wikipediaにも出ているほどの人です)がいてこのコメントはかなり参考になりましたし、こちらは注文するのをやめました。そしてこのere社のTrasitionというシリーズの雑誌でLa psychanalyse avec Nicolas Abraham et Maria Torok(ニコラ・アブラアムとマリア・トロックの下[もと]での精神分析)というタイトルが特集となっていますですが、Claude Nachinという精神科医/精神分析家が書いたUnite duelle, cryptes et fantome(クリプトと幽霊といった対)です。カーネイ、ナシャンに共通しているのは、リクールもそうですが、narration, narratif, recitつま「物語り」的な側面です。グリーンも『死んだ母親』のなかで、自由連想ではなく現象についてnaratif (theoriqueではなく)な捉え方が必要で、これがmetaphorique(ラカンのmetaphoreとはまったく違い、どちらかというと、ラカン的にはmetonymiqueです)、例えば、母親の乳房からの分離についても、かの女の身体の香り、眼差し、その他諸々で、実際グリーンはメトニミークな対象がメタフォリークになるのだと説明していますよね。ついでにこれは余計でしょうか、『精神分析の裏側』≪L’envers de la psychanalyse≫のロシア語版(Изнанка психоанализа)も持ってきました。まだ邦訳は出ていません。なぜなのか? … ロシア語でこのセミネールについて書評等、書かれたものがありましたら調べて教えてください。このセミネールについてはのちの勉強会で取り上げるかもしれませんが、今日は件のアナリザントanalysanteとアナリスト(イリーナ)とのやり取り、そこに符合するグリーンの諸概念について話し合いましょう。 I) かいつまんでもう一度このアナリザントの置かれた状況について要約します。かの女は三十代後半、ロシア人女性で高等教育を受け、社会的には成功を手にした人間といえます。単身で来日し、就労ビザを取得し、某外資系の金融機関で働いています。未婚で、結婚の意思は持っているのですが、それができません。このことは後で述べます。両親は存命中でモスクワ在住ですが、母親は病弱で常に医師による治療が必要です。父親はかの女の療養に非協力的であるばかりでなく、母親の病気は娘であるアナリザント(この両親に仕送りまでしているのですが)のせいだとかの女を罵倒します。つまり自分の妻は娘であるお前からの影響で神経を病んでしまっているのだというのです。アナリザントは自責的になり、自分が他者に不幸をもたらす人間だと信ずるほどになってしまいました。分析のセッションは続いていますが、かの女はこの治療に対しても懐疑的で、自分に対して「難しい症例」だとも言い、もう続けてゆくことはできない、と言いながらも、一方で、分析家であるわたしに、セッションを続けてゆくように説得してくれないのか、とアンビヴァレントな要求をすることもあります。直近の里帰りの折には、実家(母親はモスクワ郊外にある祖母の家で療養しており、アナリザントは父親に言われるまま、二ヶ月ほど母親の世話をした後で戻ってきたのです)であるアパルトマンから暇乞いしようとしたところ、玄関先で父親から「お前とは、もう会うこともなかろう」とまで言われたと。そして、分析をすることで、セッションで話している父親への怒りを 当の父親に見透かされてしまったに違いない、と分析に対して、分析家に対しても矛先を向けてきましたが、その言葉を呑み込むようにして、結局なにもかにも性悪女である自分が悪いのだし、このようなどう仕様もないケースの分析は意味がないだろうし、これが延々と繰り返されるのだったらゾンビみたいだと言いのけています。 Y) あなたの対応は? I) グリーンの症例の多くは、いわゆる境界パーソナリティ、自己愛パーソナリティ、いわゆる心身症的傾向のあるもので古典的な神経症のケースはむしろ稀で、繰り返しますが、分析もフロイトのやり方では駄目で、修正が必要だとしています。マリー・カルディナル注5)みたいにはいきません。寝椅子は用いず、対面でセッションを行い、ほとんどの時間が「会話」です。そのなかで分析家は即座に積極的に介入し、解釈を加えます。でも一方的な解釈だとアナリザン(ト)に思われないように、繰り返し、アナリザン(ト)に対しては、安心感を与え続けるための態度表明みたいなものを示していくことが重要です。かの女と父親との関係について重要な介入として「貴女がそう嘆くのは、貴女が貴女のお父さんを愛しているからでしょうし、そこには『理想化』というものが働いているからでしょう」と返しました。 Y) そういえば、このアナリザントはあなたのことをИринаイリーナの愛称Ираイーラと呼んでいますよね。一緒にお茶を飲みながらとか、友達として付き合いたい等々ボーダーライン・パーソナリティによくある誘いの言葉には直ちには応えないで、これを冗談と受け流しながらも、この冗談を「はなしの核心に近づくとそれを有耶無耶にするためのアナリザント特有なもの」と突いています。それでいてアミカルに話し合っていますよね。このアナリストとアナリザントとの関係はフェレンツィの場合に近いのかな? I) フェレンツィほど親から受けてきた虐待を赤裸々に告白し合うなんてことはしませんけど、プライベートなわたしの生活についてもときどきは話します。 Y) 引き続き、このケースのセッションについて説明してください。 I) かの女の母親はかの女を産んだ後で「うつ病」に罹患した、と聞いていますが、これも父親の言葉を重ねている可能性があります。かの女もある男性とのあいだの子を身籠ったことがありますが死産となり、ここでも「喪」の仕事を繰り返すこととなりますがこの二つ、母親のうつ病、アナリザントの死産は対となっていてそれぞれに連想が及んでいます。ところが母親の看病についてはなしに及ぶとその都度、父親に対する怒りが男性一般に対する怒り、不信の言葉となって現れ、分析家(=わたし)も男性的なものに属するものとして糾弾の対象として扱われ、さらにそこに抵抗が働き、わたし(分析家)とは友だちとしての関係であればいい、性(差)に対しての混乱が窺えることばとして「この忌々しい分析」、アナリストの側から、「それではこの治療は中断した方がいいのか」、という問いに対しては(アナリスト=わたしに対して)「フロイト先生、あなたと別れるですって」と分析を終えることへの恐れを諧謔を装って退けます。ここに分析への、そして分析を終えることへの抵抗の手段として、「知性化」、「合理化」、「道徳化」の典型をみることができます。 
Y) あなたは、その際、分析に対してのアナリザントの態度をбросала несовершенных мужчин「不完全な男を投げ捨てた」ものと表現していますが、このнесовершенныеという形容詞は興味深いですね。フランス語では「欠点のある」defectueuxの意味がありますが、ずばりimparfaitがぴったりです。imparfaitも「不完全な」「欠陥のある」の語意はありますが「終わってはいない」であり、実詞化されたものが動詞の時制である「半過去」です。ロシア語もнесовершенныхが不完了体でしょう。フランス語のl’imparfaitにはいろいろな用法がありますが、「(…)仕損なった」ことに対する無念の感情が言い表されている場合があります。例えば、Une minute plus tot, tu la voyais. (あと1分早くきていれば、君は彼女に会えていたのに)、更には、これはエクリの『フロイトの無意識における主体の逆転と欲望の弁証法Subversion du sujet et dialectique du desir dans l’inconscient freudien』に出てくるフロイトの『精神現象の二原則に関する定式』の仏語訳Il ne savait pas qu’il etait mort(かれ=父親はすでに死んでいるのにそのことを知らない)です。 I) かの女の分析のきっかけは「結婚願望がありながらこの願望が実現しない」ことでした。わたしとかの女とのあいだでは、この「願望を実現させることができない」ことがかの女の規則правилоに基づいていることでコンセンサスが成り立っていました。この願望が自分を苦しめる。であれば、願望を抱くことをしないように強い意志をもつことが可能なのか、とわたしに質問することもありました。わたしは、まず、願望充足がないということは、禁止が働いているのであり、誰が禁止しているのか、という問いを立ててきました。禁止する者の声が心のなかにあるのか(いわゆる幻聴と呼ばれる現象はかの女には存在しません)、それは善者の声なのか、神の声なのか、と言った問いも立てました。かの女は誰の声なのかは最初は明かしませんでいたが、自分にとって悪を招かない者の声であれば善者の声であるし、わたし(分析家)にもその声を発する者になってくれまいかと訊き返したりもしました。かの女には実生活上好意を抱いている男性がいました。かれには妻子がいて、かの女もかれとの性的関係は望まないよう心掛けていました。というより、結婚できない相手であるから接することができた訳です。母親について語り始めたのはこのようなやり取りが交わされた直後でした。
Y) フランス語にUn lendemains qui chanteという表現があります。「明るい未来」という意味です。Paul Vaillant-Couturierという詩人がArthur Honeggerに贈った≪Jeunesse青春≫というタイトルのリリックスの最後の行に出てくるのですが、今日ではフランス人なら普通に使う表現です。揶揄的には権威主義的共産主義者、反 - 権威主義、血なまぐさい革命か無血革命かを論じる御仁、一時期インターナショナルの歌としてシュプレヒコールに使われていたようです。相手のスローガンに対しておちょくりで反射的に出てくる言葉です。ところでロシア語петь(歌う), пение(歌うこと)の語源は?、これ等の語を使った表現は? I) あなただったら、どうせ揶揄的な表現でしょう(笑)。連想としてぱっと思いつくのは賛美歌(古いというイメージかな)、(声が)高い、つまりうるさいという意味、退屈なビジネス(これも賛美歌からのアナロジー的な用法なのかな、長くて退屈という意味でしょう)注6)。 Y) エチモロジーでしたら、Max Vasmerという人が著した≪Russisches Etymologisches Worterbuch≫全3巻を≪The Origin of the Indo-Iranians≫をamazon.co.ukでオーダーし、もうすぐ届きます。両方ともロシア語を意識しての注文です。amazon.co.ukで買うとなんでも安い!しかし大散財でした。すいません、また脱線しかかっています。グリーンに戻りましょう。 Greenの≪La mere morte≫に即して、述べられているテーマごとに順を追ってイレーナのこのケースにおいてどのように符合しているか確認していきましょう。まず対象喪失についてですね。 I) 前回の発表の最初にも述べましたが、わたしのこのケースと同様、グリーンは「死んだ母親」といったタイトルに相反して、母親は存命中であり、愛する(愛すべきといった方がいいのでしょうか)対象(全体対象という概念はおかしい、対象は部分対象でしかないという批判も持ち上がるでしょうし、ラカンの対象aと比べられると…) Y) Andre GreenもL’objet (a) de J. Lacan, sa logique, et la theorie freudienne というタイトルで発表しています。まだ未読ですが。アンチ・ラカニアンであるグリーンにとって徹底しているのは情動affectをめぐるラカン批判で、行き着くところ、ラカンのシニフィアン理論をかれはまったく認めていません。これについては表象代表と訳されているVorstellungsreprasentanzを巡る考察として、今いろいろ読みながら書く作業を始めました。 I) 去勢不安についてもラカンは独特ですよね。 Y) 去勢威嚇menace de castrationという言い方はおかしい。現に「ハンス少年」にとってこのような不安はなかったのだとセミネール第IV巻『対象関係』で既に述べられ、第X巻『不安』では不安は『制止、症状、不安』でのフロイトの不安信号説に与しているようにも映りますが、一方フロイトのこの本では、不安について以外のことは見事に論じられているとかれ一流の批判のことばも出てきます。信号だとしてなんの危険を予告する信号かというとジュイッサンスの危険をです。欲望はここに至って防衛の一種と定義されます(もちろん欲望は防衛以上のものではありますが)。 I) グリーンもフロイトについてはまず『制止、症状、不安』からいろいろなタイプの不安を列挙していますがその委細には触れていません。グリーンは自身の名前が(英語で)色の名なのですが、「赤い」不安(去勢により身体の一部が切り落とされる場合)、一方で、去勢の場合でも、それがどれほど破壊的なものであれ、血なまぐさいものでなければこれは「喪」の色である黒と白であり、重篤な「うつ」は黒、空虚の諸状態は白だとしています。わたしもグリーンのこの空虚 - 白について、よく理解できないところがあります。対象喪失(ラカンの対象aとこれに対するグリーンの批判については別の機会にあなたに任せるとして)そのものが喪の仕事の契機となるはずです。死別だけではないはずです。この「死んだ母親」の論文はボリュームとして、原文では何ページあるのですか。 Y) Narcissisme de vie, narcissisme de mortのp.247-283ですから34ページだけです。 I) 短すぎます。もう少し説明的でないと。 Y) 僕もそう思います。 I) はしおって図式的にいうと、フロイトまで戻るとして、喪の仕事が正常に行われない場合、喪失した対象に主体が同一化してしまう場合ですが、これがメランコリーということになりますが、同一化にもいろいろあるわけで、フロイトが深く立ち入らなかった「体内化」、英語でもフランス語でもincorporationですね。 Y) その通りですが、なぜ深く立ち入らなかったかについて、マリア・トロックがrevue francaise de la psychanalyseに投稿していて、これがL’ecorce et le noyauに載っています。後ほど説明します。 I) 喪の仕事が行われない場合、というより、行われるべき喪の仕事ができていない、これが「白い喪」ですよね。連想として浮かぶのが、このフランス語の表現はわたしも知っていますが、mariage blanc「性的交渉のない結婚」ですね。タイトル名「死んだ母親」とは相容れないのですが、「母親は生き続けていることになる」。他のケースで現実に母親と死別した「死んだ母親」が当てはまる女性もいます。ところでいわゆる経済論的観点からすると、対象に備給されていたリビドーは撤収されるわけですが、これが二次的ナルシシズムを招くわけですよね。そしてここで、あなたの持っている本のタイトルNarcissisme de vie, narcissisme de mortにも繋がるのでしょうが、一方で、対象喪失を巡って、メラニー・クラインにおけるうつ的体制への移行はそれに先行する母子間の(この「死んだ母親」のケースに見られるような)混乱がもとで阻まれるとのみ書かれているだけです。グリーンはラカンとは違って「不安」という語をかなり広い意味に用いています。そして先ほどの色分けがまた登場します。「身体の一部が切り離される」、これはまさに血に染まった色「赤」の不安に相当し(グリーンはなによりも優れた臨床家でしたので、いわゆる「虐待」、「外傷」を体験したケースも多く診ていてのことでしょうが)、離乳、超自我による保護からの切り離し、これは「白」(空虚)であり、うつ病エピソード(うつ的体制とは別のものです)が「黒」に相当します。グリーンはこの白、空虚、ネガティフという系列を重視しています。 いわゆる自我心理学がモットーとする「自我を強化する」ことに関して、他のあらゆる学派は批判的ですよね。わたしはKohutを読んだことがないのですが、かれはSelfという語を用い、Egoに関して問題をはぐらかしていたのではないのでしょうが、ナルシシスムにもポジティフな面、ネガティフな面を認めるか認めないか、必要悪すら認めないのか、いろいろ意見の分かれるところでしょうが、自我というものはあくまで脆弱であり、フロイト理論におけるナルシシスム(もちろん「ナルシシスム入門」とそれ以降でも違うのでしょうが)と自我備給との関係について、フロイト理論に批判的な人や学派においても、なによりもまず、かれの経済論的観点を批判しているものを見かけたことがないのですが。 Y) 局所論的に捉えられる1920年以降の「自我」と『心理学草稿』での「自我」(単なる側面備給です。快感原則にエネルギーの放出が最終目的だとして、さし当りそれを保管しておく倉庫のようなものを連想すればよいでしょう)を経済論的観点から整合性をもたせるような試みはラカンの天才的屁理屈を持ってしても成功しなかったのです。『自我とエス』や『続精神分析入門』のシェーマをなんとかトポロジー的に表現しようとしていたラカンも「あの出来損ないの卵」にはお手上げだったのでしょう。また、フロイトにおいてはせいぜい「自我の分裂」という表現には辿り着きましたが、真剣に取り組んでこなかった「体内化」、その結果体内化されたもの、そしてcrypteは自我の中心に形成されるわけですから。この「死んだ母親」論には情動(欲動そのものは情動量です、ラプランシュとポンタリスの辞典でも常にアクセントが置かれているのは代表です、欲動代表=表象代表で欲動そのもの、情動量の記述に関してあまり重要視していないのは、ラカンの影響力が働いていたのかもしれません)についてのラカンの軽視に関わる批判は窺うことはできません。Gerard Pirlot, Dominique Cupa共著のAndre Green - Les grands concepts psychanalytiquesという本のまず最初に出てくるのが情動で、ここにラカン批判が要領よく纏められているようなので、これを読みましょう。 I) 幻想についてはラカンと同様(フロイトの「子どもが打たれる」を敷衍としたものです)、基本的、そして主体が不在である朧げな第二の幻想を重視しており、これは原光景における母親(これも幼児におけるの朧げな、性差というものを知らない時期の父親と結びついた母親、ですからペニスを持った母親となります)が問題となっています。離乳についての不安も母親の乳房から引き離されるとしても、これはあなたが述べたようなメタファーであり、母親の身体の香り、皮膚の感触、眼差しの複合とされ、そこから引き離される不安が問題となっているのです。超自我と自我理想は多くの場合対立するものでなく、エディプスコンプレックスもこの母親(死んだ母親)に付随しており、なんども強調される、白い、空虚なと形容される母親で、しかし、この死んだ母親が明らかになるのも、分析治療における転移を経てであり、グリーンは繰り返し、古典的な寝椅子による自由連想ではなく、分析家は快活に対話をし、静止したニュートラルな姿勢は避けるべきとしています。本ケースでは当てはまらないでしょうが、なかにはエディプスの母親(これもフロイトのエディプスコンプレックス批判、フロイト以後の分析家による批判としてよく話題になる、淫乱な女=ジョカステは誤りであり、かの女はエディプスとの性的交わりの事実を知るに及んで自殺しています)よりも淫乱=スフィンクスといった図式のケースもあると。これは男性の症例に多いのでしょうか。わたしはこのようなケースに関わった経験はありません。というより、あるいはケースによっては符号するものもあるのかもしれませんが、どうも男性はシャイで、このようなことを口に出すのに抵抗があります。 歌と東関東大震災の話でアナリザントが口を閉ざし、長い沈黙が続きました。その際私の方からなにか別の話題でもいいから声をかけるべきだったのでは、と後悔していました。その後、やや日にちをおいて再度かの女から電話でセッションを再開したいとの要望がありました。話題はやはり母親の禁止に背いたことから始まるのを期待していたのですが、つまり、万能であるのは母親なんだということばが欲しかったのですが。後戻りする感じで、禁止のオンパレードで、これは神経症的な防衛機制に属すものです。フロイトが「フェティシスム」で述べているような自我の分裂は覆い隠されてしまっていると行ったところです。セッションは続いていますが、泣きながら(実際、かの女はよく泣きますが、ほとんどが悔し涙です)、それは自分が不幸だから、と母親についてはまったく語らなくなりました。 Y) まず僕がこのケースから思いつくのは超自我(フロイトの超自我ではなく、メラニー・クラインのです)、グリーンの『死んだ母親』には、あなたの説明の通り、超自我と自我理想とのあいだには区別がありません。ラカンの超自我については、ジュイッサンスとの関連で書き始めたものがあります。セミネールでいうと第X巻「不安」のセミネール→第XX巻「アンコール」という図式です。ラカンは超自我という言葉はあまり使わないので、この図式は確かなものです。jouissanceは日本語では「享楽」と定訳がありますが、僕はこれはおかしいと思うのです。plaisir「快感」と違って、ジュイッサンスは「楽」とはかけ離れたもので、人間にとってはまったく反対に、無間地獄がもたらす苦痛でしかありません。ですから僕は書きものをするときはカタカナでそのままジュイッサンスと書きます。まず1962年12月19日のセミネールですが、ここには「超自我」という語は出てきません。その代わり「神」です I) グリーンのロシア語役にもジュイッサンス(ロシア語でнаслажде?ние)という語はみかけますが、ラカンのジュイッサンスとは違いますね。単純に(性的)享楽でいいと思います。「死んだ母親」を抱えたケースにおいてはこのジュイッサンスを得ることがままならない、とは書かれていますが。ラカンの場合だと、禁止は二次的に働くことになるわけですね。では、そもそもラカンの超自我の由来は?やはり原父なんでしょうか。ですとここでもincarnationの問題となってきますよね。 Y) ラカンは1961-62にIdentification(同一化)というタイトルでセミネールを行なっています。ミレール版はまだ出ていません。Association Freudienne Internationaleというグループ(現在はAssociation Lacanienne Internationaleと改名されています)が「商業目的でなく」として、良質の版を発行していますので、ミレールも刊行しづらいのでしょう。そこでは三つのタイプの同一化について述べられていますが、ほぼフロイトの『集団心理学と自我の分析』(単行本として上梓)の第7章以降の記述に忠実です。ラカンを読むより、フロイトを読んだ方がスッキリと理解できます。『トーテムとタブー』についても理解が深まります。ラカンは晩年のセミネールL’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourreでもこれら三つの同一化について繰り返し述べています。トポロジーを別として、こちらの方がコンパクトな説明で僕には理解しやすいです。三つの同一化の第一のものがエディプスの同一化で、『トーテムとタブー』では原父を殺害し兄弟たちがカンニバリスムを行い文字通り体内化するのですが、フロイトもラカンもincorporationについては十分な解釈を怠ってきました。先ほど言いかけましたが、ニコラ・アブラアムとマリア・トロックの共著L’ecorce et le noyauには、マリア・トロックがla Revue Francaise de Psychanalyseに投稿した論文が載っていて、「喪の病と妙なる屍体の幻想」というタイトルです。フロイトとカール・アブラハム間での当時未公開の書簡について書かれており、フロイトがアブラハムに「取り込み」Introjektion, introjectionと「体内化」Einverleibung, incorporationとの違いを説明しておきながら(おそらくこれとてフェレンツィからの受け売りだったのでしょう)アブラハムがフロイト宛に「確かにあなたが仰るように、わたしのケースでもこの違いは説得力があります」といったような内容の手紙を書いたにもかかわらず、フロイトは「わたしはそんなことを言った覚えはない」とけんもほろろでして、恐らくは、当時からフロイトとフェレンツィとのあいだの確執があり、これが決定的となった時期と一致していたのではないでしょうか。L’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourreの1977年1月11日のセミネールでは先ほど触れたニコラ・アブラアムとマリア?トロック共著でデリダが巻頭言を書いているVerbier de l’homme aux loupsについて、特にデリダがコミットしているのでかなり意識している様子が伝わってきますが、同セアンスでは、自分は第一の局所論のフロイトしか認めない、自我-超自我-エスのシェーマはグロデックのシェーマト大差のないお粗末なものだ、と言い訳がましく述べています。 I) ニコラ・アブラアムとマリア?トロックは読んでみたいですね。特にVerbier de l’homme aux loupsは、セルゲイ・パンキィーエフがロシア人でしたので、フロイトだけでなく、かれに関するいくつかの文献に目を通してはいますが、crypte, fantome等理解する上でも…それにあなたが読み始めたグリーンのHamlet et Hamletも興味あります。シャークスピアのファミリー・ロマンにも言及しているのでしょう。ソ連時代からですが、ロシアはシェークスピアについて独自の解釈の伝統があります。映画ではГрегорий Козинцев監督のГамлетはローレンス・オリヴィエのものと肩を並べるものに仕上がっているものと思います。 Y) 僕はКозинцевがナンバーワンだと思っています。音楽もショスタコーヴィチですからね。それから今までグリーンを読んでこなかったのには曰くがありまして、これは雑考として書こうと思っています。Verbier de l’homme aux loupsはフランス語として、それほど難しくはありませんが、ロシア語の知識が要求されます。英語訳を、これまたamazon co uk.にオーダーしています。間も無く届くものと思っています。これはイリーナにプレゼントします。 I) ありがとう。頑張って読んでみます。ロシア語に関しては、お役に立てるかも。 Y) ケース報告については、まだセッションが続いているようなので、そのうち第2弾をお願いすることになるでしょう。 今日はどうもありがとう。勉強会の方も引き続きよろしく。 注1) この日本語表記は正確ではないが、かの女のパスポートのラテン文字表記に準じた。 注2) ニコラ・アブラアムとマリア・トロックによる語。どこの家にも表に出せない秘密がある。フロイトとの絡みでいうとファミリー・ロマンに結びつくが、子どもは親から、親自身については直接、生まれる前に逝去した祖先の話については、「誰々はかような偉業を成した。お前は由緒ある家系の系譜に連なるものだ」、などと聞かされるものだが、どっこい、子どもは醒めた目で「でも言えない秘密もあるだろうし、だから僕/わたしもそのことについては訊かないし誰にも言わない」となるものである。クリプトとは教会の地下の意であり、この「家族の秘密」と「幽霊」fantomeは対概念である。かなり昔のこととなるが、現代思想社のデリダの特集、「デリダ読本」において、cryptonymie, Le verbier de l’homme aux loupsのデリダが書いた巻頭言のみが訳され載っていた。そこでは本書は「狼男の言語標本」といったタイトルに訳されていたが、herbier-verbierという連想が働いたのであろう(因みに、荻本はJean Allouchと東京で二度ほど食事を共にし、その後もメールのやり取りが続いていた。かれは頻りに小生に小川洋子の「薬指の標本」について質問してきた。標本はフランス語ではnaturalisationとなる。薬指はフランス語では単にl’annulaireであり、小川のフランス語訳タイトルもこのL’annulaireとなっている。これが結実したものとなったのがContre l'eternite : Ogawa, Mallarme, Lacan〈2009〉であり、これについては、いずれ「Allouchについての思い出」として認めることにする。これも「喪の仕事」が関係してくるし、ファルマコンについて、毒について話は及ぶことになる)。いずれにしてもLe verbier de l’homme aux loupsを理解するためにはロシア語の知識が必要である。L’ecorce et le noyau「表皮と核」(こちらは比較的易しく読める)によって、crypteとfantomeへの理解は深まるであろう。誰でも、多かれ少なかれ、ものを言わぬ死者を内に生のまま宿しているのであるから、すべての人間はcryptophoreであるはずである。 注3) 「危険なメソッド」、原題 A Dangerous Method, デヴィッド・クローネンバーグ監督、マイケル・ファスベンダー、ヴィゴ・モーテンセン、キーラ・ナイトレイ主演
注4) https://www.amazon.co.uk/Anatheism-Returning-Insurrections-Critical-Religion/dp/0231147899/ref=sr_1_1?keywords=Anatheism&qid=1581227203&sr=8-1 注5)「血と言葉 - 被精神分析者の手記」マリ・カルディナル著、柴田都志子翻訳、リブロポート 注6) 後日、イリーナからメールがありпеть(歌う)の語源として以下のような指摘があった。петь, пить(飲む), поить(飲ませる)は同根と看做されている。питьはラテン語potare(drink)から派生しているものと思われる。ここから英語potable(飲むに適した), potion(「薬液、毒などの」一服), sym-posium)(饗宴、事実プラトンの『饗宴』は古ギリシャ語ではΣυμπ?σιονである)。poi-, pi-といった接頭辞は「液体を吸収する」の意があり、つまり「飲む」ことにつながる。神への供物としての飲みものと祭儀に歌われた賛美歌が結びつき、ふたつの言葉は同根と看做されるようになった説明される。「毒」はロシア語でядであり、ファルマコンについて、ドイツ語のGift(毒)について、さらにはsacrificeについて、ちょうど注2) で述べたことに話しが繋がる。ようやく届いたMax VasmerのRussisches Etymologishes Werterbuchともう直ぐ届くであろうThe Origin of the Indo-Iranians: 3 (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series)等を基に別稿にて認める。 |