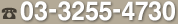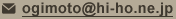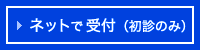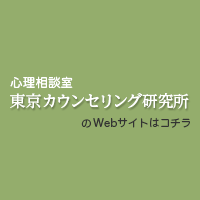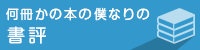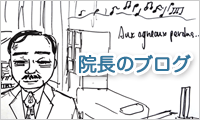|
ジャック・ラカン
 |
 『ラ・トゥルワジィエーム』 La Troisième 31.10.1974 / 3.11.74駄洒落はこのぐらいにしておきましょう。本題に戻ります。三番目の女について、強調しなければならないことは、かの女がもたらす現実界についてです。それゆえ、わたしが判る範囲内で、みなさんに質問をします。わたしが判っていることとは、わたしとともに、わたしより前に、ほんの少し気づいていた人たちがいるということ。単に気づいていただけでなく、かれらはこうも言っているのです。かれらがそのことを言ったということは、かれらがそのことに気づいていたことの現れなのだと。そしてそれがわたしの問いでもあるのです。精神分析は症状のひとつではないのか、という問いです。 みなさんご存知のように、わたしが問いを立てるときは、それに答えることができるからそうするのです。しかしながら、やはり、よい答えが出ることが望ましいですね。わたしは、症状を、現実界からやってきたものと呼びます。つまりそれは、小魚23)のように示されるのです。小魚とはいえ、食いついたら絶対離しはしません。次の二つのうちひとつしかありません。あるいはそれは増殖し続けるかもしれません。主はこう言われました、「育み、生めよ増やせよ地に満たせ」と。でも、このこと自体,大騒ぎするほどのことではありません。この増やすという言葉が気に障るとおっしゃるかもしれませんが、主は、増えるのは小魚ではないことをちゃんと心得ています。もうひとつの可能性は、小魚がなにも生まず、丸太りとなることです。 最善策はといえば、われわれが立ち向かう姿勢を示すことでしょう。なにに対してかと言うと、現実界が症状ではち切れんばかりになっていることに対してです。ですが、そこに問題があるのです。どう立ち向かうのかです。
どうやら、はなしが脇道に逸れてしまったようです。それでも、脇道からでも、行方は解っていますから大丈夫です。症状の意味は現実界の未来にかかっています。プレス会議25)で述べたとおり、精神分析の成功に関するものです。精神分析に要求されるのは、われわれから、現実界と症状を厄介払いすることです。もし精神分析がこの問題に添って取り組み続け、この要求に対して、ある程度成功裡にことを運べるのなら、期待してもよいでしょう、と言っておきましょう。プレス会議にいらっしゃらなかった方たちがここにお見えですので、これらの方たちにお話ししているのです。期待は、すべてに対してです。つまり、たとえば、真の宗教の回帰への期待です。この道は、ご存知のように、廃れてはいません。真の宗教は、狂人の戯言ではありません。すべての希望は、真の宗教において、いわば、讃えられます。聖化もされます。当然、聖化は真の宗教で容認されているのです。 仮に、精神分析が成功を収めることができるとしても、忘れ去られた症状であることによって消え行く運命にあるのです。だからといって、狼狽してはならないのです。それが真理の運命であり、真理とはそういう風に原理を立てるのですから。真理は忘れ去られるのです。ということで、すべては、現実界が執拗に生き延びるかどうかにかかってくるのです。そのためにはpour ça、精神分析は、失敗しなくてはなりません。認めなくてはならないことは、精神分析は、失敗する道を辿るべきで、そうすれば、症状のひとつとして、生き残るチャンスがまだあり、成長し、繁殖するチャンスだってあるのです。精神分析家は死なず、その後に文字は続く!だがご用心を。わたしが言ったことは、逆転したメッセージかもしれませんからね。多分、わたしも急いで飛び込んでゆくことになります。急ぐということの意味を強調するのも、みなさんのためなのですから。 それにしても、わたしが言ってきたことは、誤解を受けるでしょうね。今しがた申上げたことは、精神分析は、社会的症状なのかどうか、という意味で理解していただきたいのですが。社会的症状は、じつは、ただひとつしか存在しません。どういうことかといえば、各個人の現実の姿はプロレタリアートだということです。つまり、だれも、個人的レヴェルでは、社会的絆lien socialを築くためのディスクールをもっていない、いいかえると、見せかけをもっていないということです。マルクスが粉飾させて述べているのもこのことなのです。見事に粉飾させていますがね。そう言ってしまったからもうお仕舞いです。かれがそう発言したことで、なにも変わらなくなってしまったのです。だから、これからも、ずっと同じ状態が続くことになるのです。 精神分析は、社会的次元では、他のディスクールとは違った整合性をもっています。この整合性は、二者のあいだの絆がもつ整合性です。このことから、この関係が性的関係の欠如の場に見出されるのです。しかし、このことだけで、社会的絆が築かれる訳ではありません。ご覧ください、性的関係は、すべての社会形態を見渡しても、欠如しているではないですか。この欠如が真理に結びついており、そこからすべてのディスクールのかたちが与えられるのです。それゆえ、こうも言えます。分析的ディスクールに支えられている団体など現実には存在しません。ある学派がありますが、けっして、協会であることで、この学派が規定されているのではありません。この学派は、わたしがそこで某かを教えているということで規定されているのです。ここで、パリ・フロイト学派のことを言うとお笑いと思われるかもしれませんが、この学派では、たとえば、ストア派の学徒が行なっていた類のことが窺えます。たしかに、ストア派の学徒は意味するものsignansと意味されたものsignatumの区別を考案しました。これに対して、わたしは、自殺についての尊厳をかれらに負うています。勿論、狂言自殺などは論外です。自殺が、本来的な意味において、行為acteとなる場合です。勿論、為損じてはだめです。そうでなければ、行為のかけらもありません。 以上のことは、思想上、問題はありません。精神分析家は、思想とは、そもそも錯乱しているということが解っています。このことで、分析家が、あるディスクールについて、このディスクールが分析主体analysantを結びつけることについて、責を負うことに変わりはありません。なにに結びつけるかですが、今朝、ある人が言ったことは正鵠を得ています。分析家に結びつけるのではありません。かれが今朝言ったことは、わたしは一寸ことばを変えて言いますが、うれしいことに、かれとは意見が一致しているのです。このディスクールは、分析主体を分析主体 - 分析家のカップルに結びつけるのです。かれが今朝言っていたことは、このことです。 不愉快と思われるでしょうが、これから将来、分析家が頼りにするのは、現実界なので、この逆ではありません。現実界の到来avénementが分析家の手によるということは絶対ありません。分析家は、これに抵抗することを使命と感じています。しかしどうあっても、現実界は、制御が効かなくなり暴れ回るのではないでしょうか。特に、科学のディゥクールを支えにするようになってから、抑えが利かなくなってきています。 サイエンス・フィクションで展開されるのも、この現実の猛威です。わたしはこのジャンルのものを読みませんが、分析中の分析主体が、あたかもSFの世界のなかで起こるような想像を超えた話をわたしにします。優生学eugéniqueとか安楽死euthanasieとか、あらゆる極楽トンボ的冗談euplaisanerieをです。滑稽にみえるのは、科学者たちが、もちろんこの科学的フィクションにではなく、もっぱら不安にとらわれるときです。このことで教えられることは多いのです。この科学者たちの不安は、現実のできごとに対する症状に属しているからです。たとえば、生物学者が研究所のなかに缶詰を強いられる場合を考えてみましょう。理由はこうです。研究所内で扱っている病原体の害毒性が極めて強く、この病原体の汚染が研究所の外部にまで及び、この病原体が原因で、有性生殖が不可能になり、あるいは人間parlêtreが絶滅する、といったショッキンッグな想定がかかっているとすればです。このような極端な責任の追及は超喜劇的です。感染という事実しか考えていない頭でっかちには、すべての事柄が感染に染まってしまい、これがまことしやかに見えてきてしまうのです。厄介なことは、このことは生物学者には解らないのですが、死は限定的で、ララングのなかで、しるしを残すだけですから。 ともあれ、いま、行きがかり上強調して挙げました"eu"によって、われわれは、普遍的善に慣れっこになって麻痺しているのでしょう。わたしがカントとサドを結びつけることにより、永久に不可能であるとした関係の欠如の替わりに、このeuが居座ってしまったのではと思います。カントとサドについては、わたしが書いたものが、その当時から、目の前にぶら下がっている未来を言い当てていると自負しているのですが、この未来は、精神分析にも、いわば約束された未来があるという場合と同じとも言えます。「フランス人よ、共和国主義者たるには、あと一歩の努力が必要だ」。このサドの嘆願に、答えるとしたら、それは皆さん方の番です。もっとも、みなさんにとって、拙論はどうでもよいものなのかもしれませんが、なかには、『カントとサド』に首を突っ込む御仁もおられたようなんで。でも、かれらにとんでもないことが起きたといったスキャンダルには発展しませんでした。わたしのセミネールのひとつ26)の最後で、書いたように、わたしがわたしののダーザインを食べれば食べるほど、みなさんにはその影響が及ばないようですね。 この三番目の女を、わたしは読みます。最初の女が戻ってきたのだと記憶しているみなさんにとっては、最初のローマ講演でのわたしの話しっぷりparlanceも蘇って聞こえると思います。なにせ、最初のは、その後活字になってしまっていますからね。みなさんがこのテキストをちゃんと流布できるように、といった口実のもとにでしょうが。今日、リピートして流すことしかしない訳は、わたしが三番目の女を読むのを聴いていただくのに、差し障りがない程度に、といった配慮からです。三番目の女も三番煎じでしたら、お詫びいたします。 最初の女がまた戻って来るのは、かの女が書かれることを止めない、つまり必然的であるためです。最初の女とは『 … の機能と領域』27)であり、わたしは、そこで、言うべきことを言いました。つまり、解釈とは、意味の解釈ではなく、多義のもののうえでの戯れ言だと述べました。その訳として、わたしは、国のことばlangueにおけるシニフィアンというものに、アクセントをおいて強調しました。また、わたしは、このシニフィアンを、文字の反復要求28)として示しました。その理由は、わたしのことを、みなさん方に欠けているストア主義にも理解が行き届くためにそうしたのです。そこから、それ以上の効果を期待することなく、こう付け加えたのです。つまり、ララングからその解釈が働くと。だからといって、やはり、無意識はいち言語のように構造化されてはいるのです。言語のうちのひとつは、まさに、言語学者の扱う領域ですし、それは、ララングが働く様を示して見せているのです。それを、かれらは、一般に、文法と呼んでいます。あるいは、イェルムスレウは、形式formeと呼んでいます。それは、一筋縄では行きません。あるひとが、わたしの艶だしによってですが、グラマトロジーにアクセントを置いて強調してしまったとしてもです29)。 ララングは、望みvoex (souhait) が動詞「望む」vouloirの直接法三人称veutと、否定するnonが名を与えるnomと同じ発音であることが偶然ではないように、また、「かれらについて」d'euxが数字の「2」deuxと同じ発音であることも、まったく偶然でも、ソシュールが言うような意味で恣意的でもないようにしてしまいます。ここで連想してほしいのは、沈積、堆積、石化といったもので、その無意識的経験のグループによる言語使用によって記されているものです。 一国語は生きている、と言うべきではありません。なぜならば現用のものだからです。むしろ、一国語が持ち込むのは記号の死です。ララングがそれ自身が享じることjouirに逆らって動く必要などないこと、このことは、ララング自体がこの享じることからできているのですから当然ですが、無意識がいち言語のように構造化されているからそうなのではありません。分析家は、転移状況において、知を想定された主体とされますが、誤って、そう想定されている訳ではありません。知であるものとして、そしてこの知はララングで分節化されるものとして、無意識がなにでできているか、かれが知っているかどうか、誤って知を想定されているのではないのです。語っているのが身体であるとき、身体は、身体自らが享じている現実によってしかララング結びつくことはないのですから。本当のところは、身体は、そのものとして理解されるべきです。身体は現実界から解き放たれているのです。現実界は、身体に、その享楽をもたらす名目で存在しているだけで、それでいて、身体にとっては、やはり不透明な部分なのですから。あまり着目されない謎があります。ララングとはいったいなにものかという謎です。ララングは、この享楽を、いわば、飼い馴らすのですが、言い換えると、享楽に文明開花という効果をもたらすわけで、この効果により、身体は対象を享受することになります。対象のうち基本的なものを、わたしは、"a"と表記しますが、何度も繰り返しそう言い続けましたが、この対象については、そのものとして、よく解らないものです。申上げたいのは、この対象は、これを粉砕してしまわないかぎりですが、どうあっても、その小片は、身体の部分に対応してしまうのです。つまり、身体の開花に対応するのです。そして、精神分析によってしか、この対象は、享楽の核として形成されることはないのです。しかしながら、対象は、結び目の存在によってしか支えることができません。三つのトーラスという実質consistances、あるいはこれを構成する三つのひもの環によってできる結び目の存在によってしか変えることはできません(図1)。 奇妙なのは、享楽はどれも、この図における対象というものを措定しており、したがって、剰余享楽le plus-de-jouirも、その場所が、ここにあるとわたしは信じてきたのですから、すべての享楽にとって、その条件となっている、ということです(図1)(図2)。 簡単なシェーマができました。身体の享楽がどのようになっているのか、この享楽は生命の享楽でもあるのですが、これがどうなっているのか示すためだとすると、驚くべきことは、対象、"a"は、このファロスの享楽から身体の享楽を引き離しているということです。このことに関して、みなさんは、ボロメオの結び目がどのようにできているのかお解りになっていなければなりません。 ファロスの享楽が身体の享楽のでき損ないとして出来上がったことについては、十分お解りいただいているものと思います。ここにお見えの方たちのなかに、どれぐらい、インドからやってきた愚にもつかない話について通じている奇特な方がいらっしゃるかは解りません。かれらがクンダリニーと呼ぶものです。なかには、このクンダリニーを脊髄のなかで、上方に向けてゆくことを試みたりする者がいます。脊髄をもちだすのは、解剖学の知見に添ったものなのでしょうが、頑に、脊椎の突起が随なのだと言い、ここから脳にまでクンダリニーを上らせるとしている者もいます。 ファロスの享楽は身体の外hors-corpsで起こるのです。このことを理解するには、実は、今朝、このことを知ったのですが、ポール・マティスのお蔭です。わたしは、かれに賛辞を贈りたいと思います。エクリチュールと精神分析についてかれが書いたものを読むことができたからです。両者の関係について、マティスは、今朝、すばらしい実例を示してくれました。三島は、凡庸ですが、かれはこう言うのです。聖セバスティアンの殉教の図をみて、かれは初めて射精を経験したと。そして、射精というものに三島はびっくり仰天したと。そんなはなしは毎日のように聞かされます。最初の自慰を、分析主体はみなさんに語るでしょう。ありありと覚えているのは、それは、圧倒的なイメージで迫って来るça créve l'écranものだから、と。なぜ、圧倒的なイメージなのかはよく解ります。なぜならば、それは、スクリーンl'écranのなかからやって来たものではないからです。身体は、享楽の秩序へと導入されます(わたしの話しはそこからスタートしたのです)が、それは身体のイメージを介してです。人間,と呼ぶことにします、人間の身体に対する関係は、そこにイマジネールと特徴づけられるなにかが存在するならば、イマージュというものが限界をもっているということです。そしてそもそも、このことを強調したいのですが、やはり、現実のなかに根拠を求めるべきだということです。それはボルクが言っている、人間の未熟さのことです。ボルクが言っているのです。わたしではありません。わたしはオリジナルな仕事をするタイプの人間であろうとはしませんでした。どちらかというと、論理学者たらんとしていました。人間の幼児の未熟さのみによってしか説明できません。つまり、この未熟さゆえ、幼児には、身体の成熟とそこからの成り行きを先取りすることから、イマージュへの傾倒が起こることが説明されるのです。もちろん、この成り行きとは、つまるところ、幼児は、自分の同類をみるとき、この同類がかれの座を奪ってしまうと考えることしかできません。それゆえ、かれは、この同類に敵意をもちます。 どうして人間のこどもは自己像にこうも呪縛されてしてしまうのでしょうか。お気に留めてではないでしょうが、お判りしょう。わたしはいっとき、このことを説明するのに苦労していました。わたしが考えたのは、この像に、何種類かの動物に共通の原型といったものがあるのでは、つまり、像というものが発生学上、重要な役割を果たしている契機があるというものでした。わたしは、サバクトビバッタ、その他諸々、トゲウオ、雌鳩といったものを研究しようと思っていました … 実際、これらの考察は、断じて、肩ならしとか、準備運動とかいった類のものではありませんでした。では、主菜に対する前菜みたいなものといえるのでしょうかね。ともかくも、ひとは、自分の像をしげしげと観るものです。単にそう言うしかありません。 しかし驚くべきことは、像の問題は、これによって、ひとが十戒をもずらしてしまうところにあります。ともかくも、人間は鏡のなかの自己像よりも自己の存在において、自己自身により身近にあるのだとして、「汝、汝の隣人を汝のごときに愛せ」と言ったとき、十戒をめぐる展開はどうしたものでしょうか。これがとんだ迷妄に基づいているとするしかありません。奇妙な迷妄ではありますが、人間は、かれの隣人ではなくかれに似た者を憎むのです。こんなことはどうでもよいことだと思われるかもしれませんが、無視できないことは、ともかくも、神がきちんと知っておくべきことは、自分が言っていることがどのような意味をもつのか、つまり、だれでも、自己像よりも自分自身を愛するといった傾向があるという事実についてです。 はっきりしていることは、「自分を弄ぶ se jouir」ものとはなにかと問うならば、それは動物だということになることです。これを証明することはできませんが、突き詰めて考えてゆくと、動物の肉体と呼ばれるものが関わっているように思われます。 拡大解釈をし、生命という名の下に、植物も享楽を得ているのかどうか考えてみましょう。この問題は興味深い方向に展開してゆきますよ。考えてみるだけのことはありますよ。こう質問されたらどうするかです。野に咲く百合はどうだ、と。百合は茎や花といった組織を編み上げるような運動をしないでしょう、と反証を加えてです。もちろんこの反証には納得できません。顕微鏡を覗けば、まさに組織が編み上げられてゆく様を観察できますから。編み上げるという営為によって、百合は享楽を得ることができると言えるのです。だからといって釈然としない部分は残ります。生命が享楽を包摂しているかどうか、はっきりさせなければなりません。植物にはやはり享楽はあるとは言いがたいとするとしても、喋るということparoleでの次元以上にはっきり見えてくるのは、享楽が欠如し、既に申し上げましたが、ずたずたに傷つけたうえゴミのように捨てられ、といった状況においてさえ、このララングは、それでも、言語un
langageによって追放された生命から、この死んだ木が植物という種に属していることを教えるのです。 |