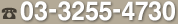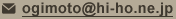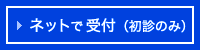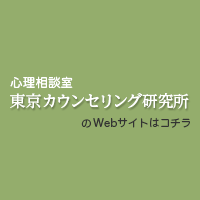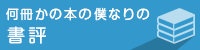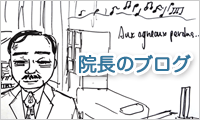|
ジャック・ラカン
 |
Verbier de l’homme aux loups試訳( » Verbier de l’homme aux loups試訳について はコチラ )原注の(1), (2), (3),…→原注(1), (2), (3)…, p.75 はじめに 狼男との5年間 5年間は、分析の期間としては平均的だ。われわれ二人は狼男と共に過ごした。この間かれはフロイトの例の作、ルース・マック・ブランスウィック、ミュリエル・ガーディナーのものそして狼男自身の認めたものを通じてわれわれののところにいたのだ。だからかれ自身が寝椅子にいたわけではなく、ドキュメントとして定着したもので、一冊の本にでも収まるぐらいの筆録を通じてということだ。これら「資料」は大した量のものではなく、誰もが簡単に手にすることのできるものである(手記注(1)だけは本書の執筆中に巡り会えた)が、p.78 それらは推敲に推敲を重ねた読解よみの作業を必要とし、本書にみる最終稿として完成をみるまでにはまさに熟成の過程というものがあった。分析の進行というものはひとりの患者だけに帰すことができないものであり、その実験的といってもいい証明をここに見ることができる。狼男は二人のパートナーにとって、同時並行的でありながら、相互補完的な進化をもたらしたのだ。われわれ独自の経験においては、分析セッションの終わりなき延長に代わって、限りない再読、同じドキュメントでありながら、読み返されるたびに別の顔を見せる再回帰があった。 注(1) M・ガードナー、狼男による狼男、ニューヨーク、1971、ベイシック・ブックス、「無意識の知コネッサンス ドゥ ランコンシィアン」シリーズで、ガリマール出版より近刊予定
患者はというと、この回路からは外されていた。ただ分析家だけが「仕事をしていた」のだ。この実在していながら小説上の患者から共鳴音を得るため5年間の再聴取を要したわけである。 訳注1)archéonyme、例えばラカンも後期になるとlalangueなる新造語を用いているが、この概念はセミネール初期におけるかれのテーゼとして有名な「無意識は言語のように構造化されている」との関連で見るとどうみても逕庭が甚だしいと訳者は吐露せざるを得ない。lalangueは言うならば、母親の赤子への愛撫によって赤子(の身体)に寄生するものである。ラカンはlangageが寄生するともparoleが寄生するとも言っている。いわば、これは母親の多形倒錯的性愛によって植えつけられることばである。母親の多形倒錯的性愛は世代を通じて受け継がれてきたもののはずである。乳母と赤ん坊とのあいだでも同様のことが行われてしかるべきである。異なった家系のあいだでの伝承であれ、これは代々行われるものと看做せる。要は、母親であれ乳母であれ、かの女それぞれと赤ん坊との二者間において極めて内密の交わりがあり、この内密さゆえ、当事者もそれを想起することもできず、そのトポスが自我のなかに組み込まれていようと、それはいわゆるノーマンズランドであるクリプトに隠されたもの/ことである。lalangueはこうして原初語に基づいているはずである。ラカン自身にはVerleugnungが働いているのであろうが、クラシカルなラカンからするとこれは変節に等しい。因みに、記憶とは、それが想起できるものであれ、なかれ、刻まれ(傍点=訳者)るものであるゆえ、外傷なのである。 約2年間にわって「資料」についての満悦感に満ちた日々が続いた。これ以上明らかにする秘密は残っていなかった。 訳注2)jouissanceは定訳として「享楽」が当てられるが、訳者によれば、ラカンのジュイッサンスはフロイトのGenußの単なる仏訳には収まりきれない拡がりがあり、少なくとも「楽」という漢字を含む点でこれは誤訳と看做したい。そうでなければ、ラカンならずともフランス語でいうplaisir快感との違いを際立たせることができないからである。ここでもジュイッサンスとカタカナ表記で示した。ジュイッサンスと‹もの›となれば、どうしてもラカンに言及しなくてはならない。ニコラ・アブラアムとマリア・トロックがこの語を巡ってラカンの影響を受けているのは、すぐ後でに‹もの›についても述べているからである。もちろんフロイトの事物の表象(言語表象との対比における)との関連も否定はできないが、ジュイッサンス(フロイトにおいてはGenußという語がフランス語jouissanceに最も近い語義をもつものであろうが、フロイトはこのGenußをテクニカル・タームとして厳密な定義を与えられるようには用いていない)と‹もの›とのカップルから考えれば、ラカンの影響は疑いのないものである。1959-60年のセミネール『精神分析と倫理』においてラカンは1954-55年のセミネールで取り上げたフロイトの『心理学草稿』の再読を試みる。ときには‹もの›は対象aと同列のものとして何人かのラカ二アンは論じているが、否、‹もの›≠対象なのである。ここで長々とこの問題について訳者は解説するつもりではない。最低限のことを列挙するにとどめておく。「失われた対象」という言葉がある。失われたものであるなら、「発見する」ではなく「再発見する」ことになるとなるが、これが不可能なのである。「出会いそこないの出会い」ランコントゥル・マンケをひとは繰り返すのである。つまり「失われた対象」という表現とは裏腹にそのような対象などはじめから存在しなかったのである。___‹もの›はカントの‹物自体›ではない。カントの‹物自体›は『純粋理性批判』で取り上げられる、理論理性の相関者としての現象の彼岸にあるものとして、「知り得ないもの」であった。ラカンの‹もの›は『精神分析と倫理』で同様に重要なテーマであるカントとサドとの相関にあり、ここで俎上に上がるカントは『実践理性批判』のカントである。理論理性では到達不可能の物自体も実践理性によって叡智界との直接的な関わりにおいて補償され、そこでの‹物自体›は最高善に崇めたてられていた。ジュイッサンスについてはJean-Marie Jadin, Marcel RitterによるLa jouissance au fil de l’ensignement de Lacanがタイトル通り、セミネール等、ラカンの教えを年ごとに追ってゆきながらここのジュイッサンスについて説明が施されており、便利な本である。ところで‹もの›のジュイッサンスjouissance de la Choseということばをラカンは一度しか発していない。それは『同一化』のセミネール(1962年4月4日)においてであるが、‹もの›とジュイッサンスとの関係でいけばやはり『精神分析と倫理』さらには1968-69年のセミネール『ある他者から‹他者›へ』が重要である。ジュイッサンスは不可能である(「不可能である」ことと「禁じられている」こととは微妙な関係にある。ジュランヴィルはすっきりと述べているがことはもっと複雑である - この問題にはここでは触れないでおく)。子どもにとって最も身近な人間である母親はこの‹もの›を具現化したものである。この‹他者›とジュイッサンスとの関係についてラカンは、コンテキストとしては、芸術作品、昇華、商品、価値といった複雑な絡み(このことを説明するとなると新たな一稿が必要となろう)において、当の芸術作品に特権的な価値を与え、これをジュイッサンスと規定しており、ここでのジュイッサンスは「ひとつの術語として、‹他者›の領野から排除されるものとしてしか規定できないし、この場合、‹他者›の領野の位置付けとしてはことばパロールの場という位置付けになってしまします」と述べている。この問題意識はセルジュ・ルクレールの『子どもが殺される』と重なっており、これはクラシカルなラカンとの整合性が保たれている部類で、ジュイッサンスの禁止としてのインファンス(子ども=ことばを喋らない者)の殺害であり、端的に言うと、象徴的なものからのジュイッサンスの規定になってしまっている。一方でジュイッサンスがラカンの領野であり、フロイトの領野である欲望との対比において、晩年のラカンはジュイッサンスの様々な様相を明らかにしてゆくのだが、その都度クラシカルなラカンの定式にずれが生じてゆく。あれだけ特権視されていたことばパロールはこの1968-69年のセミネールの冒頭で「精神分析理論の本質はことばパロールなきディスクールである」とマニフェストせざるを得なくなるのであり、では先に触れたララングはどのように位置付けられるのか、といった問いが発せられよう。逆に、この問いはニコラ・アブラアムとマリア・トロックによってインスパイアされたものと大胆な仮説を立てることもできよう。ひとつだけ言い加えたいことがある。この『他者から‹他者›へ』が初出でもありジュイッサンスのいち様相であるプリュス-ドゥ-ジュイール le plus-de-jouirについてである。周知のことであろうが、le plus-de-jouirはマルクスの剰余-価値 le plus-valueから借りてきたものである。資本主義世界では労働力も商品として扱われる、しかしながら、労働は労働力の価値に付加価値を与えてしまう。労働-労働力=剰余 - 価値との式が成り立つ。剰余-価値が労働の搾取exploitationによってもたされるとするのがステレオタイプな左派政党のモットーとして定着してきたが、exploitationを搾取と訳すのは行き過ぎの感がある。ドイツ語でもエクスプロウァタツィオンと発音されるこの語を辞書で引いていただきたい。『他者から‹他者›へ』にはダナイデスの壺に触れている件がある。壺に水を汲み入れる作業を命じられた娘たちはそれに従うのであるが、肝心の壺はそこに穴が空いているためこの労働は際限ない労働となる。繰り返すが、労働は商品であり、剰余-価値はその一部が資本準備金となりこれが資本金となると再投資がなされる。そうなると新たな労働が必要となる。ジュイッサンスは民法でいう用益権ユズフリュイ usufruitと同義語でもある。資本は投資することにより、これを益が出るように用いるためのもので、もしこれをなんらかの目的で取り崩すことにもなれば、いわゆる減資となってしまうので、これは避けねばならない。ジュイッサンスのネガティヴな面からの定義であり、禁止すべきものとしてのジュイッサンスがここにある。ところでプリュス-ドゥ-ジュイールは対象aでもある。ジュイッサンスが禁止されていながら、ラカンの超自我(フロイトではなくメラニー・クラインの超自我に最も近い)はジュイ!Jouis!と主体に(自我とはラカンは言わない)命ずる。すると主体は同様にジュイ!J’ouïsと答える。しかしジュイッサンスは禁じられている(誰が、なにが禁じているのか、少なくとも超自我ではないはずである)。であるから主体はその都度対象aを求める。欲望が反復強迫に支配されているのである。つまり欲動(より根源的なものとして死の欲動)が欲望をもたらすものだと端的に言える。しかしこの点についてもラカンは死の欲動pulsion de mortと言ったり死の本能instinct de mortと言ったり一貫性がない。誰だかがラカンは強迫神経症だったのでは、と言っているが、訳者も同感であると思うときがある。 原注(I)この新しい魔女の箒については以下参照のこと。ニコラ・アブラアムによる操作オペラションとしての象徴サンボルに関する研究(1961)、取り込みアントロジェクションについての補足を加えた分析概念であるアナセミックな本性についての考察(1968)を踏まえて、われわれの臨床的 - 理論的研究の主眼は象徴的な操作が無効な症例に向けられることとなる。このような症例においては、取り入れが欠如しており、リビドーと象徴的な発展をもたらしうる機能との出会いは見られない。 指針となる問いとしては、メタ心理学はどのような新規の概念装置を分析運動領域を拡げてゆくために与えるべきなのか、であり、並行して、「分析不能例」あるいは「終わりなき分析例」の限界設定をどのように行うべきか - この後者については狼男の症例が典型的である - 、である。この問はクリプトをもつ障害クリプトフォリーについてのいくつかの論文、著作によって扱われている(症候論的問題にはわれわれは立ち入らないが、ある種の「フェティシスム」- ある種の「ヒポコンドリア」- ある種の「固着念慮」- ある種の「躁うつ病」- ある種の「病的喪の仕事」等がこの境界線上にある)。 一歩一歩提起された問題に対してそ概念が明らかにされていっている。例えば「固守的抑圧ルフールマン・コンセルヴァトゥール」、「心内的・クリプトクリプト・イントゥラプシシーク」、「クリプト内同一化イダンティフィカション・アンドクリプティーク」等々である。 このような問題提起が起きてきた諸段階の足跡は1968から1975のあいだ、つまり本書の執筆前、執筆期間に書かれた論文中に窺うことができる。 付記するが、このことを強調しておかねばならない。二人の人間のあいだでの分析の作業 - 新たな現実の創造的対話であり - とは異なり、ドキュメントを基にした精神分析理論の構築は翻訳に過ぎない。既存のテキストの創意された(アップ・デイトされた、と創造された、との両方の意味をもつ)テキストへの翻訳であるからである。翻訳家は二重の意味で裏切り者である。他者と自己自信を裏切るからである。なにももたらさない者である。それでも、その作品は、フィクションの色に染まったものであれば、オリジナルなものに近づくことができる。ただし漸近的にそうなのであって、あらゆる翻訳、裏切りを招くものの場へと収束してゆく。 編集部より 以下に挙げる論文は近々一冊の本のなかに所収のものとなり本書と同シリーズのものとして刊行予定である。現在のところ、候補としてあげられているものを列挙する。 Verbier de l’homme aux loups試訳について
本試訳は“Le verbier de l’homme aux loups” Nicolas Abraham, Maria Toron, Aubier-Flammarion,1976の冒頭部分( 本文の前にDerridaがForsと題された序文を認めているが)である。この試訳を始めて間もなく、大西雅一郎、山崎冬多両氏による邦訳本が既に上梓されていることに気づき、この試訳の作業も意味のないものとなるかもしれないと思い、暫く放っておいたのだが、本書に対してLacanがかれの1977年1月11日のセミネール(L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourreというタイトルであるが、こうしか読めない : L’insuccès de l’une-bévue, c’est l’amour。une bévueは何人かのラカ二アンが言っているようにl’inconscientのことだとして、単純にぱっと思いつくのはフロイトの『機知』Witzとの関係における無意識である。人間は「大間違い」をするからこれを無意識的にこねくり回し、あるいは誤魔化し、しかもそれを正当化しようとする、タイトルだけからするとこのような顕在する意味にとってよかろう。ただしドイツ人とフランス人ではWitzとmot d’espritの差ほどこの(「理性の」ではなく«parletre»の)奸策には逕庭があるはずだ。もちろんaileと書かれている - 誰がこう書いたのかは判らない。Lacanはこのセミネール後もしばらく存命していたので、Millerが勝手にこう書いたのだとしても、Lacan自身が容認していたのだとしたらこれを認めねばなるまい - し、これとl’amourとの関係でいうと、les ailesだとして - 両翼がなければ飛ぶこともできないであろうから当然複数形でしかるべきだ -
La définition de l’amour de Lacan : donner ce qu’on a pas, mais par ailleurs il dit également que soit disant amour, c’est, par essence, demande de l’amour par l’autrui. La plupart du temps, lorsqu’un homme dit à une femme : «Je t’aime», celle-ci riposte immédiatement : «C’est pas ça. C’est pas toi qui aime, mais tu veut, en revanche, être aimée par moi. Ouf ! tous les masculins sont égoïstes». Mais je crois cette définition, c’est la définition même de la marchandise. Si c’est ainsi, comment la valeur est déterminée pour chaque marchandise ? Selon la formule de Marx, ce qui crée le plus-value (der Mehrwert), c’est une soustraction : le travail moins la force de travail. Le capitaliste achète cette force de travail du travailleur. Là, déjà, la marchandisation de la force de travail. Lacan traduit ce plus-value en le plus-de-jouir. Le plus-de-jouir concerne bien sûr la jouissance, mais Lacan l’appèle également ‹a›, objet petit (a). |