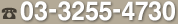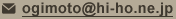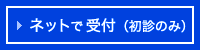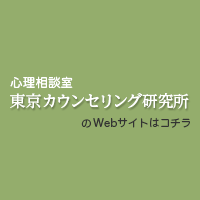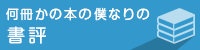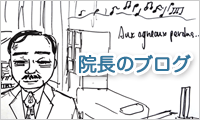試訳、アンドレ・グリーンとの対談 - 精神分析の緑化運動
原注1. 2. 3. …
訳注1). 2). 3). …
イラリック→太文字
ルビ→下線
固有名等のカタカナ表記については、定訳のあるものはそれに従ったが、例えば、salles de gardesを訳者はよりオリジナルの原語に忠実にサル・ドゥ・ガルドゥとの表記にした。
精神分析の緑化活動1. 1).
Gregory Kohon(以下G.K.)とAndré Green(以下A.G.)の対話2)
G.K. - 実を言うと、なにも準備していませんが…
A.G. - わたしもそうです。
G.K. - …でも、あなたの業績についてお伺いする前に、差し支えなかったら、これまでの実生活についてお話しいただけないでしょうか。
A.G. - ご存知でしょうが、わたしについて二冊の本が上梓されています3)。最初のは主張する精神分析家アン・プシカナリスト・アンガジェ、これはスペインおよびスイス系精神分析家であるマニュエル・マシアスとの対話で一連の対話集のうち最初に上梓されたものです。二冊目はフランソワ・デュパルクによるアンドレ・グリーンですね2。話をわたしの実生活に戻しましょうか。
G.K. - …そうしてください。
A.G. - わたしは1927年、エジプトのカイロで生まれました。わたしの父親はアレキサンドリア出身で、母親の家族がエジプトに居を構えるようになったのはかなり昔のことです。両親ともスファラディ系ユダヤ人です。母親の旧姓はバルシィロンです。因みに、いとこの一人はニュー・ヨークに住んでいて名前はジョゼ・バルシィロンです。母親の家系は有名です。かれ等はスペイン出身ですが、モロッコのテトゥアンに移り、それから地中海沿いにですが、昔も国境がいくつかありましたので、これ等を越え、最後にエジプトに落ち着くこととなったのです。最初はナイル川のデルタ地帯に住んでいたのですが、それからカイロおよびアレキサンドリアに移ったのです。
G.K. - 異端審問が直接影響してのことでしたか。
A.G. - そうです。一方父親の家系についてはよくわかりません。原因はいろいろあります。自分の家系については父親の口はかなり固かったのですが、ほとんどはアレキサンドリアに住んでいました。わたしが生まれてから我が家はずっとカイロでした。ところで父はアレキサンドリアにとどまっていた親類とは疎遠でした。父の家系のルーツはスペイン人かポルトガル人です。父はスペイン語ができましたが、喋ることはありませんでした。一方母親はよく喋っていました。父のファミリーがなぜエジプトにやって来たかはさらに謎めいています。話ではかれ等はハンガリーからやって来たそうです。つまり反体制の国から東ヨーロッパを経て、トルコ、中東諸国へ、そしてエジプトに渡ったことになります。表向きの話は以上です。父親の従兄弟のなかには父親よりもずっと裕福な人たちがいて、
1.オリジナル・タイトルは «The Greening of Psychoanalysis» - André Green in dialogues with Gregorio Kohonである(仏訳者による)。
1).「緑化活動」と訳したが、もちろんこれはAndré Greenのgreenからgreeningというもじりになっているわけであるが、因みにフランス語訳では«regain»となっている。regainとは、草、あるいは人工草原である芝生などの刈り入れの後、再度が生えてくる草のことである。ここからアナロジカルに「再生」の語義を連想できる。フランス語訳はAna de Staal, Andrew Wellerによる。
2).アンドレ・グリーンにより録音されたものに修正が施されている。
2.主張する精神分析。マニュエル・マシアスとの対話、パリ、カルマン-レヴィ社、1994年 ; フランソワ・デュパルク、アンドレ・グリーン、パリ、P.U.F.、1996年。(この他にアンドレ・グリーン、ほぼ自由な連想を実践する精神分析家、モーリス・コルコスとの対話、パリ、アルバン・ミシェル社、2006年も加えておく。仏訳者による)。
-p.10-
そのせいでわたしの名前はGreenと綴りますが、元の名前Grenにeがひとつ加わっているのです。GrinbergとかGreenmanとは無関係です。そのような名前の親類はいません。誰かがより英語風にとスノッブだったんでしょう、eを加え、それはよいとすべてのGren名の一族はこれに倣ったのです。
父親一族がエジプトにやって来てからは、そのことに触れてはならなかったのです。ともあれ、エジプトでの生活は奇妙でした。エジプトにおけるフランスの影響は格別でした。ことの始まりは1799年のナポレオンの遠征のせいでしょう。例えば、フランス文学を通読していらっしゃるなら、お判りでしょう。東洋を旅している大作家、シャトーブリアン、フロベール、ネルヴァル等々はエジプトに比較的長期にわたって逗留しています。当時のエジプトではアラブ系のコミュニティーとヨーロッパ系のコミュニティーがあり、政治、行政用語としては英語が重要視されていましたが、公用語はヨーロッパ諸言語のなかにあってフランス語でありアラビア語ではなかったのです。文化はコスモポリタン色が強かったのですが、言語はというとフランスの影響が強大でした。この傾向に弾みをつけたのがムハンマド・アリー4)でした。かれはフランス贔屓でしたから。いろいろ記憶していることがあります。これを聞いて驚く人もいると思います。例えば母はラジオで、ドイツ軍によるパリ陥落のニュースを聞いて、泣き叫びました。フランスはわれわれすべてにとって大切でした。我が家にとって、なぜフランスがそれほど大切なものだったのかですが、その他にも特別な事情がいくつかありました。わたしの14歳上の姉ですが、かの女が14歳のとき、フランス語ではポット病と呼ばれる、脊柱の結核に罹患しました。当時エジプトでは治療不能の病でした。この病気の治療法が確立されていたのはフランスでした(治療に要する期間は4年と定めれれていました)。ということで、姉はこの治療を受けるため北フランスに搬送され、4年間入院生活を送りました。母は、どの母親でも娘が病気で他国で治療を受けることになればそうでしょうが、悲嘆に暮れ、うつ的にさえなり、そこで両親は学校が休みに入るや休暇を取り、フランスへ渡航しました。母が姉と一緒に過ごすことができるようにと2ヶ月間の滞在でした。わたしが生まれる以前、我が家においてフランスが大切な国であったことの理由がここにあるのです。
G.K. - ご兄弟ご姉妹は何人いらっしゃるのでしょうか。
A.G. - 3人です。二人の姉と兄です。わたしが生まれたのは偶然です。家族にとって偶然の出来事だったのです。三人のなかではいちばん若い兄とは9年離れてわたしは生まれました。長姉との年齢差は、お話ししたとおり14年にもなります。母親が妊娠を診断されたのはパリにおいてでした。ですからフランスはわたしにとって大切なわけです。無意識的にね。
G.K. - あなたの祖父母についてお伺いしてもよろしいでしょうか。あなたは親密な関係を保った強い絆をもつ大家族のなかで育ったんでしょう。
4)wikipedia, 「ムハンマド・アリー」参照のこと。
-p.11-
A.G.- 祖父母についてはまったく知りません。兄弟たちも知らないのです。祖父、祖母というものがどういうものかさえ知らなかったのです。父は自分のファミリーとは本当に疎遠だったのです。父がアレキサンドリアに行くときは決まってひとりの姉か妹でしょうか、かの女に会うためでした。7人いたはずです。でもやはり父はファミリーとの絆が希薄でした。母はというと、まったく違いました。自分の父親を非常に尊敬し、畏敬の念をもっていると言っていました。ある種の学知というものがファミリー全体にとって恐れ多いと思われる類いなのでしょう。ファミリーの結束は強く、ですから母は常に兄弟、姉妹の家にいることが多かった、そんなでした。ですから、我が家では、家庭生活というものが大切だったなどとは言い難いです。わたしは特別扱いでした。兄弟たちのうち一番若かったせいです。でも同年輩の従兄弟がいました。かれはアレキサンドリアに住んでいたのですが、会うことができたのは夏だけでした。アレキサンドリアに夏行くことができたのは、海があるのとシーサイドのリゾート地があったからです。ともあれ、しょっちゅう会うことができたのはひとりの従兄弟だけです。われわれはユダヤ人、スファラディ系のユダヤ人でしたが、パラドキシカルな身の上だったのです。ユダヤ性を強く主張できたのですが、一方で、宗教的実践はまったく行われていなかったのですから。安息日サバトについてわたしはなにも教えてもらえませんでした。ヨム・キプルのときだけユダヤ人だったのです。ロッシュ・ハシャナ、ヨム・キプルそして過越の祭のときだけはシナゴーグに行きました。他人ひとから聞いた話しですが、父は、わたしが生まれたとき、ちょうどサバトの終わりの礼拝に際してですが、シナゴーグに行き、ラビがエリヤフ・ハー・ナヴィを歌うのを聴き、わたしの名をエリヤとすべきと思ったとのことです。しかし残念なことに父はこれを登録しなかったのです。父は信心深い方ではなかったのですが、かれが亡くなる2年前、そのときすでにかれは死が近いことを悟っていました。重篤な疾患を抱えていたからです。死の2年前です。ひとりのラビが家にやって来ました。ヘブライ語を教えるためです。そのことでかれが望むように…
G.K.- …全能の神の下で安らかに永眠することをですね。
A.G.- その通りです。死を前にして準備を整えるため … ところで、友だちは大切です、とても大切ですよね。わたしがヨーロッパにやって来たとき、わたしにとっては大変な変化でした。というのも、エジプトでは友だちの家にいるときでも、アット・ホームな気持ちでいることができました。いつでも友だちの家に行くことができましたし、好きなとき家に帰ることができました。いつでもご相伴にあずかることができましたしその家で家族同然に扱われました。本当ですよ。フランスにやって来て、誰か、かれの家、かの女の家に招かれるのには1年はかかると思いました。わたしに会いたいと思っている人がいたら、カフェででしたから。
G.K.- あなたが何歳のときのことを仰っているのですか。いつパリにやって来たのですか。なぜパリに。
A.G.- それはですね。我が家族に重大事が重なったのです。まず、わたしが14歳のとき父親が亡くなりました。まだ14歳のときですよ。両親とも59歳で亡くなりました。二人の死には違いがあります。両親の年齢差は8年ありましたから。ともあれ二人とも逝去しました。父親が亡くなったときわたしは14歳で、そのとき家計はかなり逼迫していました。父はそこそこの資産家でした。しかし姉の病気のことで、父は母親のヨーロッパ行きに随行しなくてはなりませんでした。おまけにフランスでの治療は高額でしたし、これが4年続いたのですから。またヨーロッパ行きの度に、父は自分の事業でのやりくりがまったくできないまま過ごす羽目になったのです。結局身上を潰すこととなるのです。
-p.12-
父親の死後家族は路頭に迷いました。家族の何人かはわたしが働くことで家族を養うことを望んでいました。しかしながら学校での成績は優秀な方でしたから、悲しそうな顔をしていたわたしを見て姉(かの女は病気が治らず学業を続けることができないでいました)が見かねて親に進言してくれました。こうも言ってくれたのです、バカロレアまでは勉強を続けるべきだと。ところがそこで別なところで狂いが生じてきました。高校の最終学年で、いやその一年前からです、病気に罹って学校に通学できなくなってしまったのです。ずっと臥病を余儀なくされたのです。しかしながらそんななか試験勉強は続けていました。バカロレアの第一関門に向けてです5)。そして及第しました。家族全員喜んでくれてわたしを援助する気になったのです。奨学金の給付を受けることが決まり、学費の半分はこれで賄い、あとの半分は家族が負担することになりました。そして19歳になってフランスに来ることができたのです。この年は第二次世界大戦の終戦の年にあたり、このとしがわたしの大学進学の年と同年となりました。しかしながら本当のことを言うと、何が何でもヨーロッパに来ることだけをずっと思い描いていたのです。ヨーロッパにやって来たのはヨーロッパの大学で学ぶためでした。ところがなにを学ぶのかは揺れていました。お金持ちの叔父がいて、まとまった金額を拠出していただきました。かれが言うには、わたしの兄と姉たちのためにそうしたのだし、わたしにはなにもしていない、だから好きなようにこのお金を使うが良い、と言ってくれたのです。そうなってもわたしはなにを学ぶか決めかねていました。どちらかというと、哲学を学ぶことに傾いていましたが、わたしはフランス人ではありませんでした。国籍を持っていませんでしたので議論の余地なしでした。哲学で糊口をしのぐには教えることぐらいです。国籍をもっていなければ、教職免許をもっていなけば、教えることはできません。ですから哲学というアイデアはすんなり諦めがつきました。
G.K.- 国籍をもっていなかった?エジプト人であることが記されたパスポートを持っていたでしょうが。
A.G.- いえいえ。
G.K.- どうやってフランスにやってきたのです?
A.G.- わたしは無国籍だったのです。父は、父のファミリーが何世代も前からエジプトに住んでいたことで、当然、エジプトの国籍が与えられていたものと思っていたのです。父の思い違いでした。ですから、お分かりでしょうが、哲学など問題外だったのです。そこで、なにかしらの科学なら学ぶことをもできるかもしれないのでは、と自問しました。しかし、それも気乗りがしませんでした。叔父のひとりがこう言っていたのです。お前はなにを目指しているのだ。まさか一生ウンコとかシッコを分析することにはなるまいな? そんな面白みのないことはやめておけ。馬鹿げている、と。覚悟を決めて、わたしは賭けをしました。挑戦に応じよう、挑戦という言葉以外ありませんでしたから、これは賭けでした。わたしはこう言いました。「医学を志します」と。そう言いながら、心では、精神科医になることを思い描いていました。一般医になる気は毛頭もありませんでしたから。
G.K.-なぜ精神科だったのですか。そう決心した動機は?
A.G.- ここからわたしの分析のスタートですね。思うに、死んだ母親6)についてのわたしの論文は臨床的知見としてだけでなくわたしの個人的な経験にも結びついています。
5)1945年、つまり第二次世界大戦対独戦の終戦の年においても、今と同様、バカロレア第一日目は哲学の試験である。当時は設問は共通であったが、今日においては、バカロレアそのものが人文系、経済社会系、理系、技術系に分かれていて、それぞれ異なる設問となっている。
6)「死んだ母親」«La mère morte»と題された論文は1980に書かれている(「生のナルシシズム、死のナルシシズム」«Narcissisme de vie, narcissisme de mort», Les Éditions de Minuit, 2019所収)
-p.13-
わたしが二歳のとき、母親はうつ病になりました。かの女には妹がいました。事故で火傷やけどを負い、これがもとで亡くなりました。かの女は末妹でわたしの叔母と母親は二人ともうつ病になりました。この頃の写真をもっていますが、一葉は、かの女が重度のうつ病であることが顔の表情からはっきり読み取れるものです。当時はメンタル関係の治療はひどくお粗末でした。カイロの近くで湯治したぐらいです。このときの経験は強く印象に残っていて、こうとしか考えられないのですが、合計三度にわたる分析をどうしても必要としたのでしょう。そのお陰でわたしの魂は生き返ったのです。こう言えるのも、父の友人との話を記憶しているからです。わたしは12歳でした。話のなかでわたしは既に精神疾患の研究をしたいと言っているのです。
G.K.- ご母堂さまが亡くなられてからどなたがあなたの世話をしてきたのですか。お姉さまたちですか。
A.G.- 当時はまだ家計はそれほど逼迫していませんでした。わたしが少年であった頃はヨーロッパ人の子守がついていました。主にイタリア人でしたが。
G.K.- イタリア人?フランス人でなくて?
A.G.- いえいえ、エジプトに居住していたフランス人たちはですね、特別な集落をつくって住んでいたのですよ。通常、かれ等はカイロに住むということはなかったのです。住んでいたのはスエズ運河河岸地域でした。運河の管理をする人たちです。つまりポートサイドに居たのです。例外的にカイロやアレキサンドリアに住んでいたフランス人はフランスの教育制度の下フランス語を教える教師であったり大使館員、領事館員あるいはフランスの文化施策に関わる人に限られていました。ですからフランス人の家政婦はいませんでした。一部のハイブローで裕福な家庭ではイギリス人家政婦を雇っていましたが、家政婦のほとんどはイタリア人でした。ですから、わたしの世話をしてくれたのはイタリア人の子守と姉たちということです。下の姉は14歳のとき学校を辞めました。わたしは12歳年下でしたので、わたしが2歳のときからかの女はわたしの第二の母親になってくれたのです。この頃から、父親は上の姉の病気のため、家計のやり繰りに苦労するようになってきました。
G.K.- ともかくも、あなたはパリにやって来て医学を学ぶことになり、精神科を専攻することを望んでいたわけですね。パリに到着したのはいつですか。
A.G.- 1946年です。
G.K.- 終戦直後ですね。
A.G.- エジプト、マルセイユ間を航行するおんぼろ船に乗りマルセイユに着いたのですが、パリに行く列車に乗るのに四日も待たされました。パリには五月八日に着きました。その時のパリは戦勝に沸いている最中でした。
G.K.- 記念日に着いたという訳ですね。
A.G.- そう戦勝記念日でした。しかしパリはその時はまだ戦禍から解放されてはいなかったのです。1946年、そして最初の戦勝記念日でしたが、食べ物を手に入れす術はなく、日用品を調達するには引換券が必要だったのです。だが問題はそういうことではなかったのです。親たちは子どもを養うため奔走していましたから、われわれ留学生は二の次だったのです。われわれにとっては寄る辺なさをかぶるしかなかったのです。エジプトからやって来た身としては彼我の差を思い知らされました。エジプトではみな兄弟同然でしたから。
-p.14-
われわれエジプトのユダヤ人は植民地根性などとは無縁でした。領有などというものにはこだわっていませんでしたから。異国人からすると、植民地支配者に類する最たるものは英国でありパシャ7)でした。英国の場合はコモンウェルスの美語の下に実効支配してきたのですから。一方で、われわれユダヤ系エジプト人留学生はもちろんヨーロッパの教育制度の恩恵にあずかることができたヨーロッパ人でした。限られた者のみの世界に生きていたわけですが侵略者などではありませんでしたから。
G.K.- 大学以外にどのような学校に通っていたのですか。バカロレアについては先ほどお伺いしましたが。
A.G.- 当時、フランスにはあらゆる学校がありました。子どもが英国で暮らし英国の教育を受けることを望んでいる親には英語学校がありました。イタリア語学校もあり、とても良い学校でした。それぞれのコミュニティにそれぞれの病院があったのと同じですね。ギリシャ人にはギリシャの病院があり、イタリア人にはイタリアの病院がありましたから。アメリカ人のための病院もありましたね。学校もそれぞれのコミュニティにそれぞれありました。フランス人向けには、二つのタイプの学校があり、これらはまったく別物でした。一方は宗教色の強い聖マルコ兄弟団8)でした。もう一方は宗教色を排した学校でした。この宗教色を排した学校で学ぶものは真に世界中でもトップ・クラスにあるとの自負をもっていました。われわれは宗教的ではない、であるからフランス人なのであり、フランス共和制精神そのものなのだといった具合にです。
G.K.- あなたはパリにやって来て、ご自身がフランス人だと感じたが一方では無国籍だったのですね。大学にはすんなり入ることができたのですか。
A.G.- バカロレア及第で自動的に大学進学です。今日と変わりません。問題といえば……わたしが幻想を抱いていたことです。フランスに到着したらすぐ、知識人であるヤングたちと接触できると思っていたのです。お判りでしょうが、まったく違いました。サン・ミッシェル大通りに出て、「若き知識人」はどこにいるのだろうかと目を皿のようにして探しましたが、そのような人には巡り会えませんでした。一叢のなかにあって寄る辺なさを感じました。パリの雑踏のなか、薄っぺらい学生の一群ですよ。これとは別にわたし自身の問題としてですが、医学の勉強についてアンビヴァレントな気持ちでいっぱいでした。すぐ精神科医になることを望んでいたのです。ところが精神科患者を診るのには4、5年かかることを知りました。待たなくてはならなかった、耐え忍ぶしかなかった訳です。医学の講義はわたしにとって退屈極まりないものでした。1、2年は怠け者の学生でした。試験勉強もろくろくせずに、自分のしたいように勉強していました。哲学、心理学を勉強していました。つまり文化、教養関連の類の本ばかり読んでいました。医学の学習のためになるものとは程遠いものばかりです。
G.K.- ハンナ・アレントはどこかでジュダイスムjudaismとユダヤ人性jewishnessとを分けて考えるべきだと述べていますよね。かの女によれば、歴史のある時点において重要な変化が起きているのだと。つまりユダヤ人はユダヤ人としてのアイデンティティーをもっていて、おそらくユダヤ人性で結びついている。しかしかれ等はかれ等の宗教、Judaismを失ってしまっていると9)。1946年にパリに来られたとき、あなたがユダヤ人であるというステイトとしての問題がなにかもち上がりませんでしたか。
A.G.- もちろんフランス国内の反ユダヤ主義について、当時も名残を残していることは知っていましたが、それはどの時代でも同じでしたでしょう。但し、この当時は反ユダヤ主義は戦前、戦中と比べると目立ってはいませんでした
7)wikipedia, 「パシャ」参照のこと。
8)wikipedia, 「聖マルコ兄弟団」参照のこと。
9)ハンナ・アレントについては、G.K.氏がここで述べているjudaismとjewishnessとの区別は措くとして、その後のかの女がかなりの変節ぶりを示しているのであるが、この点については、船津 真氏の『アーレントとシオニズム : 二重ネイション国家論者からイスラエル擁護、という「右傾化」の事例に即して』、言語社会2 : 241-256(https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/16493/1/gensha0000202410.pdf)参照のこと。
-p.15-
終戦直後でしたから、強制収容所についてはわれわれユダヤ人は知っていましたし、このことでフランス人もショックを受けていたことはありました。それ以前の自分を振り返って思うと、わたしにとってのユダヤ人としてのアイデンティティーというものは大した問題ではありませんでした。友だち相手がユダヤ人か否かなど意識はしていませんでした。フランスに到着した直後は、同じくエジプトからやって来たユダヤ人の友だちと接触していました。ホテルの部屋をシェアして一緒に生活していたり、あるいは部屋は違っても互いに足繁く訪れたり、時々いっしよに食事をし、お喋りしたりしていました。大学が始まると、そこは人種の坩堝であり、こんなのはわたしにとって初めての体験でした。ユダヤ人もユダヤ系以外の人も一緒にいたのですから。わたしは誰ともうまくやっていこうとする性質たちですが、ある日、ひとりの魅力的な若い女性とめぐり逢い、演劇かなにかそのようなものものに誘いました。ところがかの女はこう言うのでした。「若い男性の方とお付き合いするには両親の許可が必要なの」と。わたしはかの女の両親と会う心の準備はできていたのでまったく問題ないと返答しました。かの女はこう言い返してきました。「そういう訳にはいかないの。だって貴方はユダヤ人だもの」と。これが最初であり最後の体験でした、ユダヤ人だからとして疎外されるような言葉を他人ひとから聞かされたのは。一寸はショックを受けましたが、気を持ち直しました。一変して力づけとなったのは試験コンクール10)に合格したことでした。フランスにおけるコンクールのシステムについてはご存じでしょう…
か
G.K.- 病院等のポストに就くためのコンペティションでしょう…
A.G.- サン・タンヌ病院はパリにおいても特別な場所でした。パリにあるあらゆる病院、一般病院も含めてですが、これらの病院は押し並べて保守的でした。医療従事者は政治的には右派が多く若い医師はブルジョア階級の出で占められていました。しかしサン・タンヌはこれらとはまったく異なるバック・グラウンドと伝統を持っていました。サン・タンヌは精神医学のメッカでしたし、共産主義的ではなかったですが政治的には左派色が強かったです。サン・タンヌの医師は皆知的でした。ご存知でしょうが、病院のサル・ドゥ・ガルドゥ11)には伝統があります。他の病院のサル・ドゥ・ガルドゥの壁画はすべてポルノ、ポルノ以上のものでした。医学上典型的なものでいてポルノだったのです。サン・タンヌ病院の壁画はこれらとは異なるものでした。壁いっぱいにシュール・レアリストの画家たちによって描かれた壁画があったのです。巷で流れている卑猥な歌詞とは異なっていました。精神医学とシュール・レアリストのテーマが融合するようにとの試みが窺えるものでした。しかもこの壁画は極めて質の高いものでした。例えば、オスカル・ドミンゲス、ジャック・エロルド、モーリス・アンリをはじめ錚々たるシュール・レアリスト画家によって壁画は描かれていたのでした。残念なことに、後にこの部屋と壁画は取り壊されました。われわれインターンは他の建物に移動しなくてはならなくなったからです。旧サルドゥ・ガルドゥでは4年間過ごしましたが、この4年間はわれわれインターンにとっては実に刺激的な時間でしたし、われわれはこの時間に誇りをもつことができました。政治的に左派であったという事実は一面に過ぎません。われわれの立ち位置は、知的活動の面では革命的であり、一方でシュール・レアリスムに立脚していましたし、他にもいろいろありました。反ユダヤ主義などサン・タンヌでは問題外でした。アンリ・エーの奥さんはユダヤ人でした。ラカンの妻12)もそうでした。同様の例は事欠かないぐらい多いです。ユダヤ人か否かでなにか言われることがまったくなかったとは言いませんが。
10)周知のように、examen(s)は及第点に達していれば合格でありconcoursは獲得した点数上位何人かが入学、入賞の対象となるものである。
サン・タンヌ病院に限らず、由緒あるフランスの病院のいくつかにはインターンのくつろぎの間がありこれがsalle de gardesと呼ばれてきた。これは僧院で寄食等を施す部屋が由来とされていて、これらの病院のsalles de gardesには必ずといって壁に卑猥なフレスコの壁画が描かれており、インターンたちはここで共同で食事をするのであるが、その際専門の医学についての話題について語り合うことがルールとなっていた。一般人でもインターン同伴で寄職を許される場合があり、最近は観光目的でsalles de gardesが公開されることもある。
グリーンの宿敵であるラカンが若き頃サン・タンヌ病院のsalle de gardeにいるところを写した写真を載せる。ラカンの娘であるJudith MillerのAlbum Jacques Lacan : Visages de mon père (Champ freudien)には、グリーンはどう言おうが、卑猥極まりない壁画が写っている写真が載せられているが、著作権を独占するMillerの嫁だけあり、これをここで示すことは断念した。
12)後妻であるSylvia Batailleの方である。
-p.16-
わたしの先妻はユダヤ人ではありませんでした。かの女の父親の家系は正教信者でしたし、母親の家系はカトリック信者でした。わたしの子どもたちにには宗教的な教育をまったくしてきませんでした。で、わたしにとってのユダヤ性Jewishnessはなにかというと、これですかね。1948年に第一次中東戦争が勃発し、エジプトとイスラエルとのあいだでの戦いになりました13)。わたしの心はこれに反応しました。わたしはイスラエルが心配でしたし、気が気ではありませんんでした。この国がこれを囲むアラブ諸国を敵に回し大丈夫なのかと思い煩いました…われわれ信仰をもたないユダヤ人にとってはそうだったのです。信仰をもたないユダヤ人とはユダヤ人が威嚇を受け、迫害され、あるいはどこかでなにかが起こるまでユダヤ人であることすら忘れているのです。それでいて一方でわれわれは、イスラエルの戦争政策には断じて承認はしないのです。
G.K.- その後ですが、ラカンとの接触することになりますよね。その時のことを教えてください。フランスでではないのですが、何人かのラカニアンから聞いた話ですが、意外だと思ったことなんですが、敢えてお訊きします、かれに反ユダヤ主義的傾向があったようなことを仄めかされましたが。
A.G.- ラカンが?まったくそのようなことはありません。逆です。ラカンは苦しんでいました…ユダヤ人でないことをね。もちろんこれはジョークですけど。かれを取り巻く状況は厄介でした。しかしわたしがこう言うのも一理あるのです。わたしの書いたものですが、とはいえ、わたしひとりが目撃者だなんて言うつもりはありませんが、わたしはこう書きました。ラカンの精神分析は精神分析のキリスト教的ヴァージョンです。しかしこのことについてラカン自身からはひとことも聞いたことはありません。国際精神分析協会の会員でかれの同僚でもあったひと達とのいざこざに巻き込まれているときの噂話はいろいろ出回っていますが、その当時かれはなにか言っていたかもしれません。しかしわたし個人に限っていえば、ラカンから反ユダヤ色のある発言を聞いたことなどありません。わたしのキャリアはそもそもかれとは違ったものでした、というのも、わたしはフランス風知識人層には属してはいなかったのでしたから、そうであってもサン・タンヌ病院での研鑽という特権にあずかることができていたのです。サン・タンヌを討論、論争、出会いそして会合の活力溢れる場だったのです。圧倒的なダイナミスムのある教育機関だったのです。
G.K.- 当時どのような精神科医がいたのですか。重鎮といえるひと達を教えてください。
A.G.- 当初わたしを含めて何人かはパリにいませんでしたので、事情はつかめませんでした。俯瞰図ともいえるものをいくつか示しましょう。1953年、わたしはコンクールに合格しました。最初の一年はパリから40キロメートル離れた精神病院に派遣されました。劣悪な環境でした。わたしは一年で見切りをつけ、すぐさまサン・タンヌ病院に戻ったのです。サン・タンヌはモーズレイと肩を並べる病院です。サン・タンヌ病院は若い求学心のある精神科医にとっては稀有の場所でした。アンリ・エーはフランス国内だけでなくおそらく世界的にも精神医学における大御所であったことは衆目の一致するところでした。かれが勤務していたのはサン・タンヌではありませんでした。パリから130キロ・メートル離れた場所でシャルトルの近くです14)。エーのことを聞いたことありますか。
G.K.- ありますよ。精神医学の教科書として精神医学マニュエルを使って勉強していましたから。この教科書はポール・ベルナールとシャルル・ブリセとの共著でしたね。心理学の授業でこの教科書を用いていたのです。ですので、わたしの受講していた心理学はアルゼンチンでも極めてユニークなものだったのです。フランス・システムの精神科分類を学んだのですから。
13)厳密に言えば、イスラエルとアラブ連盟(当時)五カ国(レバノン、シリア、トランスヨルダン、イラク、エジプト)との戦いであった。
14)Bonneval病院、現在の名称はCentre Hospitalier Henri Ey(Bonnevel)で実際はパリの西南西90キロ・メートルに位置する。Eure-et-Loir県にあり、この県の県庁所在地がシャルトルである。
-p.17-
A.G.-ところで、わたしはアンリ・エーの.お気に入りの生徒だったといえます。かれが退官する際、以後もかれの講義を引き続け受講したいかどうかわたしに訊きいてきました。しばらくは受講を続けましたが、その後は止めてしまいました。こう自問したのです。正直いって、自分は精神科医なんかではないではないか、と。日に日にわたしは精神分析家になっていきました。精神医学を教える資格など自分にはない、今の自分はほうとうの自分ではない、と当時も思っていましたし、今も同じで、わたしではないものを気取る気はさらさらありません。エーのキャリアについて話を戻します。まずはサン・タンヌのレジデントになったのが第一歩で、1920年代でした。1926年にレジデントの研修を終えます。かれはラカン一派と仲が良かったですし、わたしの師ののひとりとも好友関係にありました。国外では知名度は低いですが、ピエール・マール15)です。児童精神医学の重鎮でした。1953年の分裂16)以後、マールとラカンは別々の協会に所属することとなり、顔を合わせることもなくなりました。マールはナシュトの陣営にあり、一方、ラカンとエーとの交友関係はその後も終生変わらず続きました。パリ精神分析協会が設立されたのは1927年でした。暫くして、ご承知でしょうがリュディ・レーヴェンシュタイン17)がパリにやって来ます。次いでハルトマンが続きます。レーヴェンシュタインはフランスに居を構え、後に名を馳せる四人の分析家の分析に関わります。ナシュト、ラカン、ラガーシュそしてマールです。エーはというと、新しい精神医学の構築を目指しました。かれが心に描いていた展望においては、この新しい精神医学に、精神分析も含めること、現象学派さらに生物学的新知識も、と壮大なものでした。ラカンは金蘭の友でもありライヴァルでもありました。エーの影響力とは純粋にかれ自身の学に対する真摯な態度から発するものでした。というのも、かれは大学における精神医学の教授ではなかったのですから。かれは決まって毎週パリに出て来て其かを教え、そしてかれの僧院18)に帰る、これを繰り返していました。皆エーになにかを学ぶために会いに行き、それ以外のものをかれから期待はしていなかったのです。ラカンはどうかというと、これとは違いました。かれはひとを蜘蛛の巣にかける式に自分の方に引き寄せることを計算していました。かれ等の分析に関わり、そうすれば自分の弟子にすることができる、蠱惑で落とし、最後には自分の信者にする、でした。
G.K.- アンリ・エーは断じて精神分析家にはなるまいといったスタンスをとっていましたよね。そうではなく、ラカンがフランス式精神分析の定着を目指したのと同様、フランス式精神医学を掲げこれをライフ・ワークとしようとしていたのでしょう。精神分析はエーにとっていわば脚注みたいなものだったのではないでしょうか。かれのマニュエルでみたいに…
A.G.-脚注では収まらないものがあります。論争的なところがあるんですよ。かれの立ち位置とはこうです。「そう、結構ではないですか。もちろん『無意識的』と呼ぶことができるなにかは存在します。しかしもっと重要なことがあるのです。良心(= 意識)19)ですよ」と。かれは良心は抑圧し無意識をコントロールするものだとしているのです。つまり、無意識が意識にも根付いてしまうと病気へと発展するという訳です。かれは良心の優位を疑いませんでした。その上で、精神医学をこう名づけたのです。精神医学がかれによってこう名づけられたことについて、これからのわたしの説明で合点がゆくものと思っています。かれは精神医学を「自由の病理」と名づけたのです。心的な健康を保っているということは自由である可能性をもつことなのだと。もし無意識がひとに根付いてしまったなら、誰でも自由の病理をもつことになると。その場合各人がしかじかの葛藤を抱えることになる等々、と説いています。これに続いて、かれはここに生物学的病因を混ぜてゆくのです。かれの奇妙奇天烈な理論「器質力動」論はこのように展開されるのです。「器質」は根底に生物学的なものが病因となっていることが想定されているのですし、「力動論」であるのは、心的生命の力動が関係しているからとのことなのです。かれは精神医学の教皇でした。
15)原文はPierre Maleとなっているが、正しくはPierre Mâleである。
16)https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_française_de_psychanalyse参照のこと。
17)原文ではRudy Lowensteinとなっているが、正しくはRudy LoewensteinあるいはRudy Löwenstein。Rudyは愛称であり、本名はRucolf、フランス人はリュディ・レーヴェンステェンと発音する。ドイツ語でレーヴェンシュタインで(元々はポーランド出身)で通っているのでこれに従った。
18)son abbayeとあるが、ボンヌヴァルの精神病棟はAbbaye Notre-Dame de Bonnevalの建物を改修して建て直されたものであり、僧院という言葉からして、エーにとっては英語でいうSacred places makes you feel peaceful and calmということだったのであろう。
19)原文はconsciencenessとなっているが、フランス語ではla conscienceであり、フランス人はla conscienceという語を、この語がもつ語義、良心= 意識(分析用語としては「意識」は一般的にはle conscientではあるがしばしばla conscienceも使われる)という両義性(もちろん意識が良心というものを内包しているとは考えることはできるが、このような考え方自体が優れて精神分析的と言える)を「無意識的」にくるめて用いることが多い。因みにエーは“La conscience”というタイトルの本を上梓している - PUF(1963)、後にDesclée de Brouver(1968-)に版元が変わっている。邦訳もあり、訳者である大橋博司氏の日本語タイトルは「意識」である。ここでは原文=英文consciencenessを尊重して、初出では良心(= 意識)としたが、以降は「良心」で通す。
-p.18-
フランスの精神医学界では伝統的に、年に一度、ある行事が催されます。この行事とは、親分たちの晩餐会と戯れて名づけられた催しで、この会にはフランス国内にある主要な病院の病棟長、精神科主任医長が招聘され、かれ等を見てレジデントは失笑します。レジデントたちはこの物真似もするのです。悪乗りして興ずるのです。これも年一回でした。わたしがアンリ教皇を演じる羽目になったこともありましたよ。実際そうでした。かれは精神医学界の教皇だったのです。なにしろエーは並外れた活力と学識をもち合わせたひとでしたから。エーはしばしば本源的で重要な演題のもとに会合を開催しています。例えば、1947年は精神病と神経症の心因論についてといった演題でした。ラカンはこの演題の下に含蓄のある発表をしています。
G.K.- ボンヌヴァルでのコロックのことですね。ラカンが発表したのは「心的病因論について」というタイトルで…
A.G.-その通りです。シャルトルの近くで、パリから130キロ・メートルのところで、われわれはそこに一週間滞在しました。もともと僧院だったのを病院に改築した場所でです。
G.K.- 最後のボンヌヴァルのコロック、「無意識について」で初めて貴方のお名前を知りました。あなたの発表は「無意識と精神病理」でしたでしょう。この発表の前に会誌の会頭挨拶のため「無意識への入り口のドア」を書いていらっしゃるでしょう。
A.G.-仰言るとおりです。
G.K.- いずれにしても、エーは重鎮でありながら温厚な方で…
A.G.-かれは子宝に恵まれなくて、だからわれわれはみなかれの子供たちだったのです。わたしにとっては、実の父親は別として、かれはただひとり真の父親像として見ることができた人です。ラカンは父親的ではありませんでした。魅力ある男でしたし、わたしもかれには引きつけられました。だがかれに父親像を見いだすことはできませんでした。陰ながらですが、ビオンも父親像に重なっていましたがラカンは違いました。われわれはアンリに深い愛着を感じていました。なぜならば、かれはわれわれにも敬意をもって接してくれたからです。どんなにできの悪いレジデントが、エーに対して手を挙げ、「わたしはあなたの言っていることに納得できない、理由はあれこれで」とまくし立てるとしても、アンリはかれの言葉に耳を傾け、それに答えるのでした。かれは、同じような地位に就いているの他のひとと比べると、やはりご多分に洩れず癇癪持ちでした。しかしながら、かれはひととひととの交流というものを最重視していました…但し、何人かは言っているかもしれません、ラカ二アンと非ラカ二アンが論争ゲームをしているとすると、このゲームをあらぬ方向に捻じ曲げるようなことをしていたと。だが本当は違います。かれは討論を好んでいましたししばしば論争となるような論題を提供していました。もしラカ二アンと非ラカ二アンが論争するような機会があれば、かれはこれを利用することはあったでしょう。論争することがなにより重要だったのです。
G.K.-知識人のあいだでの論争、知識人たちの世界ミリュウがもたらす影響、そして哲学、人間諸科学、こうしたものがフランスにおいては常に重要だったですからね。
A.G.-ですが、他の国ではそのようなものがなかったかというとそれは誤りです。ドイツの例があるでしょう。もちろん英国の分析家に失礼な言い方はしたくないですが、ヨーロッパの精神医学史を紐解くと、フランスの精神科医とドイツの精神科医の巨人がしのぎを削ってきたというのは正しいででしょう。かれ等のあいだでは常に相手側を曖昧だとか厳密性に欠けるだとか非難するところがありますが、出発点からして共通するものがありました。両国とも、19世紀の精神医学の古典に当たる時代の学者たちが同じアイデアに基づいて論述していたというところでです。哲学的なバック・グランウンドがあったことと精神疾患がまずあり、これを基にして理論を築き上げたことです。ピネルは精神病患者を鎖から解放した偉大な精神科医で、精神病医学-哲学提要トゥレテ・メディコフィロゾフィーク・ドゥ・ラリエナスィオン・マンタールを著しています。哲学がバック・グラウンドにあることは、両国の精神医学者に通底しているのです。
-p.19-
精神医学が「積極的に」なったことでこのような変化が生まれたのです。それより昔は、精神科医はほとんどなにもしませんでした。当時は二つのタイプの精神科医がいました。まったくなにもしない精神科医がいた一方、努めて思考し、記述し、観察していった精神科医がいたのです。観察といっても、これはまだ精神病患者の博物学的観察にすぎません。そして哲学的結論といっても脳の研究から導かれたものでした。当時既に統計と精神科の疾病分類の走りみたいなものがあったんです。まとまりがありしっかりとした分類が出来上がるまで数世紀かかったわけですが、われわが手にとって見ることのできる分類の雛形をそこに窺うことができるのです。わたしにとって精神医学の勉強の最初の数年はこれらの著作を読むことでした。これら古典に書かれている著者の観察眼の鋭さには感嘆させられます。ありとあらゆる治療法が書かれていました。ある治療はサディスティックといっていい様なものであり、一方で人道的なものもありました。何れにせよ、精神医学史は興味の尽きない学科です。アンリ・エーが教壇に立つとき、講義は精神医学史と哲学的問題意識といったふたつのヴィジョンを統合させたようなものでした。そこにはふたつの学問領域の相互作用といったものがありました。あの頃はサルトルの影響が大きかったですね。かれの弁証法的理性批判は無意識についてのボンヌヴァルでのコロックの直前に上梓されました。サルトルはそのとき絶頂期でした。メルロ=ポンティも重きをなしてきたところで、特に哲学と精神分析との接点という面でそうでした。かれの妻、スュザンヌはラカンとの分析を終え、かの女自身分析家をしていましたしラカン派でした。メルロ=ポンティはソルボンヌで教鞭をとっていました。パリで教職を得ることはかれのたっての望みだったのです。それ以前はストラスブール大学の教授に任命されていたと記憶していますが、ソルボンヌではひとつの教授職、児童心理学の教授職のみ得ただけであり、この方面における知識はお粗末なものだったのですが引き受けたのです。ところで、かれは一度限りですが、アンナ・フロイトとメラニー・クラインを比較するという極めて興味深いセミネールを行なっています。ソルボンヌでこのような講義が行われたのは初めてことでした。ラガーシュもこのセミネールに参加していました。メルロ=ポンティは1951年にはソシュールについての講義も行なっています。ラカン以前にです。かれがソシュールに着目するよう導いてくれたのです。レヴィ=ストロース、ポール・リクールといった面々もこの講義に参加していました。
G.K.- ラガーシュについて話が及びました。ラガーシュも重要かつ影響力のある分析家でしたが、わたしの目からするとフランス精神分析界においては異色の人に映るんですが。
A.G.-そうですね。かれをどこに位置づけたらいいのか。ラガーシュは高等師範学校エコール・ノルマル・スューペリュール出です。ソルボンヌでは心理学の教授をしていました。精神科医でしたが、精神医学にあまり興味を示しませんでした。ソルボンヌで精神病理学を教えたいがために、必修である精神科の臨床的なトレーニングを受ける人がいますが、かれもその口です。かれはそつなくこなしていましたがその後精神分析家になったのです。かれの本業は教職でした。かれが担当していた講座は心理学、精神病理学そして社会心理学でした。かれとナシュトとのあいだでの確執はかなりのものでした。最初の分裂の際ラガーシュは渦中の人となりました。1953年までは精神分析養成のための機関というものは存在せず、協会だけがあったのです。協会には分析養成委員会はありました。ちょうど貴方の所属する英国の協会の委員会と同じようなものでした。
-p.20-
1953に精神分析学院ランスティテュートゥ・ドゥ・プスィカナリーズが誕生します。学院は養成のためのあらゆる問題を担っていながら協会からは独立した機関だったのです。ラガーシュは、ソルボンヌ大の教授として、学院の創設のための牽引者として適役だあると自認していました。しかしナシュトはこれを阻もうとしていたのです。ナシュトは心中、医学部の精神分析学の教授職を狙っていました。このような野心は教授陣の側から見ると常軌を逸したものに映っていたはずです。しかしながらなかには、ナシュトを学院の長に推す連中もいました。ルボヴィッをはじめ相当数の人がいました。こうしてラガーシュとナシュトはぶつかり合いました。茶番に過ぎませんでしたけども。最後にはラガーシュは断念しました。とはいえ、ラガーシュが行くところは、誰もがかれについて行きました。かれの大学でのキャリアがものを言うからで、かれを頼ってでした。ラカンとラガーシュは新しい協会を設立し、1953年から1963年にかけての10年間は協力関係にありました。ラカンの短いセッションをめぐる国際精神分析協会とラカンとの諍いが問題化し始めたとき、リュビィ・レーベンシュタインは、ラガーッシュに好意的でかれの才覚を高く評価していました。ハルトマンもかれの著作に一目置いていました。ラガーシュを読んでいただければ、そこにはハルトマン色を見いだすことができますよ。かれら二人は苦渋の選択を迫られました。いかにラガーシュを擁護し、そしてラカンを排斥するかです。この問題を解決するのには少なくとも5、6年はかかりました。解決は第二の分裂でなされたのです。パリ精神分析協会分裂後の協会には指導分析家やスーパーヴィジョンを行う分析家の数は多くはなく、ほとんどの分析家志望者はラカンの下で分析を行うか、ラガーシュのスーパーヴィジョンに頼ったのです。
G.K.- 貴方が分析家になられたのはいつですか。
A.G.-1953年、コンクールをパスしてそれからの三年は精神分析に抵抗がありました。当時研究対象として目指していたのは生物学的精神医学でした。わが師はアンリ・エーと、その名をお聞きになったことがありますでしょうか、アジュリアゲッラです。かれは神経科医であり精神科医でもあり、小児の発達の専門家でした。わたしはかれのお気に入りの生徒でもあったのです。かれが言ってくれたのです。君ははどうみても分析をやったほうがいいなと。正直なところ、わたしは極めて短気な性質たちでして、この年になってなんとか自分をコントロールできるようになり、少しはましになったのではないでしょうか。そんな訳で1956年には分析を始めました。四年かかりました。モーリス・ブーヴェの下ででした。かれはパリ協会で最も秀でた分析家のひとりでした。パリ協会で最高権威者といえばナシュトでありナンバー・ツーがブーヴェでした。因にブーヴェはパリ協会を離れるかどうか躊躇していたのですが、結局ナシュトの下に留まることを決意したのです。わたしの分析は1956年から1960年にかけてでした。最後にわたしの分析家に会ったのが最後のセッションでした。逝去されたのです。
G.K.- それが最後のセッションだったとは。かれが病気だと知らされていなかったのですか。
A.G.-他の皆は知っていました。わたしだけが知らぬままだったのです。転移のなせる技なのでは…
G.K.- そのように分析がスタートしたのですね。しかしそのときは意を決してというわでではなかったのですね。
-p.21-
A.G.- そうなんですよ。最初の3年間は精神医学を必死になって勉強しました。精神医学だででなく神経学もそうなんですけど、学びながら一種の文化、教養上の基礎を身につけることができたのです。これはアジュリアゲッラから教わったもののです。サン・タンヌは実に多くの機会を提供してくれました。精神分析家はその当時から大きな影響力があり、わたしはかれ等のセッションに立ち会うのを許されていたのです。そのなかにラカンも含まれていました。かれが分析をどのように進めてゆくのか知るることもできました。それぞれの精神分析家が独自の方法でアプローチを行い。精神分析学がひとつだけではないことをを実感しました。もちろん皆それぞれが講義を行っていましたし、それ等をは欠かさず受講していました。次第に精神分析に引き込まれていったのですが、そんななかラカンはわたしに対する誘惑のゲームを買って出るようになったのです。ロゾラートとは昔から親友でしたし、かれはラカンの下で分析をしていました。機会を逃さずロゾラートを通して、かれはわたしと交流するようになりました。ある日、ラカンはかれの発表した論文の別冊をロゾラートに持たせ、わたしに手渡すよう仕向けました。1958年、バルセロナで精神療法に関する大会が開催され、エーとラカンが出席していました。わたしは当地でラカンと会いました。するとラカンはホテルで一杯やろうというので、わたしはロゾラートを連れて行きました。二時間というもの、ラカンは強引でした。「なぜわたしと一緒に来ないのか。君は僕の右腕となるべきだ」と。わたしはこう切り返しました。「執筆されたものは大変興味深いものですが、わたしにとって必要なのは、わたしの職業上でのことについて教えてくれる人たちです。バランスの問題として、もしわたしが貴方をこちら側に位置づけるとしたら、他の方たちは別の側からわたしを教えていただくことになりますが…そうするとバランスはあっちの方に傾くことになりますよ」。かれは相手が六人束になれば、自分が重さでは太刀打ちできないことで激怒しました。ところで、ロゾラートはその場にいたのです。かれはラカンの下で分析を続けていたのですよ…ラカンはですね、かれは我欲の塊みたいな人間だったのです。皆はそう思っていないようですけど。ロゾラートがそこにいるのに、まったくの無視ですから。ラカンがロゾラートを爪弾きにしたことで、当然ロゾラートの心にはは嫉妬、怨恨、その他のありとあらゆる悪感情が煮えたぐっていたでしょう。ロゾラートが受けた仕打ちをもしわたしが受けたとしたら、やはりかれと同じ感情からは逃れることはできなかったでしょう。
G.K.- 一歩身を退いて見ると、魅力があるのとは別なものがあったのでは、精神病質的なものが…
A.G.- まさにその通りです。ラカンを知らないでかれの行動を見たひとはそうは思えないと言うかもしれませんが。確かにかれには惹きつける力がありました。かれの知性は並外れていましたた。その上で他人に対して思いやりがある態度を示すことだってできたはずです。かれは御し難い性格のもち主でしたが、これが非常に見えにくいのも確かで、皆そういう目で見たくないと思っていたのです。「他のひとに対して通ずる尺度ではかれを評価してはならない。なにせかれは天才なのだから」ということでしょうか。
G.K.- ロゾラートは今どうしているんでしょうか。
A.G.- フランス精神分析協会アソスィアスォン・プスィカナリティーク・ドゥ・ラ・フランス(A.F.P.)の極めて影響力のある四人のうちのひとりです。
G.K.- かれの書いたもので非常に示唆に富んでいるのを読んだことがあります。記憶から離れません。「うつ病の軸となるナルシシスム的なもの」についてのものです。
A.G.- そう、優れた論文のひとつです。この論文が書かれた時期はわれわれにとって重要な時期、1970年から1972年にかけてです。精神分析新雑誌ヌーヴェル・ルヴュー・ドゥ・ラ・プスィカナリーズが刊行されていた時期にあたります。
-p.21-
当時、ポンタリスは精神分析新雑誌ヌーヴェル・ルヴュ・ドゥ・プスィカナリーズの創刊に踏み切り、共同執筆者としてフランス協会アソスィアスィオン(はラカンとラガーシュが名を重ねていたフランス協会ソシィエテの消滅後にこれを改称して設立となった)の会員に協力を求めた。本協会は独立を保ちつつ今も存続しています。わたしは1972年、協会の編集委員となりました。われわれにとってこうした動向はフランスの精神分析の歴史におけるランド・マークとなっています。なぜならば、これをもってわれわれはラカンから解放されたからです。われわれは英国の分析家に遭逢できたのです。マズュード・カーンが英文論文の編集者を務めています。わたし自身の業績についてですが、誤解していたことがあります。わたしには、ラカ二アン時代とその後の英国時代があったと認識していました。しかし時系列でいうと、この認識は誤りがありました。1961年、わたしはラカンのセミネールの聴講者となりました。ところがちょうど同年、昔はエジンバラ大会と呼ばれていたロンドン大会のプレコングレスに参加していたのです。そのとき今日では錚々たる顔ぶれとなっている分析家と出会っているのです。例えば、ウィニコット、ジョン・クローバーそしてハーバート・ローゼンフェルド等で、かれらセミナーを聴講していたのです。わたしなりの選択であり、これは良い選択でした。わたしの経験したものに類似した事象についての教えを受けたときの感慨を今も忘れません。眼から鱗が落ちたようでした。目新しいなにかを教わることができたとも感じました。わたしの分析に対する考え方において、英国の影響はラカンからの影響と並行していたのです。ラカンは毎週、英国は6ヶ月に一度という違いはありましたが。
G.K.-情動についての本を書かれたのはいつですか。何年のときですか。
A.G.- 1970年です。しかしこれを一冊の本にしようとは当時思っていませんでした。ご存知のようにパリ協会(S.P.P.)は特別な何某かがありますでしょう。ロマンス語圏精神分析家大会コングレ・デ・プスィカナリスト・ドゥ・ラング・ロマーヌ20)が大会の名称ですから。このイヴェントでのリポーターは大会側が選任するのです。フランス語でリポーターズ(仏語 : rapporteurs)は英語のリポーターズとは意味が違います。リポーターたちはまず論文rapportを書き、長いものですと150ページに及ぶものも出てくるので、これが参考文献として扱われ、ときにはモノグラフとなる場合もあります。なんらかの問題にぶつかり、疑問があり、このことを調べたいと思ったら、参考文献図書で当該する主題を検索すると、このリポートが出てきます。もし記述が納得できないものであっても、それはそれで、この情報は利用できるものであり、参考文献となり得るのです。ということでわたしは書きました。リポート以上のものです。300ページもあったのではないでしょうか。最初はタイトルとしてラフェクト(L’Affect)にしました。お話ししたように、1967年、わたしはラカンと喧嘩をし、かれとの関係を完全に絶ちました。7年間にわたる交友関係の後の決裂です。なにかを書こうと思っていました。1960年のボンヌヴァルでの無意識について前掲)、ラプランシュとルクレールが提出した論文21)をめぐる討論として、頭のなかでは出来上がっていたものがあり、これを書こうとしたのです。因みにラカンはふたりの共著であるこの報告を読んで烈火のごとく怒りました。かれはこの報告を‹唾棄すべきものラブジェクト(l’abject)›とまで扱き下ろしました。わたしが書こうとしていた本の主題から、ラカン批判であることをラカン自身見抜いていました。三年かけて、わたしのリポートは一冊の本に生まれ変わったのですが、タイトルだけは変えました。より読書欲に訴えるタイトル、生きたディスクールル・ディスクール・ヴィヴァン(Le discours vivant)22)と。
20)パリ精神分析協会(S.P.P.)の設立は1926年である。当初の大会名はConférence des psychanalystes de langue françaiseであったが、大会事務局は、フランス国外(ヨーロッパ域内フランス語圏諸国及びフランス語圏カナダ)の会員も増加していることを鑑み、1956年、大会の名称をCongrès des Psychanalystes de Banques Romanesと改称したが、同時通訳が取り入られるようにり、フランス語圏以外の国の会員の増加により、大会執行部委員の大多数の意見に基づき、1997年バルセロナ大会より、旧称のConférence des psychanalystes de langue françaiseに戻った。
21)1960年、ボンウヴァルのコロークで発表され、翌年、レ・タン・モデルヌ誌に、この発表の第III部と第V部がL’inconscient, une étude psychanalytiqueとのタイトルで掲載される。本論文はその論理的帰結が「言語は無意識の効果である」となり「無意識は言語の効果」と主張するラカンに真っ向から異論をぶつけたことになってしまった。
22)Le Discours Vivant, puf, 1973.
-p.22-
G.K.- わたしが記憶しているかぎりでは、アルゼンチンででしたね。その頃はまだアルゼンチンに住んでいました。因にロンドンにやって来たのは1970年のことです。びっくりしましたよ。皆が口々に貴方がラカンと喧嘩別れをしたと言っているのを聞いてです。当時はパリでなにが起きているのか詳しい情報を得ることが難しかったですし…
A.G.-アルゼンチンでということでも、バランジェはフランス人ですよ。かれはフランス人分析家との関係を保ち続けていました。
1
Bref historique
Son appellation a évolué au fil des ans depuis ses débuts en 1926 sous la dénomination de Conférence des psychanalystes de langue française.Avec la participation de collègues étrangers francophones et l’introduction progressive de sociétés européennes et canadienne aux côtés de la SPP dans la composition de son bureau, il a pris en 1956 le nom de Congrès des psychanalystes de langues romanes. Puis il s’est avéré que les analystes étrangers communiquaient de plus en plus dans leur propre langue, les premiers d’entre eux à rejoindre le congrès avaient souvent fait leur formation dans un pays francophone.Aussi s’est il dénommé Congrès des psychanalystes de langue française en 1979, des pays romans s’y ajoutant en 1985.
D’intéressantes tentatives de traduction simultanées furent faites, mais leur qualité fut inégale et elles ont pesé d’un certain poids sur le coût du congrès. Le français restait la langue essentielle. Il fallait en prendre acte. Après avoir réuni en 1997 à Barcelone les présidents de la plupart des sociétés composantes, il a été décidé de reprendre dorénavant le nom de Congrès des psychanalystes de langue française.
『アンドレ・グリーンとの対話 - 精神分析の緑化運動』ついて
The Dead Mother - The Work of André Green, edited by Gregorio Kohon, Rutledge, London所収のThe greening of psychoanalysisと題された編集者であるGregorio Kohonとの対話の冒頭の約3分の1に当たる。Greenは対話を好み、この対話中にも紹介されているMracel Maciasとの対話(Conversation)、Maurice Corcosとの対話(Entretien)の他にも小生の友人であるVincent Fortéの従兄弟にあたるPatrick Frotéの対話集にも登場する(Cent ans après - Entretiens avec Patrick Fort, Gallimard, 1998)。小生も一度モントリオールにあるPatrick Froté宅を訪れ、フランスから一時帰国している夫妻と談笑した経験があるが、当時の小生はLacanしか眼中になく、Patrick FrotéからのLacan以外のフランス語圏分析家についての貴重な情報については裏覚え程度しか記憶がない。PatrickはVincent同様スイス生まれながらカナダへ移住、モントリオール大学で心理学の博士号を取得し、パリ第VII大のJean Laplancheグループ内のJacques Andréの指導の下、博士後の研究として、フランス精神分析シーンの様々の変容(ルビ=トランスフォルマシオン)に参画し、André Green以外もJean-Luc Donnet, Jean Laplanche, Jean-Claude Lava, Joyce McDougall, Michel de M’Uzan, J.-B. Ponytails, Jean-Paul Valabrega, Daniel Widlöherといった錚々たる面々との対話(そしてこの対話のための準備としてPatrickはかれ等の著作を通読しており、この準備そのものがかれの研究対象となっていた)を通じてそれぞれの対話が対話の主体であるそれぞれの二人の分析家に影響を与え、これが当のフランス精神分析シーンの変容に一役買っているわけである。小生は今になって、同僚=同志(ルビ=タヴァーリシ)であるイリーナの影響もあり、André Greenを読むようになってきているのだが、このPatrick Frotéとの対話(ここではPatrickが問題提起を行い、それ等の問題に対してAndré Greenがほぼ語る主体でPatrickはその聞き役に徹しているのだが、これ等提起された問題が壺を押さえているため意義深い話がGreenから引き出されている)についても折あれば試訳を試みたいと思っている。
このThe greening of psychoanalysisであるが、編集がややぞんざいであり、注のために本文に数字が振られているのだが、肝心の注に当たる文が欠落している。フランス語訳Essais sur la Mère morte et l’œuvre d’André Green(Ithaque, 2009)ではこの対話の副題としてLe regain de la psychanalyse(ibid., pp. 31 - 95)が採られており、こちらにはそれぞれの番号に注が記されているので、この部分は原注として訳し、さらに訳注を加え、これ等を読んでいただければ、解題は必要ないものにしたつもりである。イリーナとは小生の作業である邦訳と同時進行になるが、原文(英文)からロシア語訳を進めており、しばしば意見交換をしているので、これは共同作業ともなっている。かの女は近々かの女自身のHPをアップする予定であり、そこにロシア語役(こちらは小生の邦訳より先を行っている)を載せることとなっているが、ロシア人の近々は日本人の近々とは異なることをここで理っておく。