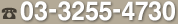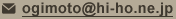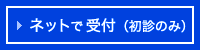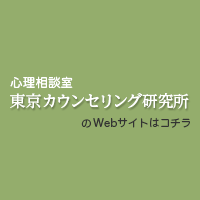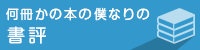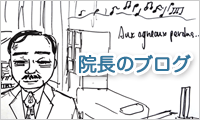|
ジャック・ラカン
 |
 La topologie et le temps 15/5/1979 gaogao ラカン : 今日は、ナジオとジャン=ミシェル・ヴァプロの対話になります。 ナジオ : この演壇に立つと感じるのですが、当然ですが、みなさんはラカンのセミネールの聴講者であられるので、どうかお手柔らかに、と願う次第です。というのも、昨日,月曜日の昼、ラカン氏は、わたしにここで話しをしてくれと頼んだのです。わたしがかれの理論をもとに問題を立て、それをみんなに語ってくれというのです。昨日の今日ですよ。問題の内容とは、無意識の主体の理論に関するものです。わたしのスピーチにタイトルをつけなければならないとすると、こう書くことになりましょうか、すなわち『精神分析に魅せられた子供』です。わたしの年初の目標は、無意識の知と解釈との結びつきを調べよう、といったものだったのです。理解が深まるにつれ、主体の問題が頭をもたげ、いちばんの問題となっていったのです。今朝は、はなしを簡単に絞って、主体の概念についての可能なアプローチについて、みなさんに再確認していただこうかと思います。この主題のアプローチは、みなさん方のほとんどにとってお馴染みのものでしょう。みなさんにお任せしますので、これから述べる疑問点について考えてください。 わたしがまとめたものは三つの部分から成ります。すなわち、主体と無意識の知との関係、主体とフレーゲの論理学との関係、最後に主体と去勢との関係です。 I - われわれの出発点は精神分析そのものの出発点であり、精神分析とは、言語が次のように言い表されることに拠って出来ているのです。すなわち「わたしは、わたしが言うことを知らない」といった言表です。ヒステリー者の欲望が転移を生み出したものだとすると、この「わたしは、わたしが言うことを知らない」は、フロイトの無意識の概念を生み出したものであり、ラカンにおける知としての無意識の概念を生み出したものということになります。 ほかにも「わたしは、わたしが言うことを知らない」の道理があります。なぜならば、自分のditを発する主体は、断じてそうですが、ditを発する主体とメッセージやditを受けとる主体とは別ものだからです。われわれはつねに同じわれわれではありません。言うdireという行為において、わたしは変るからです。「シニフィアンの効果である主体」という表現は、まさに、主体は、言うdireという行為とともに変化するという意味です。 端的に言って、わたしはなにを知らないのでしょうか。(原文に読み取り不能と書かれている) 2. わたしを支配下におくシニフィアンがどれなのか知らないので、わたしは、同様に、そのシニフィアンがさし向けられる他のシニフィアンについても無知なままです。言い換えれば、わたしは、言いながら、どのシニフィアンがわたしを待ち受けているのか知りません。 3. わたしはわたしが誰なのか知りません。 結局のところ、みなさんは、一方で、固定された主体、あるシニフィアンにぶら下がっている主体、言うという行為の主体を扱っているのです。他方で、複数のシニフィアンが順繰りに続くのです。主体とは、実際は、どこにもありません。繰り返して言います。というのも、わたしが導き出そうとしていた結論がそうだから言うのですが、主体とは行為のなかにあります。言われたことditを発する自らの行為のなかにあります。ただし、このditは<他>からやって来るのであり、<他>にさし向けられるであり、すべては、言われたことどもditsのあいだで起こり、主体は、連結されたシニフィアンの開集合のなかで宙づりにされ、見失われ、抹消されるからなのです。われわれは行為の主体でありこの行為とともに主体なのです。しかしながらわれわれは姿を消します。われわれは、行為の主体ですがわれわれは存在しません(1)。ここに、主体のアンティノミーとも呼ぶことが出来るものがあります。 II - われわれは、まず、ラカンの理論において導入されて久しいトポロジー的な対象を用いて、このアンティノミーをイメージとして思い描くことがゆるされるでしょう。主体の定義として、メビウスの環が示すものがそうです。しかし、主体をただちにメビウスの環と同一のものとするのは誤りでしょうし、メビウスの環を見せて、「これが主体だ」というのも誤りです。そうではなく、メビウスの環から得られるものとは、面がひとつしかないというその特性が、その帯の中心に沿って切断したとき、違ったものになるという事実です(少なくとも、半回転の捻れを施した帯についてはそうです)。切断する軌跡の曲線が閉じたとき(切断の出発点に戻ったとき)、この環の特性は失われます。切断の結果できあがる帯は、もはやメビウスの環ではないのです。 アンティノミーを考えるための二番目の方法、今度は論理学的な方法に移りましょう。この方法を理解するためには、ラカンがかれのセミネールでのはなしのなかで、長年をかけて確立させた分析に立ち戻らなければなりません。この分析とは、<一>(いち)とゼロとの関係であり、これはまた主体とシニフィアンとの関係にも繋がります。この証明の詳細に立ち入ることは差し控えさせてもらいます。J. =A ミレールが、『縫合La Suture』※というテキストのなかで行っている証明は厳密ですね。ここでは、相関する重要なポイントを述べるに止めます。目下われわれに課せられた問題に答えるためです。この問題とは、主体は不可能でありながら、それでいて名指され、あるいは名指される以上に、一(いち)にむけて数える(一多いか、一少ないかどちらにせよ)のはどう説明したらよいのかという問題、あるいは、主体という移ろいやすいものが、いかにしてシニフィアンによって固定されうるのかという問題です。 ※ ≪Cahier pour l'analyse≫ no.1-2, p.39-51, Paris, 1966 フレーゲによるゼロの定義にしたがいアプローチすることにより、すっきりとことは説明できます。この数はふたつの特性を持っています。一方で、ゼロは不可能な対象を指し示しますが、この対象の現実の側面に対してではなく、真理の側面に対して指し示すのです。なぜならばかような対象は自己と同一性を持ちえないからです。他方で、数列との関連で、ゼロはひとつの数字として数え入れられます。ゼロはこうして不可能性の概念として定義され、数列のなかにおいてひとつの場所を占める要素としても定義されます。同様に、主体は、シニフィアンの連鎖からのけ者にされたものですが、それでいて、ひとつのシニフィアンによって代表され留まりつつ、そこから出て、数え入れられる要素となります。それゆえ、主体とゼロとは優れて類縁関係にあるといえますし、さらに、両者に共通する活動、つまり両者とも、それが占める独自の場所により、数列上での移動訳注)を裏付けるのですが、この活動を考慮に入れればなおさらのことです。こうして、次のように結ぶことができるでしょう。つまり、無意識の主体を語る存在etre parlantにおけるシニフィアンの効果と規定すると、このことが含意するのは、シニフィアンの列が、われわれを通して、われわれから、ゼロという定数を生み、このゼロは欠如manque、連鎖を支える欠けた支柱manque-pilierであると。 訳注)マルサスThomas R. Malthus(1798)は『人口論』(Essay onPopulation)において「食糧は等差数列的に増加するが、人口は等比数列的に増加する」と述べて産児制限を主張したが、このとき援用されたのが、タビネズミの集団移動という現象であった。 このことを、分析のなかで、どのように活用していったらよいのでしょうか。これを空虚な思弁と片付けるべきか。もし、分析中に、主体/患者が語るとして、それは意味を表すのではなく、命令するsignifier、自己に命令するためだとするならば、分析が向かう他の目標がどのようなものか、とわれわれは期待してもよいのでしょうか。つまり、ある主体/患者が語る -そこに既にパラドックスが生じています -その結果、かれは消え去ることになるのです。わざわざ行為として表明し、そして自らを消去するのです。われわれが促し、期待するのは、主体/患者が自らの資格を投げ捨て、<他>のところにやって来て、消え去り、それと同時に、無意識のシニフィアンの連鎖を再連動させることです。主体/患者は言う。そして言いながら、主体/患者となり(原文に「空白」とあり)、そして消え去るのです。行為の前にはかれは存在しなかったし、後にはもはや存在しないのです。主体/患者は、この連鎖を離れ、「外に=立つ」ex-sisteのですが、連鎖と関わってそうするのです(原文に(?)と記されている)。 この証明に辿り着いたいま、そして去勢の問題に立ち入る前に、先取りして、問いをみなさんに告げ知らせたいと思っているのですが。つまり、もし、全システムが、秩序がシニフィアンなのだとして、なぜそこに主体という語を導入しなくてはならないのか。なぜラカンは、この語に執着し、そのくせ、そもそも、主体は存在しないとまで言うのか。さて、先刻ご承知のこととは思いますが、主体の存在l'existenceを否定することは、少なくともラカン理論の視点からみれば、誤りです。「主体はシニフィアンのもとにあり、ついでもはや存在しない」という言い方には誤謬が含まれています。主体は分割されているのです。それゆえ、主体は連鎖のなかに在るのです。ラカンはこの主体という語を保ち持ち、されにはこの語を利用して、精神分析を形式主義から救い出しました。 フロイトとは一線を画して、かれは主体に執着します。好例となる件を引用しましょう。欲望の満足(ご存知のように欲望はシンボル、シニフィアンを用いて満足する、とフロイトは言います)に言及しながら、ラカンは主張します、「フロイトは、欲望が満足する、と言っていますが、わたしはこう言いたい、欲望の主体が満足する」と。なぜかれは、主体の問題にこうもしがみつくのでしょうか。此彼の懸隔、フロイトに対するニュアンスの違いを取りあげるとすると、満足の概念から、ラカンは、主体を手放さないようになったのかどうかです。主体は、ラカンにとって、享楽を語るために必要なのか、満足を語るため必要なのか。わたしが思うには、このように問いを立てては駄目なのです。後述しますが、主体と享楽とは対立関係にあるのです。留保つきで漸くこう言うことができます。享楽があるところでは主体はない、と。ですから、主体にまとわりつくものの説明としての享楽の問題提起は誤っています。 III - どのように主体の問題提起を行えばよいのかをお話しする前に、三番目の話題に直行しましょう。つまり、主体と去勢との関係についてです。去勢を巡る問題において、ラカンにおいて、問題を解く鍵を見出すことができそうです。これはジョーンズから借りてきたアファニーシスという用語にヒントを得ています。このアファニーシスという語について、ラカンはいつもといっていいくらい、かれのセミネールのなかで触れています。ジョーンズへの賞賛を交えてですが、批判的に引用しています。他にも、ラカン理論のいくつかの重要な概念が、ジョーンズの影響を色濃く受けていることで、わたしは、ラカンは、フロイトを自分の分身のように愛しているが、ジョーンズに対しては、欲望を抱いている、と思うようになりました。そこで、こうも言えるでしょう。すなわち、フロイトが「欲望が満足する」と書いている部分について、ラカンは、かれに対して「欲望の主体が満足するのだ」と言い返すのだとすると、ジョーンズが「欲望の消失aphanisis du désir」を唱えるところで、「否、主体の消失だ」と抗弁する、と。ラカンは理屈を通す。「シニフィアンの連鎖に主体は不在であるとはならない。次から次へと起こる出来事のどこにも主体は不在であるとはならない。そうではなく、主体は、消去されてではあるが、存在する。主体は、<他>のところで消失するs'aphanise」のであり、消え去るs'évanouitのだ」と。 ここで、去勢を、ラカンが何年も前に定式化した、ファロスをもつとファロスであるとの区別を参照するとなると、このアファニーシスの概念は、主体が位置する場所に裏打ちされます。シニフィアンに関わるか、ファリックな対象に関わるかによってです。 今日は、かつて報じた点について、微に入り細に入る検証は行ないません。ただ、記憶を頼りに、「去勢されているêtre châtré」といったお馴染みの表現を使うとき、これはなにを言おうとしているのか、と考えてみましょう。この表現に三つの意味を当ててみましょう。第一に、語る存在être parlantは、性に対して、二つの方法でしか向きあうことができません。シニフィアン(症状であれ否であれ)か幻想かです。小手先だけに拠る方法です。というのも、享楽への通行禁止を解除することはできないからです。通行禁止とは、ここでは性的関係が存在しないこととご理解ください。第二に、シニフィアンに頼ることが強制であり、服従であるということです。強制とは空しい反復への強制です。代理補填がいつまでたっても達成されず、不発に終わるからです。服従とはこの反復を命令するファリックなシニフィアンへの服従です。そして最後に、あるシニフィアンから他のシニフィアンへとの交替させる過酷な労働が一生続くことです。主体は、受動的に消える、消失するs'aphaniseのです。消滅のひとつのかたちがそこにあるのです。 ファロスであることに関する他のかたちは、まったく異なった次元に拠っています。幻想の次元です。そこでは、主体はファンタスマティックな対象の陰に隠れることで姿を消します。おおまかに言って、二つの類のアファニーシスを区別すべきです。もはや現前しないne plus être làための二つの方式です(これは単に現前しないne pas être làとは別の事柄です)。反復に固有の方式であり、身を隠す方式でもあります。 去勢とは、これを理解するのに困難は伴わないでしょうが、一器官の切除、そう思っている人もいるでしょうが、そのようなネガティヴなオペレーションではありません。そうではなく、去勢するchâtrerとは、継時的なシニフィアンの生産への過酷な労働です。もし、なにかが剥奪privationを蒙るとすると、それはペニスではなく、主体自身です。去勢する、それは骨抜きにすることです。というのも、シニフィアンがより執拗で、より反復を繰り返すとすると、主体は、より目減りするのですから。ここで、まとめとして、術語を他の語に置き換え、あらたに「去勢とはなにか」と問いを発するならば、去勢とは、イニシエーションであり、こどもが、世界に一歩踏み出すことですが、その世界とは、享楽を目指しながらも挫折するのを味わう世界であり(享楽は知ることすらできないもので、たんにそれを通達するだけなのです)、世界に立つには、自己が消え去ることを代償として支払わなくてはならないのです。またもや、われわれは同じ結論に達しました。こどもは世界に登場し、青ざめるのです。 先程立てた問題提起にたち戻りましょう。「この主体という語は、そこに絡み付くどのような障害からわれわれを解放してくれるのだろうか」という問いです。以下の考え方を、みなさんはどう捉えるか、つまり、存在か非在かといった古くからの選言的命題の問題を、ラカンは、袋小路に陥ることとして取りあげたに違いないとする考え方です。わたしの解釈では、ラカンにとっての課題は、主体を存在論的に捉えない、主体をある基体と看做さないことだったのです。言い換えると、主体を、表象されたreprésentéといった概念に貼付けないことが要求されていたのです。主体が、表象によって表されたものと片付けることができないことが必要だったのです。そのような主体は、バークリー風に言い表せば、かれの有名な定式、「存在l'être、それは知覚されたものl'être per6ccedil;u」となり、われわれにとっては、こう言い表すことになってしまいます、「主体、それは、表象された主体である」と。それゆえ、ラカンにとって、主体イコール基体、すなわちある表象に逐一同一であるもの、といった定式は避ければならないものなのです。もし主体がそのようなものでしかないならば、純粋な表象というものを、実体を備えた完全体として立像するはめになってしまいます。しかしながら、形而上学の網に引っかかったまま、お陀仏とならないためには、主体はそうではないautre必要があったのです。 そこでラカンは、片方の手に、代表されたreprésentéといった概念を、それが基体とはならないためにしっかりと掴んで、別の手で、すべての連鎖のなかにおいて、抹消された主体といった概念を引き寄せるのです。これを逆に言うのも有効です。主体を完全に消し去ることはしてはならないといった必要性から、代表されたreprésenté主体という概念に頼るのだと説明されます。この両方の手は、お判りでしょうが、分裂した主体を表します。この点を明確にしたいと思います。巧妙なのは、主体を単に分割したことによってではなく -そうでしたら、ラカンは存在と非在に分割することもできたでしょう -というよりは、主体を代表と代表の全体とのあいだで分割したことによってなのです。このことにどのような利点があるのでしょう。それは、このようなやり方によって、かれは、主体を代表された存在にし、一方で、この主体に、能うかぎりの言うdireを、能うかぎりのシニフィアンを、連鎖の配列に従いの鳴り響かせるのです。こうしてラカンは、主体を守り、守蔵する、とくに連鎖を守蔵するのです。連鎖とは無意識的表象代表の連鎖ないしシニフィアンの連鎖のことです。もう一度繰り返して強調します。主体の分裂は、存在と非在とのあいだのものではなく、主体を代表するシニフィアンと連鎖のなかにおける消失なのであり、われわれの文字で示せば、S1とS2とのあいだの分裂なのです。 ところが、主体を分割するにあたって、ふたつのリスクを検討しなければなりません。そして双方のリスクとも、代表するという機能にのみ基づいています。ラカン謂わく、「あるシニフィアンは、主体を、他のシニフィアンに対して代表する」と。この代表の概念ぬきにして、主体の分裂はありえないでしょう。というのも、代表するものであることを通して、主体はシステムに結びついたままでいられるのですから。しかしながら、そしてここにこそ、わたしがラカン氏から教えられたことから生じてきた質問があり、それをかれに向けて発したいのですが、みなさんにも考えていただきたいのです。つまり、このreprésentationという語の縛りだけでは、シニフィアンによる決定と消失した主体の効果というふたつのまったく異質な次元を、それをまとめて全体として支えてゆくには、あまりに頼りないのではないでしょうか。 représentationという語が、採択の決定と排棄rejet、廃止の原因と廃止されたもの、この相反する両者を結びつけることが許されているというのですが、どう理解したらよいのでしょう。みなさんのなかの何人かはこのような問題の立て方に対して反論を唱えるかたもいらっしゃるでしょうが、この反論のうちいくつかは、このわたしの発表の骨組みのなかにすでに見出されるかもしれませんし、そのことをわたしの口から申し上げるかもしれません。でも、わたしはこの疑問に対して、自由に語らせることにして、われわれはそれに身を任せた方がよいのではと思っています。あとで、道を引き返さなくてはならなくなるかもしれませんがね。 さて、主体を分割するものとしてのreprésentationを、問題意識をもって検討することによって、可能と思われるのは、主体の水平軸での分割ではなく、垂直軸での分裂増殖により、連鎖を成すに能うかぎりのシニフィアンを生ぜしめることです。つまり階を成すように薄片が積み重ねられた主体です。このような主体の空間上の概念形成は、解析関数で定義できる、リーマン面(2)と呼ばれる、トポロジー的曲面のいくつかの類をもって現れてくるものです。19世紀の数学者リーマンは、複素変数への解析関数理論の応用を通じて、多価関数の特殊なケースを驚くべき方法で解決しました。何度も指摘しますが、(複素数zの平方根の)変数に複数の関数が対応するようにするのです。他の計算(積分)にとって、不規則数は計算の障害となるものですが、この不規則数を取り除くため、リーマンは、いわば、代数的関数固有の領域を離れ、幾何学的空間に、さらには、空間の想像的なものl'imaginaireに依拠することとなるのです。そうして、かれは、関数に値するものを能うかぎり増やすといった試みに着手します。関数の数を減らす努力をするのでなく、変数にいくつもの関数を対応させ、この対応により、変数の値を切り分けるのです。ひとことで言いますと、リーマンは、関数の数を減らすのではなく、複数に分けた変数に値を振り分けさせたのです(3)。ところで、この関数を増やすというやり方には、少なくともリーマンのやり方においては、空間的,トポロジー的支えが必要となります。かれは、重ね合わした薄片で構築物を建てます。個々の薄片はそれぞれの値があり、この値とは平面を複素数で満たした集合と看做せます。幾層もの階あるいは薄片は、曲面の性質により、その数を無限大まで増やすことができます。この構造こそ、リーマン面と呼ばれるもののことです。 このタイプの分析と主体とのアナロジーとして捉える、よくやられることです。こう想定しない手はないんじゃあないか、勿論、試行錯誤は必要だが、と。主体は、自らの関数を増やすという操作を蒙り、自らを薄片を積み重ねられたものとして構築するものだとの想定です。リーマンが変数の値に操作を加えたようにです。そしてもうひとつの想定です。主体は、連鎖を構成するシニフィアンの数に従って自己を細分化しるとして、首尾よくそこに同一化を行なうことができるのか、という推定です。仮にこの推定が当たっているならばですが、自明のこととして、主体はこのシステムへの執着から解放されることになります。なにせこのシステムは、主体がそうなる当のものなのだから、その必要もないと。次も自明のことです。主体が連鎖に同化する様を名づけて、これを知を想定された主体と呼ぶことです。これも既に、説明してきたつもりですが、主体の否定と主体の依存とを混同すべきではありません。また、主体は存在しないと言うのと主体は消失するs'aphaniseと言うのとは別の事柄ですが、これらは周知のことです。しかし、いつもながら実感させられるのは、精神分析家にとって、理論面でも実践面でも、この主体が、われわれからするりと抜け出ていってしまうということです。主体とは、じつは、ゲーム理論がよく当てはまる、お飾りとして他のカードに付け加えられた「ジョーカー」のようなものとして、推論、思弁の対象となっているのです。われわれ分析家は、主体思想の下僕のように振る舞っているが、心底では形式主義的主体論者なのです。 さて、リーマン面を援用して、主体を薄片の積み重ね構造を持ったものと看做し、一方で、消え去るものと看做すことで、主体というものについて、直観的な把握ができあがってゆきますが、それと同時に、当の直観を次々に訂正してゆくのを止めて、直観そのものが症状ではないのかと問い糾す方向にも向かいます。そうなれば、問題はもっとすっきりとしたかたちで示され、そこからさらに、主体の効果的なアファニーシスへの深化が必然的に見えてきます。同時に、その結果としてですが、自我の想像的imaginaire次元について更なる検討が加わるでしょう。主体についてのわれわれの諸定式をもとにして考えると、この自我を巡るテーマおよびその検討に際して与えられる直観は例外的なものです。主体がわれわれが措定したように、連鎖に閉じ込められたままのものとしても、自我の想像的審級までも視野に入れておくこと、このことと直観との関係についてさらに分析を深めてゆくこと、これらの必要性を重要課題として受け止めるべきです。 端的に言うと、つねに「主体とはなにか」といった問いを発してゆくことがわれわれに課せられているのでしょう。去勢という術語に立ち戻るならば、また、主体というかわりに子ども、連鎖というかわりにその翻訳として父親の法、たんに享楽を規定するかわりに、※母親の享楽と言い換えたなら、そして最後に、もし、精神分析において子どもとは誰なのか、精神分析が、その仮説を支えるうえで、かくも饒舌に語っている、この驚くべき子どもとはいったい誰なのか、と自問してみてください。こう答えることとなるに違いありません。この子ども、つまりこの主体とは、父親の言葉で話し、考え、母親の享楽によって引き寄せられる存在であると。精神分析における驚くべき子どもとして、われわれ語る存在は、風のような存在、言葉を希求する享楽とこれら言葉を秩序立てている父親の名のあいだで消え去るメッセンジャーでしかありません。 ※この印の注として、余白に判読不能な人物の名が記されている。YあるいはAYで終わる名前である。 (1). (2). (3). については、以下のコメントが付記された。 (1). わたしは、「われわれはnous sommes」と言いますが。このnous sommesから始めるのは正確ではありません。というのも、「わたしが主体は行為において存在する」、と言い、ついで「この主体は言われたことles ditsにおいて、自己を抹消する」と続きますが、問題があります。この「われわれ」nousとはなんでしょう。わたしが「われわれはnous sommes」というのは、「われわれは主体について思弁を巡らすことができるのは、われわれ自身が主体として、主体に根ざす二重性duplicitéに関わっているかぎりにおいてです」(ラカン) (2). リーマン面ないし複素数解析多様体の構造は、代数的関数理論とトポロジーに共通の基本理論のひとつです。このリーマン面の特性のひとつで、とくにラカンが導入したトポロジー的対象の操作のなかでわれわれが関心をもつ機縁となったのは、リーマン面での方向付けorientabilitéです。逆に、すべての方向付け可能な閉じた曲面はリーマン面と同相homéomorpheであり、球面、トーラス、穴の空いたトーラスに当たります。この点については、G. SPRINGER. Introduction to Riemann surficesの第2章を読んでいただければ、理解は容易いと思います。 (3). 注目すべきは、このリーマンの発見は、かれの重複度の定理theories des multiplicitésに負うています(この概念はHerbart訳注)の哲学の影響が色濃い)。 訳注)リーマンは、かれの業績の随所において、かれの理論がヨハン・フリードリッヒ・ヘルバルトに、とくにかれの哲学と心理学に負うていることを述べている。かれの1854の論文において、かれ自身の重複度の概念の前提となっているものは、ヘルバルトとガウスに尽きるとまで述べている。(cf. http://solidariteetprogres.online.fr/Dossiers/Culture/Herbart.html) (この原稿はJ. D. Nasioにより校閲済みである) (2008/02/22) |