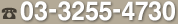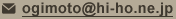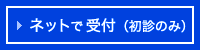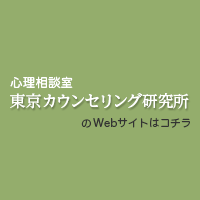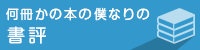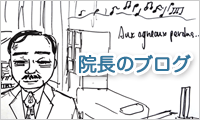|
ジャック・ラカン
 |
 (13) 1963 3 6 水曜日 フロイトの『制止、症状、不安』の補遺B、「不安についての補言」のなかで、「なにものかの前での/に対しての不安」Angst
vor etwasという件から問いを発し、不安、対象そして欲望との関係をどのような構造で示せばよいかラカンは考えます。ラカンは、欲望の原因としての対象が、この欲望の前にではなく後ろに置かれるとしたことから、不安におけるこの「前」vorをめぐり、「このvor、このものを、あなた方において、欲望を前に押し出すものとしてpromouvant、欲望の後に置きましたが、これがどうして前devantに位置をずらしたのか」とこのvorを通して、対比をもったものとして、この構造について問いが立てられるのではないか、と切り出します(V.
A. p.143)。 フロイトのvor etwasに戻ります。なにに対する不安かですが、フロイト自身述べているように、それは危険Gefährあるいは危険状態Gefärung、それも内的なそれです。内的な危険に対しては、防衛が関わってきます。そしてフロイトのいう信号は、シニフィアンの領域に属するものではなく、現実という不可避的次元からやってくるもので、それゆえ騙さないものです。 エディプス神話において、エディプスは母親を享有しました。そしてそのことを知るvoirこととなります。その直後、かれの両眼は(その前に、ラカンは言葉に尽くせないもの、それでもわたしはあなた方にイメージとして示したいと言っています、と述べています)、眼窩から抉りとられ、眼球の硝子体とか房水を含んだまま膨れ上がったものとして。まさに地面に落ちます。濁った汚物の堆積です。かれは視力を失いました。しかしながら、かれはこの両眼を、原因としての対象として見ずにはいられません。究極の、もはや罪をまぬかれた、いや、限界を超えているのです、つまり欲望のきわみconcupiscence、知りたいと希求するconcupiscenceです。 1) ラカンは、サドに関係する形容詞を使い分けています。sadiqueとは、もっとも一般的で、「サド的」と訳してよろしいのではないでしょうか。sadienはサドという人間にかかわる場合使われることが多いように思われます。「サドの」で宜しいのではないでしょうか。問題はsadisteで、これは名詞sadismeに対応するものですが、Jean Allouchは、"ça de Kant, Cas de Sade"のなかで、例えば、Écrits所収の"Kant avec Sade"においては、( … ) le sadisme rejette dans l'Autre la douleur d'exister, mais sans qu'il voie que par ce biais lui-même en un "objet éternel", si M. Whitehead veut bien nous recéder ce teme" (Écrits. p.778)とあるのに、1963年のCritique誌においては、( … ) le sadique rejette dans l'Autre la douleur d'exister, mais sans qu'il voie que par ce biais lui-même se mue en "objer éternel"となっている点に着目し、ここでsadienからsadismeへの訂正は、sadismeという語の通俗化をそこに読まなくてはならず、Écritsの方の訳としては、「通俗的なサド像(とはいえないであろうが、ブランショ、バタイユのサド観によるサド像も含めて)によれば、このサドは、<他者>のなかに(『不安』のセミネールに従えば、<他の>シーンのなかに、と訳し替えることができる)、ずっと生き続ける苦しさ(séminaire VII巻で出てくる、第二の死を意味するものであろう。いわゆる無限地獄であり、享楽そのものを表している)を投げ込み、しかしながら、この迂回(つまり、通俗的sadisme観からみること)により、もしホワイトヘッド氏が〈永遠なる対象〉というかれの用語をわれわれにお返ししてもよいと言うならば、使わせてもらうとして、この永遠なる対象へとsadismeにおけるサドは向きを変えてしまったということに気がついていないのではなかろうか」(Écrits, p.778)とならないでしょうか。"Kant avec Sade"における主体(拷問を課す主体も犠牲者の主体も)も二分duplicationが施されていて、享楽の意志は変節して、快感原則にも従わなくてはならなくなるところが、このラカンのテキストの重層的な難解度を解く鍵となるのではないのではないでしょうか。 では、サド的sadique、マゾシスト的masochisteのポジションとは何なのか考えてみましょう。聖ルチアと聖アガタの像は大いにかかわっているのですよ。鍵は不安にあります。しかしそれは探さないとだめです。なぜそうなのか解らないとだめです。マゾシストについては、前にも話しましたが、前回でしたっけ。マゾシストのポジションはどうなのでしょう。マゾシストの幻想は、かれにおいてなにが隠蔽されているのでしょうか。<他者>の享楽の対象であること、それがかれ自身の享楽として望んでもいるのですが。というのも結局は、マゾシストは、いま言いました逆説(「Zurbaránの描いた聖ルチア、聖アガタに対してわれわれは、欲望こそ抱くが、不安を感じはしない」とするラカン自身の言葉)のとおりですが、かれのパートナーとは巡り会うことができないのです。 2) ラカンの覚え書き的な草稿のこの頁の頭の部分には、la jouissance de l'Autre/l'angoisse … l'angoisse de l'Autre/objetといった記載が認められるとV. A.の注にあります。 続いてキリスト教の核心に迫ります。 神には霊魂などありませんでした。このことは明白です。神学者で神に霊魂を賦与しようとした人などいませんでした。ところが、神との関係の図式がまったく別なものに変ってしまったのです。それはあるドラマから始まります。受難というドラマであり、ある人が神の魂となるのです。というのも、堕天したchu(この堕天したという語にpéjoratifな意味をこめないで読んでく ださい。他に適切な日本語が思いつかなかったもので=小生)対象の残り物であるa、このことが味噌なのですが、このaの次元に霊魂の場所を設定するために、霊魂が生きているという観念をもつ必要などないのです。この観念はたいそうな行列のご一行ができましたが、この行列のお陰で、霊魂は生きているというまことしやかな観念がわれわれの文化圏では罷り通っていました。しかしながら、この堕天la chuteというイメージは、これこそ重要なイメージなのでが、伴っていませんでした。kierkegaard3)こそは、この構造を見事に見抜いていたのです(V. A. p.148)。 3) いうまでもなく、キルケゴールが『不安の概念』のなかで述べているアダム(それは種としての人間でもある)の無垢の状態からの堕罪、(楽園の)追放ですが、Jean Ansaldiによれば、この無垢の状態こそラカンの享楽にあたり、それは言語の<他者>、ラカンが存在しないと言っている<他者>の<他者>、真理をいう真理であるメタ・ディスクールとまで言っています(Jean Ansaldi, "le Discours de Rome suivi de L'angoisse, Le Séminaire X, Théétète, pp.54-60. ラカンはマゾシスト的なものから説明を始めました。その方が混乱を招かないからだそうです。問題は、マゾシスト的なものとサド的なものを正反対の対立物とする誤った図式です。 ここでラカンは、再び聖アガタの話に触れ、切り落とされた乳房は不安を招くことがなく、不安を招くのは分離の瞬間だとします。そして生物学の話に移ります。動物には胎生動物と卵生動物が分類されているが、実際のところ、すべての動物は胎生動物だともいえるが、卵生動物だともいえると。胎盤は、胎児由来の組織と母体由来の組織が合体したもので、羊膜を卵殻だと看做せば、胎児は自分の栄養を自己補給しているともとれるのであり、着床とは、母体に胎児が寄生する現象だともとれるからです。胎生、卵生の見方を変えることで、胎児と胎盤、乳児と母親の乳房これらは両受体ambocepteurと名付けることができます。 ここから去勢の話へとラカンは進みます。フロイトは性交の中絶coïtus interruptusと不安を結びつけました。この場合、射精はリング・アウトla
mise hors de jeuに等しく、享楽を勝ち取ることはできません。もちろんペニスは膣内にあっても萎えてしまいます。両者にとって去勢は平等です。萎えることchuteについて、神経症者は、主体の現実の落下chuteをめぐって、役に立たなくなった器官について、部分対象を、また幻想をつくり出します。答案を書き終えようとした瞬間、答案用紙は回収された、と訴える神経症者は、不安のさなか、射精してしまった、と言うのと同じようなものです。 |