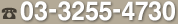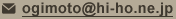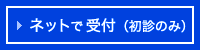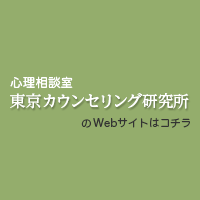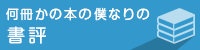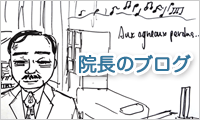|
ジャック・ラカン
 |
 (8) 1963 1 16 水曜日 前回のセッションで不安は対象なくしては存在しないとラカンは言いました。この対象が対象aで今年度のメイン・テーマとなるものです。不安とは対象aを語るに際してその迂回路に存在し、対象aの唯一の主観的翻訳なのです。既に、対象aは幻想の式 S barré poinçon petit a でお馴染みのものです。これは [S barré] désir de (a) と読むことができます。幻想は欲望の支えとなるものです。このことに関しては、『無意識の形成物』の1958年3月26日のセッションを参照してください。 ここで、欲望と対象との関係について陥りやすい迷妄として、ラカンは、フッサールのいう志向性に準じてこの関係性を捉えることだとしています。欲望の対象objet du désirといった表現を、実際ラカンはこれまで用いてきました。この志向性の教えるところでは、なにかしらのものに向けて、ノエマ(ラカンはこれをpenséeとも言い換えています)が必ず存在するとなります。欲望についても同じなのでしょうか。 欲望の対象とは先にあるen avantものなのでしょうか。そうではありません。そのように捉えてきた対象関係論において不毛な方向性を歩んでしまってきたのです、とラカンは言います。 J.= A. ミレールはこの不安のセミネールにおいて、ラカンは欲望についてのクラシックな教義を刷新していると述べています。そもそも欲望は、分析的に解釈されたものとして、パロールないしシニフィアンの連鎖の底流にあり、抑圧された欲望として、メトニミークな欲望であるが、それとは別の面もあり、これは、ミレールに従えば、現象学的欲望、対象に魅せられたものとしての欲望だとされます。ところが本セミネールで現象学でいう志向性の構造を退ける欲望が登場します。対象への志向性の構造に換わって対象の因果性(原因性)causalitéの構造というものが本セミネールのライトモチーフとなっているとしているのです。
高峯一愚氏の著作を読むと、カントにおいて、アリストテレス(『自然学』等参照してください。しかし、アリストテレスはあまりに多くのことを列挙するので、そこにどのように原理を立てていってよいのか、後世の哲学者の悩みの種となっており、カントもその例外ではなかったのでしょう。例えば、オルガノンのなかの『カテゴリー論』の第12章では「より先」というものについて、時間的なものと論理的なものだけに限定できない言語使用が存在する事実が述べられており、読んでいて混乱してきます)からとった「われわれにとって先なるもの」プロテロン・プロス・ヘイマスと「本性上先なるもの」プロテロン・ティ・ピュセィの両極がつねに循環的に働いている様を窺うことができます。前者は特殊的、質料的であり、後者は普遍的、形相的で、transzendentalの定義として、「超越的なtranszendentalなもの、つまり超感性的理念つまりは仮像を内在的に、しかもア・プリオリに規定される様態」だとすると(トランスツェンデンタールとア・プリオリを混同してはなりません)、いわゆる強弁的な弁証的推理によってもたらされる仮像、理性の思弁的使用によって悟性を空転させて、「構成」によって辿り着いた超越論的理念である、自己原因としての自由、最実在的存在体としての神、思惟する不治の魂に辿り着くことが出来るのだが、今度はこれらを「統制的」に、例えば「自由」に関していえば「実践的自由」は「本性上先なるもの」によって規定されているのだから「われわれにとって先なるもの」である「超越論的自由」も確立される、とするのは凡そ循環論法の誹りをまぬかれることはできないと小生は思うのです。ここら辺のところは高峯氏もちゃんと意識しているふしは臭わせています。ですから小生はカントの解説書としてかれの三批判解説『カント 純粋理性批判入門』、『カント 実践理性批判解説』、『カント 判断力批判注釈』(すべて論創社)は貴重な書物として拝読している次第です。
みなさんは、エピステモロジーにおける展開において原因causeの概念だけが立ち行かなくなってきていることに十分通じてられるでしょう。この概念は内容がどんどんと希薄になり… une succession de réduction、貧弱で曖昧な機能の極みとなってしまってしか生き続けることができなくなったのも、広義に解しての話ですが、現代物理学と呼ばれる領域の進歩がそうさせているのです。 光を量子と看做した際、E=hν(E=光のエネルギー, h=プランク定数,ν=振動数=光速度/波長で示される。顕微鏡で電子を覗いたとき、その位置の不確定の大きさをΔx=λ/AB/AE(Δx=顕微鏡で電子を覗いたとき、その位置の不確定の大きさ, AB=レンズの直径, AE=物体とレンズの縁までの距離)となる。一方、h/λの運動量をもつ光子で物体をはじいたとき、物体はどちらにはね飛ばされてしまったのかよくわからない。特にレンズが大きく、EとAとのこりが近いほど、電子を横に強く蹴った光がレンズに飛び込んでくる可能性がある。このため、観測された電子の運動量の不確定の度合いΔpは、用いる光の運動量h/λにABとAEとの比を書けたもの、Δp=λ/h x AB/AEになる。ここでΔxとΔpとをかけあわせてみる。そうすると、レンズの直径とか、レンズと物体との距離などという、使用する顕微鏡独特の数値は消え去り、しかもλも消去されて簡単に、Δx・Δp=hとなる。この関係式が、ハイゼンベルクの不確定性原理である(以上、ほぼ都筑卓司著『不確定性原理』BLUE BACKS 講談社からの引用です)。 この後すぐに、ラカンは「対象aは、ノエシス的契機における志向性l'intentionnalit éd'une noèse 1)といった類いのもののなかで位置づけられるべきものではないし、この志向性は欲望の志向性ではないです。この対象は、われわれからすれば、欲望の原因として捉えられます。先ほどの譬えでいえば、対象は欲望の後にあるのです(太字=筆者)。さらにラカンは続けます。 1) Claude conté, Jean Ouryの版ではl'intentionnalité d'une noèmeとなっています。 この対象aからひとつの次元が現れてきます。この次元を主体の理論から除外しているところに、主体/客体の相関の問題に欠陥が生じてきているのです。この相関の中心部分が知connaissanceの理論として大手を振っているのですから。この対象の機能は、そのトポロジー的構造について新機軸を打ち出すことが要請されているのですが、このことについては既に、フロイトははっきりと述べていますし、特に欲動についての記述を読めば一目瞭然でしょう(V. A. p.80)。 曲面のトポロジーにおいて、クロス・キャップの構造はラカンが相互貫通線ligne d'interpénétrationという言葉で言い表している部分は、はめ込みimmersionと看做すことができるでしょう。前述した不確定性原理との関連から、トンネル効果によって説明されるリーク電流は三次元ユークリッド幾何学では捉えにくい、曲面のトポロジーによって理解しやすい現象ではないでしょうか。 フロイトの欲動についてのラカンのコメントに戻りましょう。欲動には目標Zielと対象Objektが区別されています。『続精神分析入門』Neue Folge der Vorlesungen zur Einfürung in die Psychoanalyse, GW XV, p.102- (邦訳 : フロイト著作集、第一巻、464頁-)で、フロイトは「目標は自己の身体にもとめられることもありますが、通例はある外的対象が挿入されており、この外的対象において欲動はその外的目標に到達します」と言っていますが、この「挿入される」eingeschobenという語をラカンはVerschiebung(置き換え)déplacementと同義の動詞の分詞形と解釈します2)。また同箇所で内と外inner, außerを巡って、対象は外に、傾向的満足は「手袋の」内側のなにかにおいて認められるとしています。手袋gantをラカンはしばしばトポロジー的構造を説明する際用いていますが、retourner qqn comme un gant 「誰々の意見をまったく別のものにしてしまう」といった意味の成句があり、図25において、このようなフロイトの言葉の撞着はトポロジー的に解決されます。外部(a)は、主体が、<他者>の位置において自分自身の鏡像を捉えるより前に(太字=小生)内在化され、自我と非-自我との分化が起こるのはこの鏡像が映されてからのことだとします。 2) 欲望が対象を追究するmetonimiqueな運動をラカンはdeplacementとしていることは周知のことです 対象aについて、フェティシストのフェティッシュを例にとると、フェティッシュは端的にまずフェティシストの欲望の原因なのであり、ヒール靴がフェティッシュだとすると、「かの女」がそのヒール靴を履いている必要などないのです。これはちょうど、女性の胸に夢中ならば、それが「かの女」の胸でなくてもよい、といった論理なのです。 さて主体と対象との関係について、話が及びます。 aをちょうど天文学でいる歳差運動として捉えるように位置づけるとしましよう。(…)人間の心的習性は、人間の主体というものがどこにあるのか探ろうとしますが、残念ながら、それはフロイトが傾向の源泉として示した場所にその横顔を認めるぐらいなものです …(sic) そして言葉のなかにおいてはdans le discours、あなたたちが自分だと、あなたたちが「わたしなんだ」と言うその瞬間に、正確に言えば、その瞬間、無意識の次元において、aが身を据えることになるのです。無意識ではあなたたちは、その瞬間、a、つまり対象なのです。誰だって、そんなのは耐えられないことですが、それどころか話discoursのなかだけではすみません。ディスクールは結局、対象を裏切るのですから(V. A. p.81) そしてサド的、マゾシスト的主体と対象です。 図31において、右側はA、<他者>の側で、上にS、下にS barréが位置し、左側はS、未だ成りそこないのわたしje encore inconstitué、問題視されるべき主体、精神分析におけるわれわれの経験においては再検討されて然るべき主体です。この主体は伝統的な主体/主観、つまり対象/客体との独占的な関係をもちうる主体/主観の定式とはまったく相容れない主体です。 図32に移ります。\\はサド的欲望[d]と呼ばれるもので、そこには謎があり、分裂schize、分離dissociationとしてしか説明や定式化ができないものが含まれています。この欲望は、ひたすら、これらを他者に持ち込むことを企て、ある限界まで堪え難いものを課すのです。限界とは、主体が生きていることによって蒙る、身体に痛みを与える分割division、裂け目béanceが他者において体現する地点です。ところが、サドの目論みは、他者に苦痛を与えるというよりは他者に不安を与えることであることとラカンは言います(ここでの他者とは?他者?ではありません)。 今度は図33が描かれます。ここでS barré φのφは、今年度の2回目のセッションで示したものと同様、アルファベットのオーではなくゼロです。他者の不安、つまりこの不安の主として味あわなくてはならない生の苦しみ、サド的欲望が扇情に長けているのはこの点においてです。ラカンが過去のセミネール(L'téique de la psychanalyse, 23 MARS 1960, 30 MARS 1960)で、サドをカントがかれの純粋実践理性批判の課題との可能性として述べている箇所との関連で取りあげるのに吝かでなかったのはこうした理由からです。より正確にいうと、道徳意志の可能性の問題です。端的に言ってしまえば、道徳的純粋善との関連で明らかにされる一点をそこに持ち込んだらどうなのか、ということです。 余談ですが、ラカンは『エクリ』所収の『カントとサド』をÉdition du Cercle du
livre présieux版のサド全集の第15巻、『閨房の哲学』の序文として執筆に勤しんでいたのですが、結局、ラカンのテキストは不採用になり、1963年のクリティック誌(1963年4月号、No
191)に発表されることとなりました。どうして不採用になったのかについては、Jean Allouchの "ça
de Kant, cas de Sade" (Cahiers de l'Unebévue)
に詳しい。 3) V. A. では、… c'est une forme précisément - Man Ray n'a pas trouvé mieux, le jour où il s'est agi de faire son portrait imaginaire -, une forme pétrifiée. V. M. では …c'est précisément la forme que Man Ray n'a pas trouvé mieux que de lui donner le jour où il s'est agi de faire son portrait imaginaire, à savoir une forme pétrifiée. マゾシストの位置はまったく違います。マゾシストにとって、自分自身の対象としての受肉化は宣言された目標なのであり、テーブルの下の犬4)、取引される商品objetsのなかのたったひとつのアイテム、端的に言うと、対象一般、交換される商品である他の(太字=筆者)対象への同一化を強要されるのです。このような「どうにもならない」impossible道をマゾシストは求めているのです。どうにもならないとは、自分に対して自分を捉える。皆がそう捉えるように、自分がaであるものとして捉えるのですC'est la route, la voie qu'il recherche justement, cet impossible qui de se saisir pour ce qui est, en tant que, comme tous, il est un (a). 現象学の立場からでしたら、… de saisir l'(en-soi) comme le (pour-soi) … とでも言えそうですが、後になって、ラカンがサルトルを批判している箇所に触れますので、そのときにまとめてお話しいたしましょう。 4) マタイ伝、15, 21-28. 異邦人の女はイエスにとっても犬でしかなく、「子どもたち(弟子たち)のパンを犬に与えてはならない」とまで言う。しかしこの異邦人の女は食い下がる。「犬だってテーブルから落ちてくるパン屑、つまり奇跡をじっと耐えて待ち望んでいるのです」と。イエスはこの異邦人の女の信心深さに心を打たれ、自らの狭い心を恥じる。 しかしラカンはこうも言います。ただ単に、マゾシストは対象への同一化に達するのではなく、サディストが現れるのと同様、あるシーンにおいてこの同一化が現れるのだと。但し、このシーンにおいてさえ、サディストには自分の姿を見ることができず、残骸le resteしか目に入らないのです。(2007/12/06) ここで、マゾシストと対象、超自我との関係をめぐって、理解を用意にするため、Pierre-Christophe Cathelineauの "Masochisme et culpabilité, 16/01/1996 (Freud Lacan com. article=00042)に依拠することとします(途中、小生が思うことを太字で挿入させました)。 フロイトは "Das ökonomische Problem des Masochismus" (G.W. XIII pp.369-383., 著 300-309頁)において、「罪責感」は奇妙なことに、大概の場合は無意識的であると言っています。では意識的な罪責感、悪しき良心、過失感 pensée d'une faute はどうなのでしょう。女性的マゾヒスムスの場合は、マゾヒスムスは幻想のなかにおいて提起され、倒錯的マゾヒストによって現実に示されますが、女性的マゾヒスムスは性愛的マゾヒスムスに還元されます。ラカンはアングロサクソン系の精神分析で展開を見なかったこの女性的マゾヒスムスの特殊性をLes quatre conceptsで論じています。女子に原初的に現れると想定されるマゾヒスムス的状況は抑圧によりサド的状況へと変貌を遂げ、その性愛的性質は抹消される。男子においては、マゾヒスムス的状況にとどまる。であるから、女性的マゾヒスムスを論ずるには、男性から始めなくてはならないと。「子供がぶたれる」を巡って倒錯的マゾヒストの仕掛けというものはその幻想に帰着するとフロイトは言う。ここに現実 le réel と幻想の言表との相違が問題となる。フロイトはMétapsychologieにおいて、欲動の目標の能動性と受動性それぞれを区別してその変化形を論じているが、受動性のそれについてはあまり関心を示さない。受動性という概念からして、マゾヒスムスにおいて鍵となるのは苦痛の快感ではなく、この快感に伴う支配権Herrschaft, Bewältigungとなる。 ラカンがマゾシストがangoisse de l'Autreを引き起こすという場合、このdeは主格=目的的使用で「<他者>に対する不安」であり、主体がreste, déchet であるaとなることに対する不安です。 フロイトにとって、リビドーと死の欲動は欲動のふたつの側面ですが、より根源的な死の欲動をリビドーは、性に、生に(フロイトは、バタイユとは違って、エロスを常に生の欲動の側に位置づけており、生涯この立場を変えることはありませんでした)、あるいは筋肉組織を介して外界へと逸らしてゆかなくてはならず、ここから支配欲動、権力意志への欲動(Nietzscheもさらにサドの自然に対する態度-そこには、啓蒙主義と当時のフランス貴族の一部に特有なものなのでしょうか、新古典派的趣味といったもの〔これはかれの『イタリア紀行』に窺うことができると思います〕との相克-もこのようなコンテキストを意識して読んでゆくことが可能でしょう)が説明されると言えるでしょう。 翻って、欲動の源泉は、源泉という言葉からしてérogèneという語に結びつくといえるでしょう。ここでマゾヒスムスは性愛的マゾヒスムスとして欲動の源泉とその目標への回帰という事態がマゾヒスムスを軸にして論じられるべきと小生は思います。小児の自慰に対する親の禁止(この禁止が現実に存在したかしなかったかはケースによりけりでしょう)は事後的に法の侵犯とそれに対する罰を主体に刻印するでしょうし、このことから侵犯(超自我の命令自体が欲望の法の神経症的解釈であり、パラドクサールなことに、この法に定言命令的に従うことが欲望の法に対する侵犯となるのです)と罰を追い求めるという愚かなことを人間の主体は一生繰り返してゆきます。ここに、マゾヒスムスにおける対象aへの同一化というものが理解できるでしょうし、人間にとって根源的な問題がここに横たわっていると小生は思います。 道徳的マゾヒスムスに話を戻しましょう。無意識的な罪責感は良心(フランス語ではconscienceです。意識と良心とのあいだで混乱が起きても不思議ではありません)の呵責として顕現してきます。この傾向のある主体/患者にまとわりつく困難さは、治療への徹底した抵抗です。分析家あるいは分析的な治療を掲げている治療者は権威主義的(フランクフルト学派のいう権威主義的ではありません、もっと通俗的な意味での、つまり権力を笠に着るといったタイプです)治療者ではありませんから、こうした主体/患者は分析あるいは分析的治療に陰性反応しか起しません。フロイトも対抗策として考えました。無意識的罪責感を意識化すればよいと。治療者は超自我の分身であるかのような理想自我の位置に身を置けばよいといったようなことも言っています。一方で、現実の生活での災禍、財産を失うとか重篤な身体疾患に罹患するとかいった契機をもってこの道徳的マゾヒスムスの傾向は消失するともいっていますが、このような災禍は当の道徳的マゾヒスムスが求めていたものに他なりませんので読んでいて空しくなります。「犯してもいない罪を認める」とか「罰を受けるために罪を犯す」といったテーマは『トーテムとタブー』、『モーゼと一神教』にも認められます。後日のセッションで主要なテーマとなる、行為化 passage à l'acte においても、自傷あるいは自殺企図は自罰でしょうし、これに伴う苦痛は、自責感よりもはるかにましであるから、主体/患者はこうした行為に及ぶ訳です。リスト・カットすること(治療者が匙を投げないかぎり、ほとんどの場合、リストカットはacting-outですが)をフランスでは一般にはcouper la veineといいますが、最近、昔行なわれていた瀉血のとき吸い玉を用いる前処置としての皮膚への切り込みを指していたscarificationという語が当てられるようになって来ています。アナグラムを意識してこの語が選ばれたとしたら出来過ぎで恐ろしいです(sacrification-scarification)。道徳的マゾヒスムスにおける超自我と理想自我との関係をみてゆくと、主体はかれの理想(ここでのフロイトは自ら打ち立てた超自我と理想自我との関連で混乱しているとしか言えません)からの要請のこちら側で取り残されている自分の像に対して「道徳的不安」を抱き、それに反応するのです。 sinthomeの最初のセッションで、ラカンは知はdiscour
du maître(「主人の言説」とか「主の言説」とか訳されてきましたが、maîtreという語にmaîtriseつまり支配、コントロールという語、これは死の欲動をリビドーが生/性へと方向転換させるに際してのコントロールを含意しますが、このことを意識してこの言説を理解すべきです。生を命じ、死〔去勢によって主体は死つまり有限性を受け入れますが、これは生からの解放である安息としての死です〕を与えず、死しても第二の死、無限地獄、『ジュリエット』に登場するサン・フォンの思い描く死後も続く拷問、つまり生き続けることの苦痛douleur
d'existerを命じるのは超自我以外にはありません。signifiant-maîtreによる命令とは超自我の命令と他ならないのではないでしょうか。Braunsteinはラカンの超自我とフロイトの超自我を混同してはならないと言っています。前者の命令はobéirではなくjouirの命令ですが、jouissanceこそ、フロイトが禁じていた当のものとしています。しかしながら、ラカンのjouissanceはいくつもの異なった事柄をカヴァーする語で、現にBraunstein自身、jouissanceをjouissance
de l'être, jouissance phalliqueそしてjouissance de l'Autreに大別して述べています。この三者に3タイプの超自我を当てはめた場合、jouissance
de l'êtreに符号する超自我こそ、生を命じる、「猥雑な、獰猛な、限度を弁えない、言語とは異質の、そしてNom-du-Pèreを与り知らない超自我で、これはフロイトの超自我ではないもの」ということになります〔La
jouissnce-Un concept lacanien, Nestor Braunstein, Point
hors ligne, pp.317-318.〕)において分割されます。この分割はsymbole(le
symboliqueではありません)の分割に一致することになります。次いで、ボロメオの輪はle symboliqueの分割、symboliqueの輪とsinthomatiqueの輪に分割されます。これが主体の分割にも影響を与えるのです。 本セミネールにおいては、ラカンは、フロイトの3つのタイプのマゾシスムの分類について、説明が不十分だと批判しています。なにか統一原理が必要でしょうが、マゾシスムがあるのは超自我があまりに残忍だからとするのは一面的すぎると言わざるをえません。原因としての対象というものに超自我が一役買って出ていなければならないはずです。対象のカタログを分類のなかに加えることだってできるでしょう。母親の乳房、糞便、ファロスと。しかしその後に眼をラカンは加えます。慎重さを欠いてはならないといいながら、眼は、それが存在しなければ、不安も起こりえないものであるのは、それが危険な対象だからだとし5)、そのすぐ後に、欲望と法は同一の事象だと言ったことについて聴衆のひとりに喚起を求めています。 5) ラカンは、注釈として、これは超自我のことだ、と後にタイプ印刷版に加筆しています。ここでは眼=超自我なのです。 欲望と法は同一の対象を共有しているかぎり、同一なのだと言ったというのです。しかしながら、両者は単に同一のものの両面とは安直にはいえないこと、正しい道を進むため、向かう先でそれらが同一であることを気づいてもらうためだと言います。その地点とは精神分析にとって、それがスタートために必要となる最重要な神話、エディプスの神話だと。 エディプス神話が言わんとしていることとは、まず最初に欲望、父親の欲望と法は同一のものであったこと、法の欲望根の関係は切っても切り離せないもので、それがゆえ、法の機能とは欲望の道を辿ることだった。また母親にとっての欲望も法の機能と同一のものであったと。ただし、法がそれを禁止するものとしてがこの法が母親を欲することを課していたのだと。というのも、結局、母親はそれ自体として強く欲し求められる対象ではなかったのだから。母親ではなく妻を選ぶのは、欲望の構造においてすでに命令が重きをなしているからです。命令のためにひとは欲望するのです。エディプス神話が意味するのは、父親が立法者であるとする欲望です。 マゾシストの役割とは、<他者>の欲望が法をなすことにあります。かれは、排泄物(ラカンdéjetという語を用います)であるaとして登場します。どこに登場するかというと、かれの小さな舞台、シーンにです、とラカンは言います。この舞台とは<他者>の欲望が法を生み出す次元です。 …このaは、もし、それが認められる場所に位置するとすると,それが可能だとすると - というのも、いましがた申し上げましたように、欲望の対象として自ら認められる/承認されるse reconnaître対象としてのaは、それはつねに、マゾシストだからです、それが可能だとしてです。マゾシストがそうするとして、それは舞台の上でだけです。かれがもう舞台の上に居られなくなったとき、そこになにを観ることができるでしょう。舞台は拡がり、われわれの夢の世界にも及びますが、われわれは、つねに舞台に臨んでいるわけではありません。舞台から離れ、こちら側に世界に身を置くと、<他者>の場所において、いったいなにが起きているのかが探ろうとすると、われわれは、そこに、欠如manqueしか見出せません(V. A. p.84)。 ラカンにとって<他者>とは無意識です。マゾシストは倒錯者としてネガティフなものをポジティフなものとして舞台に乗せます。光学シェーマ(図34)で花瓶はSの側にあっては、主体はaという対象と一体となって示されます。小さな舞台とは幻想の式におけるpoinçonです。倒錯者と神経症者(ひとはときとして、少なからず神経症的なのでしょう)との関係は、フロイトも述べているように、写真のネガ、ポジの関係にあります。倒錯者の幻想といういい方は、神経症者からみた倒錯的シーンです。 事実、ラカンは続けてこう言います。 主体が<他者>の場所で自己を構成するところに、対象とその欠如は結ばれ、連繋ができるのです … (ibid)つまり、抑圧の回帰として現れるよりさらに溯って、原抑圧Urverdrängungが構成される地点、ひっそり隠れてけっして姿を現さない、とはいえ、原抑圧という語を使っている以上、まったく未知のものとは言えませんが、その地点まで溯って … その地点において、転移におけるわれわれの分析において、みなさんにはアガルマという語を用いて示したものが、その構造と位置が与えられるのです。この空の位置に、無視されがちであるのはもっともなことではありますが、転移の次元が成り立つのです。この場所が、縁、開口部、裂け目béanceとしてかたちづけられるなにものかによって縁取られているのですが、鏡像はこの縁取りの境界線です。この境界こそが不安のために選ばれた場所なのです。(2007/12/20) 『エクリ』所収の『ダニエル・ラガーシュの報告「精神分析と人格の構造」についての考察』において、光学装置は、ブアスの原図の場合は、視点OがB´を頂点とし、母線であるB´β、B´γ円錐の内部に位置していないと、錯覚は生じない(邦訳『エクリ』III 126頁)。ラカンによる凹面鏡と平面鏡との組合わせの装置(同、128頁)においては、眼は、やはり実線で示された円錐の内部で、また凹面鏡の延長として示される破線の楕円の内部に位置しなくては、花瓶のなかに入った花の像を見ることができない。 図36に記された花瓶の縁と平面鏡の上限から引かれた直線がその境界を示しています。この境界内に映し出されるものが、世界という錯覚であり、この錯覚は、承認の錯覚を生み、さらにはラカンがいうシーンも錯覚のシーンなのです。そしてこの境界はpoinçonあるいはlosangeによって表されるのです。 錯覚により映し出されるものは理想自我です。眼の位置をずらすことにより、錯覚が錯覚であることが解る訳です。自我理想は像の在-不在の象徴的取り込みにより成立してくるものです。因に像i(a)と理想自我、自我理想との関係については、ラカンはナルシシスムとの関連でとり上げることが多いのですが、一次性ナルシシスムのとり扱いについては時代によってさまざまです。
narcissisme primaire(ラカンはここではpremier narcissismeと言っている)は、au niveau de l'image réelle de mon schéma, pour autant qu'elle permet d'organiser l'ensemble de la réalité dans un certain nombre de cadre préformés (p.144)としている。 また さらに、 溯って XIV- La logique du fantasme. 1966-1967 XXIII-Le sinthome. 11 Mai 1976 Joyceにおいてはボロメオの輪に欠陥があり(つまり、無意識が現実界と結ばれており〔p.154〕)、RとSの輪は絡み目となっているため、Iの輪はそのままでは、抜け落ちてしまう(図、p.151)。これはエクリテュールにおけるラプシュスlapsus calamiに基づいているものです。Iの輪とR, Sの輪が離れないように、矯正的なエゴego correcteurが挿入される(図p.152)。 現実は、ちょうどエゴにかかわるものによって説明されますが、つまりは、快感-自我Lust-Ichは一次性ナルシシスムという段階があり、この段階の特徴としては、そこには主体は存在しないということではなく、内部と外部が関係を持たないということが挙げられます。 次回のセッションの導入がなされます。ドラの症例に続いて、「若き女性同性愛者の一例」として知られる、実名Sidonie Csilagの自殺企図(ウィーンの鉄道が通っている溝渠に身を投じたのですが、フロイトはこの行為をniederkommenという動詞を用いています)、6)行為化passage àl'acteの導入ですが、ラカンは女優であり高級娼婦であったLéonie von Puttkamerへの一途の愛は宮廷風愛amour courtoisに匹敵するものであり、相手はDameであり、かの女に花束を贈り続ける行為はまさに騎士chevalierのそれであり、現実に、Epel社から刊行されているInes ReiderとDiana Voigt(Thomas Gindeleの仏語訳)、Sidonie Csillag-homosexuelle chez Freud Lesbienne dans le siècleにはかの女の「バラの騎士」の衣装に身を包んだ、写真が掲載されています。Jean Allouchは"Ombre de ton chien- Discours lesbien"と題する書物のなかで、Dameに身を捧げる騎士道的愛をla chiennerie amoureuseと形容しています(ここでは犬chienあるいはchienneは哀れなものではありますが、愛における無償の忠誠の象徴です。マタイ伝のなかに出てくる犬もペジョラティフな意味でキリストの口から発せられますが、その実、神への忠誠を体現しています)。かの女の父親(ラカン曰く、かの女の父親に対する愛は大文字のPhiであったのですが)がInes Reiderと街角ですれ違ったときの嫌悪感をこめた一瞥、かの女に弟が生まれたこと、二人に対する町中の後ろ指を指すような蔑視、そしてフロイト自身の無理解と責任放棄、passage à l'acteは起こるべくして起きたといえましょう。しかもFreud自身、niederkommenという語を深く追究していませんでした。ラカンはル・モンド紙に"l'héroïne de UN métier de chien"という記事を書きました。ヴィクターの「蓄音機の朝顔から主人の声を聴くワンちゃん」のイメージを思い起こさせます。
|