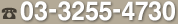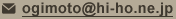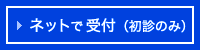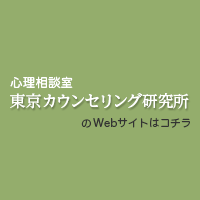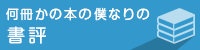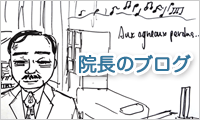|
ジャック・ラカン
 |
 (3) 1962 11 28 水曜日 黒板に図10が描かれます。 『鏡像段階』と『ローマ講演』との間にどのような橋渡しが必要なのか、とある人(アンドゥレ・グリーン)がラカンに執拗に問い詰めてきたことを吐露しながら、ラカンはまさにこのふたつの領域、鏡像とシニフィアンとの間には裂け目hiatusがあり、そしてこの日のセッションよりその裂け目について述べてゆくことになります。 さて、図10の説明に入ります(凹面鏡を用いた、いわゆる光学シェーマはセミネールI巻以来、何度も取り上げられ、エクリ所収の『ダニエル・ラガーシュの報告「精神分析と人格の構造」についての考察』で詳しく説明されます)。鏡といえば鏡像段階のことは既にご存知でしょう。赤ん坊は、鏡のなかのまとまりのある像、ゲシュタルト的によい形を、錐体路系の未発達(これに基づくキネステジー的機能が、バラバラの身体に繋がるのです)を補う視覚的優位(とはいえ、この人間特有の視覚がいわゆるカント的超越論的感性論という落とし穴を生み出し、ですからラカンはトポロジーを導入したのです。しかしこのことは、後日、然るべきとき述べることにします)に基づき,大喜びで自ら受け入れ、これが自我を形成する雛形となるとさしあったては要約できるでしょう。しかし光学シェーマは平面鏡(つまり鏡)だけではなく凹面鏡の効果も加わります。このセッションではまず、まず、2本の破線のうち、垂直のもの(青色)は想像的なもの、水平のもの(赤色)は象徴的なものに関わることが説明されます。垂直線では、平面鏡によるのとおなじく花瓶プラス花(a)が示されますが、これはセミネールVIIIにおける対象a、アガルマ的な対象ととりあえず捉えてかまわないでしょう),すなわちi(a)です。いっぽう水平線である象徴的なものにかかわる線については<他者>が関与してきます。赤ん坊は、鏡像を見た後に、必ずと言っていいほど、かれ(かの女)を抱いている大人(母親)の方に振り返ります。その都度、<他者>の承認を求めるのです。理想自我は鏡像、イマーゴですが、自我理想は<他者>の欲望が関与して来るもので、ちょうど前者は垂直線、後者は水平線と関係します。 アンドゥレ・グリーンとのやりとりがまた持ち上がります。ラカンはレヴィ=ストゥロースの『野生の思考』の4章「歴史と弁証法」に触れ、分析的理性を弁証法的理性に対峙させます。鏡像段階は段階ということばからして、また6ヶ月から18ヶ月のあいだの子供、先取りする、といった表現からして歴史的、弁証法的です。しかしながらラカンはマリエンバードでの発表当時から、つまり1936年当時から、鏡像段階についての諸概念を歴史的に理解しないで欲しいということを述べています。そもそも人間とは愚かなものであるので、歴史的に、アルケーがありテロスがあると説明しないと解らないから、ということでしょう。レヴィ=ストゥロースが弁証法的理性について批判で矢面に立たされているのはサルトルの『弁証法的理性批判』です。「歴史的」にものを語ると、つねになんらかのイデオロギーに拠りかかわらざるをえません。それがマルクス主義的なイデオロギーであれ、ブルジョワ的イデオロギーであれ … もちろん歴史の終焉も終焉というイデオロギーに拠りかかっていることは明らかです。この辺の問題は、レヴィ=ストゥロースがかれの研究をいわゆる未開社会に限定し、この社会に見出すことのできる構造から、「冷たい社会」société froideというものの存在を明らかにし、西欧においては、過去に支配-非支配の図式が複雑に絡み合い、あるいはこの図式が転覆されることもしばしばあった歴史というものがあり、勿論未来にも同様な展開が予想されるだろうから、これは「冷たい歴史」だけでは説明できないことを心得ていたのです。ただこの「熱い社会」société chaudeも「冷たい社会」の構造によって規定されているのであり「熱い社会」は「冷たい社会」プラス・アルファによる表現様態なのだと理解してよいでしょうが、この領域はレヴィ=ストゥロース自身、自分の守備範囲外だと慎重な姿勢を保っていたのでしょう。もちろん歴史を勉強しなないなど問題外です。しかしそこには、ランガージュとパロールの関係があるということを踏まえておかねばならないでしょう。20世紀は戦争の世紀でした。21世紀はどうなるのでしょう。テロリズムの世紀になるかもしれません。そこまでとは行かないまでもNation-Stateというものが糾弾される世紀になる、あるいはグローバリゼーション対民族主義という対立が際立ってくる世紀になるか、はたまた、科学主義の頓挫ののちに現れる宗教の世紀となるかもしれません。ランガージュとパロール云々とは、過去現在を反省しようとすると、そこには人間の主体というものがあり、戦争に加担したのも、そのことを後悔するのも人間の主体だということですが、それでもすべての人間の主体は歴史と呼ばれるものに飲み込まれてしまうからです。「今を生きる」、ラカンがactualitéということばに込めた意味はそうゆうことなのでしょう。サルトルはこの「今を生きる」あるいは「時代を背負っている」ことを自認し、いわゆるengagementを地でゆく生き方をしていった人でした。そのようにして哲学書も小説、戯曲も書いてゆきましたし政治色の濃いパフォーマンスを演じていきました。死ぬ直前になってかれはこのような生き方に後悔したか、デカルトのように仮面を被って前進するlavaus prodeoような人生にすべきだったと思っていたかはわかりませ。だれにとっても後悔とは後の祭りなのでしょうからどうしようもありません。しかしラカンはこのactualitéの困難さを十分理解していました。 やや脇道に逸れましたが、ラカンはというと、フロイトの「別の場面」der anderer Schauplatz, autre scène (Die Traumdeutung, G.W. II/III. p.541) について話を進めようとしてこのscèneということばにつられてか話は飛びます。セミネールVIでかなりの時間を割いて取りあげたハムレットについて、さらに分析を深めようとします。劇中劇のシーンから話が始まりますが、このシーンで不思議なのは、先王であるハムレットの父親を殺した犯人が現王である弟クローディアスであるはずなのが、劇中劇の犯人ルシアーナスなる人物は王の甥、つまり現王クローディアスとの関係でゆくとハムレット自身ということになってしまいます。動揺したのはクローディアスよりもハムレットだとラカンは言います。その後のハムレットの運命を決定するのは、復讐とて罪であり、それを成し遂げることになるのですが、それはかれ自身の鏡像であるルシアーヌスによって前兆として示されるのです。フロイトが『喪とメランコリー』で強調しているのは、対象を喪失したことに際して、この対象との同一化に対する悔恨です。ハムレットにおいて、同一化の対象はオフェーリアです。そしてかれの鏡像はオフェーリアの兄でもあり、ハムレットと同様、対象であるオフェーリアを共通にするレアチーズでもあり、勝負の相手はクローディアスではなくかれに向けられる、これがラカンの解釈です。 対象については、この年のセミネールをとおして展開されますので、その都度説明するとして、このセッションにおいても欲望の対象objet du désirという表現が用いられていますが、ここで出てくるラテン語desideriumは動詞desideroの名詞型でdesideroがフランス語のdésireの意味をもつほかに、「… を喪失したことを嘆く」という語義があることから、desideriumは「かって所有あるいは見知っていたものがいまは欠如しており、その欠如に対する欲望」といった語義になります。objet cause du desirまで今一歩です。
… 想像的なものにが向かう先は、ファロスが、欠如のかたちとして、つまり-φで示されることになり、ここで描かれるi(a)、わたしが現象と呼んできたものと相当するものです。主体を素材によって捉える、つまり身体のイメージの構成にはまさしく想像的な機能が働くのですが、それはリビドーの備給が行なわれるということです。ファロスはこのイメージのなかではマイナスのものとして、空白として現れます。ファロスは、おそらくリビドーの予備タンクみたいなものでしょう。といっても、ファロスは単に想像的次元で描かれないだけではなく、輪郭は与えられるのです。いわば、鏡像から切断されてです… (sic. V. A.) 昨年度はクロス・キャップについての説明を試みましたが、そこに、話の展開上この展開を繋ぎ止めるため重要なピンとも呼ぶことのできるあるものをこのトポロジーのもつ両義的な領域に付け加えるため … (sic. V. A) トポロジーが、想像的与件を極限まで扁平化させ、一種の超空間のなかで演じ、煎じ詰めるとこの超空間はシニフィアンの純粋な分節から成り立っているということになり、それでいて、直観的に捉えることのできる諸要素がわれわれに現れてくるのです。これらは、この奇妙な像、クロス・キャップによってみごとに表される像によって支えられている要素です。クロス-キャップについては、一ヶ月以上わったって、みなさんの前でいろいろ手を加えてお見せしましたね。ですから、どのようにかお解りでしょう。このような曲面(図12)でのことでしたね 。ここでは繰り返して実演することはしません。お解りでしょう、切断によってふたつの異なった小片(図13)が得られます。ひとつは鏡像として現れるものb、もうひとつは文字通りaで、鏡像のなかには見えません(V.A.p36)。φは鏡像では- φですから現れてきません。しかし、それは性器に結びついていて、全面的な自我備給、つまり鏡像への自己愛的同一化から主体を引き離すためのリビドーの蓄えという意味での予備タンクです。この蓄えのおかげで、欲望は満足(実際、ラカンはsatisfaction du désirという言い方をしていますが、欲望には満足が与えられません)を求めて対象に向かいます。いわゆる対象備給に要するエネルギーはここから得られるのです。そして対象とは超越論的感性では捉えることのできないものです。このカント的直観形式では捉えることができない対象というものをめぐって、いかに精神分析はフロイト以降迷妄に陥ったことか … 1) 1) 前述しましたが、自明のことですが、鏡は平面です。光学シェーマでは凹面鏡の効果が重要ですが、ラカンはこの凹面鏡のことをsphérique球面鏡と呼んでいます。ラカンは光学シェーマを用いて究極的には人間の超越論的感性の限界を示し、この限界を超えるためにはどうしてもトポロジーに頼らなくてはならなくなりこれを導入したのではないでしょうか。次のように考えてみてはどうでしょうか。人間が観ている世界とはなんと奇妙なシーンなのでしょうか。遠近法も自明のこととされていますが、なにも遠近を遠くのものは小さく見える、近くにあるものは大きく見えるといった図式で捉えなくても可能なはずです。例えば遠くのものはぼやけて見えるあるいは暗く見える、近くにあるものははっきり見えるあるいは明るく見えるでも遠近感は生まれます。人間の遠近法では消失点point de fuiteというものがありますが、人間の視野がもし360度近くあり、網膜も凹面ではなく球面だとしたら、消失点もないでしょうし、自分を映し出すため、鏡は平面鏡では役に立たず、視覚器官がやはり球形であるとすればその中心点から等距離にある球面の内部がすべて鏡になっている球面鏡を用いることになるでしょう。完全に360度の視野というものを想定すれば、そこには左右という方向性orientationは意味のないものになるでしょう。いずれにせよ人間は平面というものにこだわります。鏡以外にも、文字が書かれている書物、タブロー、写真、映画のスクリーン、地図(実際、地図を作成するためには多様体理論を援用しなければなりません)そしてユークリッド幾何学 … 平行線の定理をめぐって非ユークリッド幾何学は生まれました。人間の思考にとって「見る」という営為がどれだけ重要視されてきたかは、例えば理論(理論理性の理論からしてそうです)théorieの語源を調べると理解できると思います。ラテン語のtheoria(思弁的研究recherche spéculative)はさらに古代ギリシャ語のthéôriaから派生してきており、これはⅠ見る,観察する、調べるという行為Ⅱ観劇(Le RobertのDictionnaire historique de la langue françaiseによると宗教劇に遣わされた役者グループで、この劇で神託が告げられた、とのことです。ハムレットの劇中劇もまさにこれですな … 失礼また脱線です)Ⅲ観想(プラトン以降)という語義があり、同辞書ではthéôriaもthéôros観客から派生した語であるとしています。また思弁的spéculatifという語も低ラテン語のspeculativusから借りてきた語で実践的に対する反省的、理論的を意味します。動詞spéculerはラテン語speculariからの借用で、これは、「観察する」、「ねらう」、「スパイ的監視をする」という語義があり、specula(「観察を行なう場所」、「高所」の語義があります)から派生したもので、さらにこの語もspecere(「注視する」という語義があります)から派生したものです。spéculerにはspécutacle, spéculaireといった関連語があります。spéculaireはラテン語spécularis(「鏡の」という形容詞)からの借用で、それはspeculum(「鏡」、転じて比喩的に「忠実な再現」、「像」という語義があります)がもととなっていますが、現代フランス語では、speculum anal肛門鏡, speculum nasal鼻鏡のように、医療機器の名称として用いられています。ラカンは、人間は3次元空間に埋めまれているplongéと言いますが、この心的に欠陥のある生き物(つまり人間のことです)は往々にして次元をひとつ次元を下げて見ないとものごとが理解でいないようでして(みなさんが見ているこのディスプレイもこのページをプリント・アウトして印刷されるのも紙という平面です。また、医療機器に話が及んでしまいましたのでついでにですが、MRIなどにおいては、MR信号を周波数変換してからディジタル変換して得られた実数部と虚数部からなる、つまり複素数からなるraw dataの集合 - これをk-spaceと呼びます - を二次元フーリエ変換してはじめてMR画像になるのです。もし人間に心的欠陥がなければ、raw dataの時点で、あるいはせめてもk-spaceの時点でことを把握できるとはいえないでしょうか)、晩年のラカンがとくに注目していた結び目のトポロジーも、結び目を結び目として規定できるのは3次元においてだけのようです(狭義の結び目においてはたしかにそのとおりなのですが、ボロメオの結び目は厳密な意味においては結び目ではありません。また絡み目でもありません)が、ラカン自身が黒板に描いたものもVappereau氏が保有しているノートに描かれているものも平面化mise à platされているのです。ところで本セミネールで出てくる曲面であるクロス・キャップなどはふたつも次元が下げられて描かれているのです。これからしばしばラカンはこの曲面に言及しますが、次元のことは重要と思い、ここでさし当って述べさせていただきました。 最後にラカンは図8に戻ってコメントを加えます。鏡像i(a)は<他者>の承認を余儀なくされ、それは右側の像として示されます。i'(a)は実像i(a)に対して虚像image
virtuelleとされます。- φは左側でもそうだが、右側にも見ることも、感じることも、示すこともできない、とラカンは説明しますが、詳しくは次回に、とこの話を閉じます。幻想の式S
barré poinçon petit aについて、このpoinçonを今までとは違った読み方で説明すると予告もします。ここでは、幻想における欲望の支えであるaは、人間にとって、かれの欲望の像としては見ることができない、また、aの現前は人間にとってもっと間近に見られ、それは欲望の始まりinitium
du désirであり、だからこそi'(a)は価値のあるものになる、と道しるべは示します。一方でこの欲望の対象(とまだ言っていますね)のなかで(といっても、しばしば不適切に対象関係の完全なる道などと呼ばれていますけれども(V.A.p.38)、と断わります。そろそろ「欲望の対象」という言葉はお払い箱であることが予感されます)i'(a)に飛びついたりすると、騙されますよ、と念を押します。 |