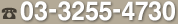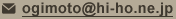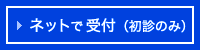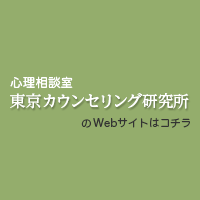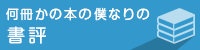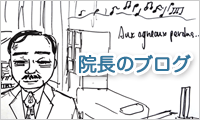|
ジャック・ラカン
 |
 (2) 1962 11 21 水曜日 黒板には図6、図7が書かれます。 雄カマキリとみなされた哀れな男(ラカン)の目の前に巨大な雌カマキリがいます。つまり目の前に<他者>がいるわけです。désir de l'homme est désir de l'Autreという有名なラカンの定式があります。このdésir de l'Autreのdeとはまずは主格的属格であり、<他者>がもつ欲望の意味になりますが、このセミネールが始まるに先立って行われた、地方での会合でのかれ自身の発表に言及し、<他者>を目的属格としても理解することができることを述べます。そうすると、主体の欲望が<他者>に向けられる、という意味になります(V. M. : p.32 ; V. A. : p.23)。この両義性はそこに絡む,いわゆる相互主体性、相互主観性をさらに強調することになります。この定式は、Alexandre KojèveのÉcole pratique des hautes études第4部門での1933-39年のヘーゲルの『精神現象学』の講義(Alexandre Kojève, "Introduction à la lecture de Hegel", TEL, Gallimard)が下敷きになっていることは皆さんご存知のことと思います。実際、コジェーヴの講義においても、中心に据えられているテーマは、(B)「自己意識」のAのなかの「主と奴」における、他者とのあいだの承認をめぐる欲望でした。しかしラカンはヘーゲルでもコジェーヴでもありません。 他者と欲望に関して、此彼の違いをラカンは4つの不等式図8によって説明します(V. M. : p.33- ; V. A. : p.24-)。ヘーゲルにとって<他者>は意識です。<他者>はわたしを見ています … そこからわたしの欲望も引き起こされます、とラカンは述べた後、自説を述べます。 ラカンにとっては、言わしていただければ、ラカンは分析家ですから、<他者>は、分析においては無意識として位置づけられます。そしてこの<他者>がわたしの欲望を引き起こします。この欲望がかれには欠けていて、そのことをかれは知らないかぎりにおいてそうなのです。この、かれには欠けている、かれは知らないというところにおいて、わたしは含みをもたせたかたちで引き寄せられるのです。というのも、わたしにとってそうするしかないので、わたしの欲望の対象としてわたしに欠けたものを探し求めるのです。それゆえ、わたしには、ただひたすら、それがどのようなものであれある対象へと向かう、わたしの欲望の入り口も支えもありません。ただ、<他者>への避けられない依存にあるS barréで示されるものへ欲望を結びつけ、縫い合わせる道だけは残されます。 式1/は、ヘーゲルの欲望の式です。ヘーゲルの他者は欲望する者として主体も同様の欲望をもつことを必要とします。主体から承認を受けるためです。他者が欲するものはaです。ここにあらゆる袋小路の元凶があります。「わたしが対象として承認されるのであれば、そしてこの対象は見てのとおりそもそも意識、自己意識ですから、暴力以外による解決はありえません … ふたつの意識のあいだで裁断を下すことがどうしても必要になる」からです。 式2/はラカンの式です。欲望の支えとなっているイメージつまりd(a)のi(a)について、ラカンはここでは曖昧さを残したままにしておきます。というのも、ここまでラカンはi(a)を鏡像としてきたからです。さしあたって、「鏡像の表記によってカヴァーできるファンタスム」とします1)。<他者>の欲望とこの像とは等価であり(ヘーゲルの場合は欲望イコール他者の欲望であることが式(1)で示されています)ますが、ここでは<他者>はA barréとなっています。「なぜならば、<他者>の地点で欠如がはっきりと表されてくるから」です。 1)ファンタスムの問題は後日、対象aをめぐって、倒錯において享楽との関係を含ませながら、特にサドと法との関連で展開されますが、セミネールVII巻以来展開されてきたこのテーマはこのセミネールにおいて完結するわけではありません。セミネールXIV、XVII、XIXへと続きます。 式3/,4/は表記方法は異なるものの同一のことを言っているのです。3/は方向性をもっていますが4/は二段になっていて、左側に括弧によって番になっており、上段下段を左右に並べると、左から右に行っても右から左に行っても結局もとに逆戻りになる構造をもっています。3/は「不安はヘーゲルの定式の真の姿を示すもので、この定式は不公平、不正であり、『精神現象学』を座りの悪いものにしてしまっている …」とラカンは言い、次のように続けます。 何度も指摘してきましたが、倒錯は政治の領域にまで及んでしまうのです。想像界にだけ捕われてそこから出発するとそうなるのです。というのもこう言えば的を得ているでしょう。つまり、奴隷の隷属は影響力大で、これは絶対知にまでも影響を及ぼすのです。言い換えれば、奴隷は世の果てまで奴隷で居続けることになるのです。ヘーゲルさんへマをやらかしました!ヘーゲルの定式の真の姿、これをキルケゴールはちゃんとした形で表します。これはヘーゲルの真理ではなく不安の真理となります。不安こそが分析でいう欲望についての考察へとわれわれを導くのです。(V.A.pp.25-26) 最後の式は不安の真理の式です。この式で不安と欲望が関係づけられます。ヘーゲルの式1/では「対象aが欲する」というパラドキシカルな命題が含まれていますが、この式とラカンの式2/との違いは、ヘーゲルの式においては、主体が対象であり、有限性を救い難い形で刻印された主体/対象の元凶なのでありまして、自己意識のアポリアをそこに読み取らねばならないんですと …2) 2) どうです皆さん、少なくともここでのラカンは見事なまでアンチ・ヘーゲリアンです。『歴史の終焉』『イデオロギーの終焉』と誰かさんは言いますが、体制側の御用学者は「もう終わったのだ、これが最終的具現パルーシアなのだよ。みんなハッピーで、ようするにハピー・エンドだからだれも文句あるまい」と言います。なにせヘーゲル自身がそうだったのですが。少なくともかれは御用哲学者ではありましたが … 誰かさんは御用なに学者なのでしょうか、かれのスローガンを逆転させればその真理は明らかになります。この言説は『終焉のイデオロギー』に属するものだと。 精神分析は自己意識が自己に対して透明であることをけっして要求いたしません。ヘーゲルの道を逆戻りするようなことはしませんが、他者との死を賭けた闘争に持ち込むことも絶対いたしません。われわれは欲望が絡んだ対象とはなり得るとしても、そこには無意識というものが介在します。 たしかにわれわれ、有限性が刻印されてるかぎりでわれわれのわれわれにとっての欠如、無意識の主体は有限の欲望となりえます。しかしみかけ上は有限とはいえ無限定です。というのも、欠如manqueはつねにある空videを分有しており、空はいろいろな方法で埋めることができます。しかしわれわれは分析家ですから知ってます。どんな手を使ってでもこの空を埋めることなどいたしません(V.A.p.26)3)。 3) この後、ラカンは有限と無限について、欲望の無限性という偽無限はシニフィアンの理論に還元できるとしています。すべての整数といえば、その組合せが無限に存在するとしても、シニフィアンとしては0から9までの10個であり、2進法では2で済みます。例えば超越数である円周率πも十進法で3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 … と表記できます。これが無限定であるとしても、その都度この後には0から9といった離散的なシニフィアンが続く(ことになる)でしょう。つまりそこには反復が認められます。もちろんラカンにとっては、反復とはプラトン的なアナムネーシスではなくその都度刷新されるキルケゴール的な反復です。メトニミーの反復とはこのような反復なのです。 いつの間にか、ラカンは図9に向かいます。まずAがあり、シニフィアンの場として規定されます。Sはいまだ存在しないものですが、シニフィアンによって決定されることになります。真んなかに縦線が引かれますがこれが分割divisionという操作(「割り算という演算です」とも翻訳できます)です。主体はAに従属しており、割り算の商としてS barréであり、Aの場所にあって、シニフィアンの一本の線trait unaireを記されたものです。同様にシニフィアンはAを輪切りにするとしても、そこには割り算の余りが生じます。この余り、無理数、<他者>の他者性の唯一の保証、これがaです。シニフィアンの線が記された主体、S barréといわば<他者>のプロパガンダのため駆り出された余りとしての対象a、これらは同じ側にあり、線が引かれる対象であり、<他者>の側に位置 づけられます。わたしの欲望の支えであるファンタスムも、S barréとaとでその全体として、<他者>の側にあります。わたしの側には、わたしを無意識として構成するもの、つまりA barré、わたしが到達できないものが位置づけられます。 時間が少し余って、ラカンはアンチ・ヘーゲリアン色を強く訴えます。他者性の克服は「おまえを愛す。仮におまえがそれを望まなくとも」といったヘーゲル的希望的観測の定式で示されることに対して、精神分析の定式は「わたしはおまえを欲する、仮にわたし がそのことを知らなくても」(V.A.P.27)4)となります。 4)とくにヘーゲルのフランクフルト時代の論文『キリスト教の精神とその運命』には、愛を法(ユダヤ的律法とカントの道徳論の立場の法)の止揚と規定します。Cohenによれば、judaïsmeとkantismeはloi
positive(ここでいうpositiveとはnaturelleの対立概念です。カント自身の宗教観にしたがえば、かれ自身は理神論déismeの立場をとりthéismeと対立することになります)にとどまっている、ということになります。この法はまったき他律性、つまり人間の精神(ヘーゲル
…そこでわれわれは欲望のステータスを省みるため立ち止まる。欲望は法の媒体に対して自律的なものとして示される。むしろ欲望から法が成立するからである。この事実ははこうである、奇妙なシンメトリーによって、欲望は、愛の要求の無条件性をひっくり返す。そこでは主体は<他者>に従属しているが、この<他者>を絶対的な条件の力へと向ける(ここでの絶対性l'absoluとは離脱という意味をも持つ)(Ècrits, p.814)。 それゆえラカンにとって、絶対知(同書, p.802)は非-知によって裏打ちされているといってよいのです。このことはすでにハイデッガーの1930-31年の『ヘーゲルの精神現象学』の講義において述べられています。絶対知der absolute Wissenに関して、「解き離しを行ない〈absolvent〉- 解き放ちAblösungに携わり-揺れ動来つつ絶対的である知」、また「絶対者の本質は、無-限な解き離しの遂行die un-endliche Absolvenzであり … 」とあります(Martin Heidegger, Hegels Phänomenologie des Geistes, Vittorio Klostermann, p.71 ; 邦訳, ハイデッガー全集, 第32巻, 95頁, 藤田等訳, 創文堂)。 (2007/09/06) |